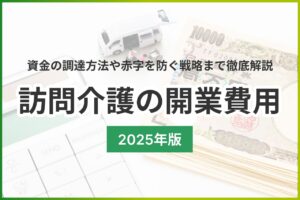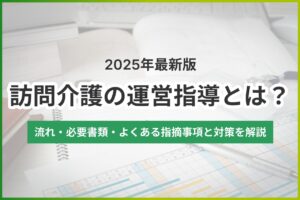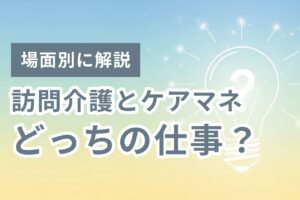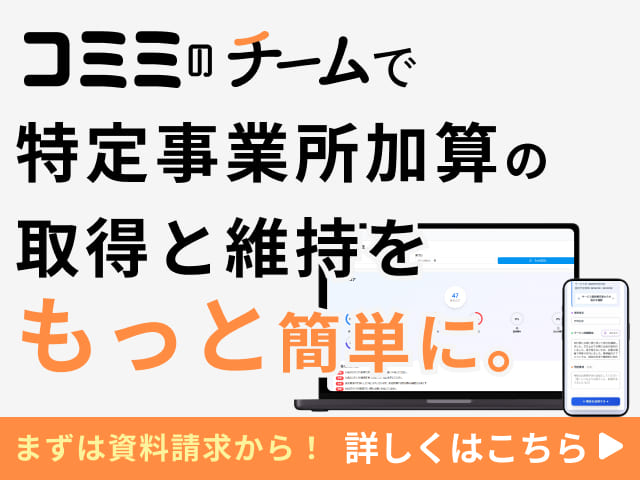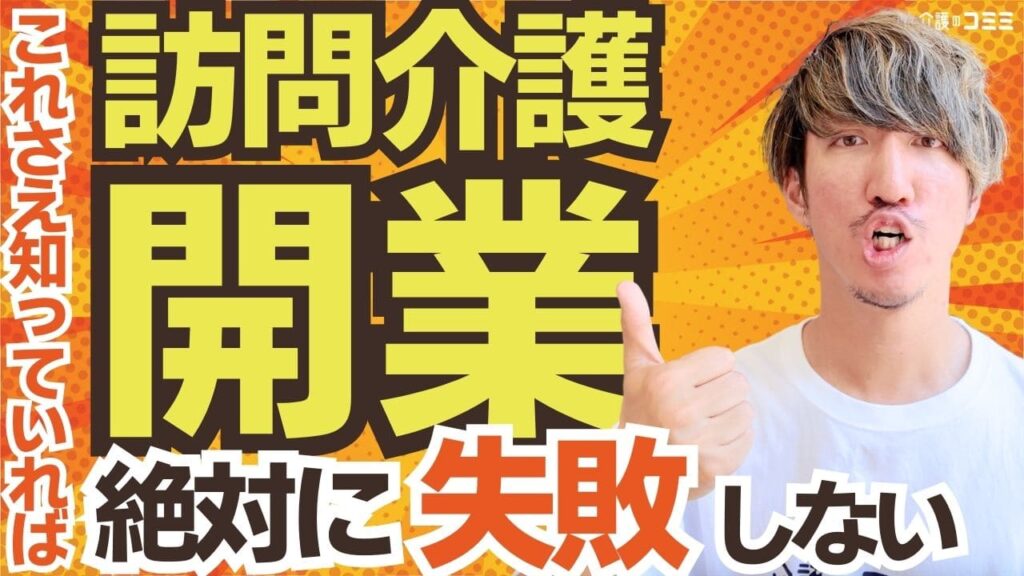訪問介護の開業・立ち上げの手順 | 必要な資金・手続き・失敗例まで徹底解説
介護施設の経営・運営改善
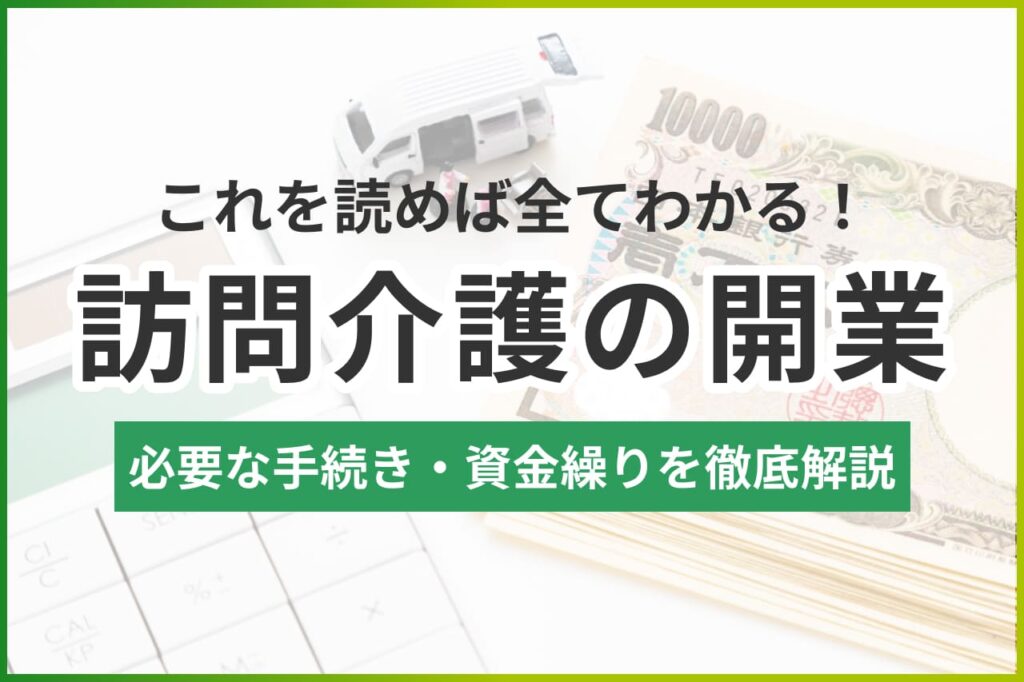
少子高齢化が進む日本において、「訪問介護事業」は今後ますます重要性が増す分野です。介護のニーズが高まり続ける中で、「自分で訪問介護事業所を立ち上げたい」と考える方も増えています。
しかし現実には、毎年100件以上*の訪問介護事業所が倒産・廃業していることをご存知でしょうか?
*参考:東京商工リサーチ「2024年度「介護事業者」倒産 最多の179件 前年度から3割増、報酬改定の「訪問介護」が半数」(2025年4月)
これだけ見ると「今の時代に訪問介護の開業は厳しいのか」と思われるかもしれませんが、失敗事例が多い分開業前にしっかりとノウハウを押さえておくことで成功に導くことができる可能性も高いです。そこで、本記事ではそんな厳しい環境の中でも「生き残る事業所」をつくるために、開業前に知っておくべき全体像・注意点・成功のヒントをわかりやすく解説します。
訪問介護事業所の新規開業・立ち上げを検討している方は、ぜひ最後まで読んで参考にしていただけると幸いです。
開業前に知っておくべき訪問介護事業の基本!サービス内容と売上の仕組
- ステップ1. 法人設立の手続き
- ステップ2.事業計画の策定 - 失敗しないための最重要ポイント
- ステップ3.事業所物件の選定と準備
- ステップ4. 人員基準を満たすスタッフの確保
- ステップ5. 設備・備品の準備
- ステップ6.介護保険事業者の指定申請手続き
- ステップ7.開業前の最終準備と確認
- ステップ8.事業開始〜開業後の運営準備
※訪問介護の開業に必要な資金や具体的な調達方法については、以下の記事でより詳しく解説しているので、資金面や経済面で不安がある方はぜひ併せて参考にしてください。
開業前に知っておくべき訪問介護事業の基本!サービス内容と売上の仕組
訪問介護のサービス内容とその対象者を知ろう
訪問介護は、介護保険制度に基づくサービスの一つで、要介護または要支援の認定を受けた高齢者の自宅を訪問し、日常生活の支援を行うサービスです。訪問介護で提供するサービスは、大きく以下の3つに分けることができます。
身体介護
身体介護とは、利用者の身体に直接触れて行う介助のことを指します。具体的には、入浴介助、排泄介助、食事介助、衣服の着脱介助、体位変換などがあります。これらは、利用者の自立支援を基本としながらも、安全かつ快適に日常生活を送るために必要不可欠な支援です。
生活援助
生活援助は、身体に直接触れずに日常生活を支える支援を指します。掃除、洗濯、食事の準備や片付け、買い物代行など、利用者が自力で行うことが難しい日常的な家事全般を対象としています。
通院等乗降介助(その他)
通院等乗降介助とは、介護タクシー等の手段を使って、利用者が病院や通所サービスに通う際の移動を支援するサービスです。単なる移送ではなく、「乗車前後の移動・乗降の介助」や「通院時の院内付き添い」が含まれることもあります(自治体の指定基準によって異なる)。
対象は要介護1以上が原則で、必要に応じて介護保険内での算定が可能です。
訪問介護における売上・収益の仕組み
訪問介護事業所の売上・収益は、介護保険法によって定められている単位などから算出する介護報酬という形で得ることとなります。具体的には、訪問介護の場合は以下のような計算方法で介護報酬が算出されます。
地域区分 × サービス単位(基本報酬 + 加算) × 1ヶ月の訪問件数 = 売上
以下では、具体的な地域区分による単価や、サービス内容ごとのサービス単位について解説します。
訪問介護における地域区分ごとの1単位の単価
まず地域区分とは、指定を受けている事業所が所在する市町村に応じて、1〜7級地とその他の8区分*に分けらたものです。
*具体的な市町村ごとの区分は「地域区分について」(厚生労働省)をご参照ください
2025年現在で、これらの地域区分ごとに定められている訪問介護におけるサービス単位1単位あたりの単価は以下の通りとなっています。
| 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10.00円 |
訪問介護のサービスごとに算定される単位
サービス単位についても、具体的に提供するサービス内容によって算定できる単位(基本報酬)が以下のように異なっています。
| 種別 | 項目 | 単位 | 1件あたり売上* |
|---|---|---|---|
| 身体介護中心 | 20分未満 | 163単位 | 約1,858円 |
| 20~30分未満 | 244単位 | 約2,782円 | |
| 30分以上1時間未満 | 387単位 | 約4,412円 | |
| 1時間以上1時間半未満 | 567単位 | 約6,464円 | |
| 生活援助中心 | 20分以上45分未満 | 179単位 | 約2,041円 |
| 45分以上60分未満 | 220単位 | 約2,508円 | |
| 通院等乗降介助 | 97単位 | 約1,105円 | |
*地域区分を1級地とした場合の単価で算出しています
なお、上記の基本報酬は令和6年の介護報酬改定にて、訪問介護については以前の単価よりも引き下げられることとなってしまいました。
そのため、訪問介護事業所が従来の水準で売上を維持するには、基本報酬に加えて加算を算定することがより重要となっています。加算の仕組みや、訪問介護で算定できる加算の種類については以下の記事でわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
訪問介護で算定できる加算のうち、最も売上向上に大きな影響を与えるのが特定事業所加算です。この特定事業所加算の最上位区分である加算(Ⅰ)を取得すると、加算率20%が適用されるため、立ち上げ初期から算定できると経営失敗のリスクを大きく減らすことができるでしょう。
特定事業所加算については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
介護のコミミでは、訪問介護の特定事業所加算の取得や維持を手助けする「コミミのチーム」というサービスを新たに開始しました。
加算の取得や維持に必要な事務作業を大幅に軽減することができるので、ぜひ加算の取得とともに導入を検討してみてください。
訪問介護の倒産数はなぜ増加しているのか?
東京商工リサーチの発表によると、訪問介護事業所の倒産件数は近年上昇傾向*にあります。背景には次のような課題があります。
- 人手不足によるサービス提供の限界
- 利用者の獲得競争(地域によっては競合が多数)
- 指定基準や運営基準の遵守が不十分で、指定取消しや加算取り下げにつながるケース
- キャッシュフローや資金繰りの甘さ
*参考:東京商工リサーチ「2024年度「介護事業者」倒産 最多の179件 前年度から3割増、報酬改定の「訪問介護」が半数」(2025年4月)
つまり、「人が足りない・儲からない・書類が難しい」と三重苦に陥りやすい業界なのです。
だからこそ、「なぜ失敗するか」を開業前に知っておくことが、最初の倒産予防策になります。訪問介護の失敗要因や、それを防ぐための対策案についてはこの記事の後半で解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。
それでも訪問介護を開業すべきか?
訪問介護の倒産が増えていると聞くと「開業しない方が良いかも」と思うかもしれませんが、ネガティブな話ばかりではありません。むしろ、制度的・社会的なニーズは今後も右肩上がりに増加していくと考えることができます。以下はその根拠です。
- 2040年に向けて高齢者人口はピークを迎え、在宅介護ニーズが急増している
- 「地域包括ケアシステム」の構築が国策として進行している
- 2024年度介護報酬改定で、ICT導入や介護職員の処遇改善に関する新たな支援策が拡充した
このことから、従来の失敗要因をしっかり防ぐことができれば、訪問介護には持続可能かつ社会的意義の強いビジネスモデルを築ける可能性があることがお分かりいただけるかと思います。
訪問介護を開業するまでの道のり
訪問介護事業所の開業は、4〜6ヶ月の計画的な準備が一般的です。例えば東京都では事前申請が開業4ヶ月前に必要*であり、確実な立ち上げには十分な準備期間を確保することが重要です。
*参考:東京都「介護保険事業者指定のガイドブック」
立ち上げまでの道のりとしては、以下が基本的な流れです。
- 法人の設立(株式会社や合同会社など)
- 事業計画の作成と資金調達
- 事業所の物件選定と設備の整備
- 人員基準を満たすスタッフの確保
- 介護保険事業者としての指定申請
- 事業開始に向けた最終準備と確認
この流れを把握しておくことで、「何を・いつまでに・どの順序で」準備すべきかが明確になります。
最短3ヶ月での開業が可能な場合もある
以下の条件が整った場合のみ、最短で3ヶ月程度での開業も可能です。
- 法人が既に設立済み
- 主要人材(管理者・サ責)が確保済み
- 事業所物件が決定済み
- 自治体の指定申請スケジュールに余裕がある
訪問介護の開業準備から事業開始までの手順
上述の手順で記載した各ステップの詳細を1つずつ解説します。
ステップ1. 法人設立の手続き
訪問介護事業を行うには、まず法人格の取得が必要で、多くは「株式会社」「合同会社」「NPO法人」などの形態が選ばれます。以下にて、これらの法人格の概要や違いを解説するので、ご自身の目的に応じた法人格の取得を検討しましょう。
株式会社とは
株式会社は、最も一般的な法人形態であり、訪問介護事業を営む上でも選ばれることが多い法人格です。出資者(株主)と経営者(取締役)が分かれているのが特徴で、資金調達の自由度が高く、信用力も相対的に高いとされます。
訪問介護事業においても、後々の事業拡大や融資を想定している場合は株式会社が適しています。定款認証が必要で設立コストはやや高めですが、銀行や行政、取引先からの信頼を得やすい点がメリットです。
合同会社とは
合同会社(LLC)は、設立費用を抑えられ、経営の柔軟性が高いことから、近年選ばれることが増えている法人形態です。出資者と経営者が一致する「社員」主体の仕組みで、株主総会や取締役会などの設置義務がありません。
訪問介護事業を小規模で始める場合や、身内だけで経営する予定である場合には、合同会社は合理的な選択です。設立後の事務負担も軽く、法人登記費用が株式会社より安いのも魅力です。ただし、認知度がまだ低いため、一部の金融機関では株式会社に比べて信用力が劣ると見なされることもあります。
なお、個人事業主としての指定申請は基本的に認められていないため、必ず法人化しましょう。
NPO法人とは
NPO法人は、営利を目的としない特定非営利活動を行う法人で、地域貢献や社会課題の解決を目的とする訪問介護事業に適している場合があります。収益を上げることは可能ですが、その利益は構成員に分配せず、事業活動に再投資することが求められます。
NPO法人を選択する場合は、設立に時間がかかることや、所轄庁(都道府県・政令市)への認証申請が必要である点に注意が必要です。一方で、地域福祉との親和性が高く、助成金や寄付の対象になりやすいなどの社会的メリットもあります。
ステップ2.事業計画の策定 – 失敗しないための最重要ポイント
事業計画は、「創業融資の審査」「指定申請の基準確認」「開業後の経営安定」に直結する非常に重要な工程です。特に以下の3点は重点的に作成してください。それぞれの注意ポイントを簡単にまとめてみました。
サービス内容・提供エリアの決定
- 「生活援助中心か?」「障がい者支援も行うか?」など方針を明確に
- エリアは「自治体の指定区域」に注意(営業所と訪問範囲のバランス)
収支計画・資金繰り計画
- 月次損益(PL)とキャッシュフロー表を作成
- 利用者数シナリオ(悲観・現実・楽観)ごとの収支見込みも有効
資金繰りを検討する上で、必ず加算の取得・算定についても併せて検討しましょう。
加算は基本報酬に上乗する形で得られる貴重な収入源で、訪問介護事業所が算定できるものだけでも10件以上あるので、加算による売上への影響度や、算定できる加算の種類については以下の記事をぜひ参考にしてください。
また、介護ソフトなどをはじめとするICTツール導入の検討も、このタイミングで併せて進めておくと、より精緻な事業計画を立てることができます。以下の記事では、訪問介護で実践できるICTツールについて紹介しているので、資料請求や見積もりなどを早めに進めておくと良いでしょう。
人員計画
- スタッフの配置数・採用時期・給与水準などを設計
- 加算算定に影響するため、常勤換算や資格者数に注意
ステップ3.事業所物件の選定と準備
事業所は事務所兼スタッフの拠点として必要であり、以下の条件を満たす必要があります。
- 独立した事務スペースの確保(住居併用は要注意)
- 通信・情報保護のための設備(鍵付きキャビネット、パソコン等)
- 法人の所在地と事業所の住所が一致していることが望ましい
※物件の賃貸契約時に「介護事業で使用」と明記しておくとトラブル防止になります。
ステップ4. 人員基準を満たすスタッフの確保
訪問介護は人員配置基準が明確に定められていて、以下の要件を満たさないと指定を受けることができません。特に常勤換算2.5人以上の計算は複雑となるため、ここで詳しく解説します。
必要な職種・人数・資格要件
| 職種 | 人数 | 資格 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1人 | なし |
| サービス提供責任者 | 1人以上(利用者人数40人を超えるごとに1人追加する) |
|
| 訪問介護員(ホームヘルパー) | 常勤換算で2.5人以上 |
|
サービス提供責任者については、以下の記事で詳しく解説しています。
常勤換算2.5人の正しい計算方法
常勤換算とは、「勤務時間 ÷ 常勤者の勤務時間」で算出します。一般的に常勤者の勤務時間は週40時間(1日8時間×週5日)とされます。
常勤換算 = 各職員の週勤務時間の合計 ÷ 40時間
常勤換算の計算例
| 職員名 | 週勤務時間 | 常勤換算 |
|---|---|---|
| 常勤職員A | 40時間 | 1.0 |
| 非常勤職員B | 25時間 | 0.6 |
| 非常勤職員C | 20時間 | 0.5 |
| 非常勤職員D | 15時間 | 0.3 |
| 合計 | – | 2.4 |
上記は4名の職員の勤務時間から計算した常勤換算の例ですが、合計して基準の2.5人を満たさないため、要員の追加が必要となります。
人員基準クリアのチェックポイント
これらを踏まえて、以下のようなチェックポイントを設けておくと、人員基準のクリアを確認することができます。
- 常勤換算2.5以上が確実に確保されている
- 管理者・サ責の資格要件を満たしている
- 雇用契約書で勤務時間が明記されている
- 退職リスクを考慮し、0.5以上の余裕がある
- 勤務体制・勤務形態一覧表が正確に作成されている
採用と研修計画
採用難のリスクに備えるため、開業2ヶ月前から募集を開始することが理想的です。また、研修については「接遇・緊急対応・感染対策」などを事前に実施しておくことで、指定審査においても有利に働くことがあります。
ステップ5. 設備・備品の準備
業務に必要な最低限の設備を整えます。例としては以下のようなものがあります。
- パソコン、業務用電話、FAX、プリンター
- 書類保管用の鍵付きキャビネット
- 介護ソフト(請求・記録ソフト)などの業務支援システム
介護ソフトをはじめとする、訪問介護で実践できるICTツールについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ステップ6.介護保険事業者の指定申請手続き
介護保険事業者として介護保険法に基づく介護報酬を得ることを行政から認められるためには、基準に基づく指定*を自治体から受ける必要があります。
*参考:厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
この指定申請手続きは令和4年からオンラインで行うこともできる*ようになり、自治体によっては電子申請を原則としている場合もあるので、申請方法については必ず各自治体の情報を確認するようにしましょう。
*参考:厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」
申請から指定までの手続きとスケジュール
例として東京都においては以下のようなスケジュールが明示されています。
- 4ヶ月前:事前申請
- 3ヶ月前:指定前研修受講
- 2ヶ月前:申請受付
- 毎月1日:指定
参考:東京都「介護保険事業者指定のガイドブック」
申請から指定まで1〜2ヶ月半程度まで要すことになりますが、上述のように申請前に事前申請や研修受講が必要になる場合もあります。手続きに漏れがあると指定が数ヶ月レベルで遅れてしまうこともあるため、指定申請を検討する段階で各自治体に必ず手続きを確認することと、スケジュールに余裕を持つことが大事だと言えます。
指定申請に必要な書類
具体的な必要書類については、申請する自治体の情報を確認する必要がありますが、参考までに東京都における必要書類は以下の通りとなっています。
- 指定(許可)申請書
- 訪問介護事業所の指定等に係る記載事項
- 申請者の登記事項証明書又は条例等
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 資格証の写し
- 事業所の平面図
- 外観及び内部の様子がわかる写真
- 運営規程(料金表含む)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 誓約書及び誓約書別紙
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 体制等状況一覧表
- 加算様式・参考様式
- 処遇改善等計画書
- 老人居宅生活支援事業開始届
自治体への事前相談を忘れずに
申請前には必ず都道府県や市町村の介護保険課に事前相談を行いましょう。
地域により「独自の書類様式」や「運用上の注意点」があるため、早めの相談がトラブル回避の鍵です。
ステップ7.開業前の最終準備と確認
開業前の最終準備として、以下のような項目を確認しましょう。
- 開業日を明確に定め、関係機関へ通知
- 緊急連絡体制、BCP(業務継続計画)の整備
- 事前研修、サービス提供マニュアルの完成
BCP(業務継続計画)の基本や策定方法については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
ステップ8.事業開始〜開業後の運営準備
事業開始後は、まず利用者の獲得に向けて紹介や連携、営業活動を積極的に行います。
利用者が獲得できると、訪問介護計画書の作成なども必要になります。
初回サービス提供時には適切な記録を残し、運営状況を関係機関に報告することが重要です。また、加算算定や訪問実績の管理体制をしっかりと整備し、継続的な事業運営の基盤を固めていきましょう。
訪問介護の開業に必要な資金と具体的な調達方法
訪問介護事業を開業するには、ある程度まとまった資金が必要です。ここでは、どのような費目があり、どのように資金を集めるべきかを解説します。
※訪問介護の開業に必要な資金や具体的な調達方法については、以下の記事でより詳しく解説しています。
訪問介護の開業資金の内訳
開業時にかかる費用は、事業規模や立地条件によりますが、おおよそ800万〜1,000万円程度を見込んでおくと安心です。以下は主な内訳です。
| 項目 | 内容 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 物件取得費 | 敷金・礼金・仲介手数料 | 50〜100万円 |
| 内装・設備費 | 備品購入、通信環境整備など | 50〜100万円 |
| 人件費 | 採用・研修・初月給与の準備金 | 150〜300万円 |
| 登記・手続費用 | 定款、登記、申請書類など | 10〜30万円 |
| 運転資金 | 3〜6ヶ月分の家賃・給与・管理費など | 300〜500万円 |
※事業規模や立地条件により差があります。
開業資金の調達方法
開業資金を準備する方法には、以下のような手段があります。
自己資金
自己資金は融資審査の際にも重要視されるため、全体の30〜50%程度を目安に準備できると理想的です。
融資(日本政策金融公庫など)
創業融資として人気が高いのが「日本政策金融公庫」の制度融資で、無担保・無保証で最大7,200万円*程度まで利用可能です。また、地方自治体の制度融資と併用することもできます。
*参考:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
助成金・補助金
「キャリアアップ助成金」「特定求職者雇用開発助成金」など雇用関連の助成金が中心となりますが、初期投資には使えないケースが多く、開業後の申請・受給が前提となります。申請手続きや報告義務が多いため、社労士への相談も視野に入れることをおすすめします。
なお令和7年度においては、訪問介護サービスの人材確保と経営安定化を目的とした「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金」が新たに創設されました。この補助金の主体は各自治体となりますが、2025年8月時点で実施している自治体も多くあります。
以下の記事では、補助金の詳細や自治体ごとの最新の実施状況を掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
開業のための融資を成功させるためのポイント
融資審査で重視されるポイントは以下の通りです。
- 実現可能性の高い事業計画書(収支予測、提供サービス、競合との差別化)
- 創業者の経歴や介護業界経験の有無
- 自己資金の割合(多いほど信頼性が上がる)
- 返済能力の根拠(月次の利益計画と返済計画)
特に訪問介護は「介護報酬での収入=入金まで2ヶ月遅れ」となるため、運転資金の確保と見せ方が重要です。金融機関から信頼される“数字の裏付け”が、資金調達成功の鍵を握ります。
訪問介護の開業・経営で失敗しないための注意点と成功の秘訣
訪問介護事業は、制度や社会的ニーズに支えられた有望な分野である一方で、倒産や廃業のリスクも高い業種です。ここでは、よくある失敗パターンと、長く安定して経営を続けるための成功のポイントを紹介します。
訪問介護の開業・経営が失敗する主な原因
過去の倒産事例から学ぶ、訪問介護事業における経営失敗の主な要因として、以下のようなケースが考えられます。
資金ショート
介護報酬の入金が2ヶ月遅れであるため、初期の運転資金が尽きやすく、赤字続きで資金繰りが回らず、融資も受けられない状態に陥ってしまうケースがあります。
人材不足・定着率の低さ
採用難に加え、離職率の高さが慢性的な人員不足を招き、一人の欠員で稼働できなくなる「薄氷のオペレーション」に陥ってしまうことがあります。
利用者獲得の失敗
地域との接点が少なく、紹介ルートが構築できないことや、競合との差別化ができず、価格競争に巻き込まれることで利用者獲得に失敗するケースが見られます。
ずさんな運営管理・コンプライアンス違反
記録不備、苦情対応の不備、運営基準違反などにより、介護保険事業者の「指定取消し」や「加算の返還処分」を受けるリスクが発生することがあります。
競合との差別化不足
他事業所と同質化し、選ばれる理由がないことや、ブランディング・サービス品質への投資不足により、競合に埋もれてしまうケースがあります。
成功する訪問介護事業所にするためのポイント
一方で、経営難に陥らないためにはどういったことがポイントになるのかを、以下に整理しました。
質の高いサービス提供体制の構築
質の高いサービス提供体制を構築するためには、まず経験豊富なサービス提供責任者を配置することが重要です。サービス提供責任者は利用者のケアプラン作成や訪問介護員の指導・管理を担う中核的な役割を果たすため、豊富な現場経験と専門知識を持つ人材の確保が事業成功の鍵となります。
また、職員のスキル向上を図るため、eラーニングを活用した研修を積極的に実施することも効果的です。時間や場所に制約されることなく、継続的な学習機会を提供することで、職員の専門性向上と定着率の改善につながります。
介護のコミミでは無料で始めることができるおすすめeラーニングサービスも紹介しています。興味がある方は以下の記事を参考にしましょう。
人材育成と働きがいのある環境づくり
人材育成と働きがいのある環境づくりにおいては、介護職員等処遇改善加算を活用した待遇改善を図ることが重要です。また、キャリアパスの見える化と社内研修制度の整備により、職員が将来への展望を持ちながら成長できる環境を構築することで、定着率の向上と組織全体のサービス品質向上につなげることができます。
介護職員等処遇改善加算(通称、処遇改善加算)については以下の記事でもわかりやすく解説しています。
地域包括ケアシステムの中での連携強化
地域包括ケアシステムの中で成功するためには、地域のケアマネジャーや包括支援センターとの関係構築が不可欠です。また、医療機関や他の介護事業所との連携を深めることで、利用者紹介ルートを確保し、安定した事業運営の基盤を築くことができます。
効果的な集客・営業戦略
効果的な集客を実現するためには、自社パンフレットの作成や地域広報、SNSの活用など、多角的なアプローチが重要です。さらに、ケアマネジャーへの定期的な訪問を通じて関係づくりを行い、事業所の特徴やサービス内容について積極的に情報提供することで、紹介につながる信頼関係を構築できます。
適切な収支管理とコスト削減
健全な経営を維持するためには、利用実績をリアルタイムで管理し、収支状況を常に把握することが重要です。また、訪問件数と人件費のバランスを適切に保つ体制を整備することで、効率的な運営とコスト削減を両立させることができます。
法改正への迅速な対応
介護業界は制度変更が頻繁に行われるため、介護報酬改定や制度変更に対して常にアンテナを立てておくことが必要です。行政説明会や地域研修などに積極的に参加し、最新の情報を収集することで、法改正に迅速かつ適切に対応できる体制を整えることができます。
訪問介護の開業・経営に関するよくある質問(FAQ)
Q: 個人でも開業できますか?
A: 原則として、訪問介護事業所は法人格が必要です。個人事業主では介護保険事業者の指定を受けることができません。
Q: 必要な資格はありますか?
A: 開業者自身に特別な資格は不要ですが、配置義務のある「サービス提供責任者」や「訪問介護員」には、所定の資格(初任者研修、実務者研修など)が必要です。
Q: 指定申請にはどれくらい時間がかかりますか?
A: 書類提出から指定通知までは2〜2.5ヶ月程度が一般的です。ただし、都道府県・市町村によってスケジュールが異なるため、事前相談が必須です。
Q: 運転資金はどれくらい必要ですか?
A: 最低でも3ヶ月分の運転資金(家賃、人件費など)を確保しておくと安心です。訪問実績が安定するまでは収入が不安定なため、6ヶ月分を目安に備える事業者も多いです。
Q: 利用者はどうやって獲得しますか?
A: 地域包括支援センター、ケアマネジャー、医療機関との連携が鍵となります。信頼関係を築き、紹介を受けられる体制を整えることが集客の要です。
Q: 訪問介護の立ち上げにはどれくらいの期間が必要ですか?
A: 4〜6ヶ月の計画的な準備が一般的です。法人設立、人員確保、物件選定、指定申請などを順次進める必要があります。東京都では事前申請が開業4ヶ月前に必要なため、十分な準備期間の確保が重要です。
Q: 常勤換算2.5人はどう計算しますか?
A: 各職員の週勤務時間の合計を40時間で割って算出します。
例:常勤職員1名(40時間)+ 非常勤職員2名(25時間+20時間)の場合、1.0 + (45÷40) = 2.125となり、2.5人の基準を満たしません。
まとめ:訪問介護事業の成功に向けて、最初の一歩を踏み出そう
訪問介護事業の開業には、法人設立・人材確保・資金調達・指定申請など、多くの準備と知識が必要です。加えて、倒産や失敗のリスクを避けるためには、事前の情報収集と現実的な経営戦略が欠かせません。
一方で、地域に根ざした信頼ある事業所を築くことができれば、社会貢献性も高く、やりがいのあるビジネスとなります。
この記事を参考に、あなたの開業への一歩が確実なものになるよう、丁寧に準備を進めていきましょう。もし不安がある場合は、専門家や自治体の相談窓口の活用も視野に入れてください。
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する