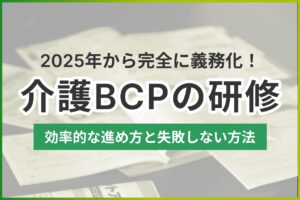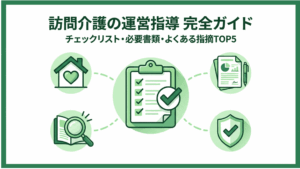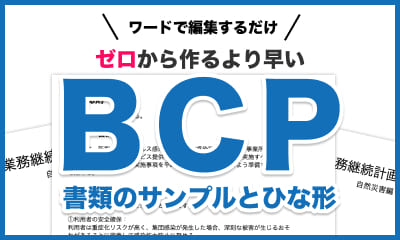【2025年版】介護のBCPとは?義務化の背景と減算の回避方法をわかりやすく解説
介護報酬の加算・減算介護施設の経営・運営改善

令和6年(2024年)4月に介護事業におけるBCP(業務継続計画)の策定が義務化となったことを受け、BCP策定に取り組む介護事業所が増えようとしています。
そこで、この記事では今さら聞けないBCP策定の重要性を解説し、忙しい中でもBCP策定から研修・訓練まで少ない負担で実行できるよう、みなさんをサポートできればと思います。
※このBCP策定の義務化にあたり令和6年に新設された「業務継続計画未策定減算」という減算の中で、一部認められていた経過措置が2025年3月にはいずれも終了したため、2025年4月以降は全ての事業所のBCP策定が完全義務化されたことに注意しましょう
この記事の内容は、YouTubeの動画でもわかりやすく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
BCPの策定以外にも義務化されている「BCPの研修」について解説した記事も公開しています。「BCPは策定できたが研修がまだできていない」という方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。
BCPとは何か
BCPとは事業継続計画のこと
BCP(ビーシーピー)とは、いわゆる「事業継続計画」のことを指し、自然災害や感染症などの緊急事態が発生した際に事業を継続させるための対策や行動指針を定めたマニュアルです。 介護事業所においては、利用者の安全と健康を確保し、サービスを継続的に提供することが求められます。
介護事業所にBCPが必要な3つの理由
介護サービスは、高齢者や要介護者の日常生活支援や生命維持に関わる役割に責任を負っている以上、災害時や感染症の流行時にもサービスの継続が求められます。BCP策定が求められる具体的な理由としては以下の3つを挙げることができます。
- 健康管理や生活・生命維持などの利用者に対する責任を果たすことができる
- サービス中断による事業の損害を最小化できる
- 介護保険法で定められている法的な義務を満たすことができる
ここからは、主に3つ目の「介護保険法で定められている法的な義務」について解説します。
介護事業所におけるBCP策定の法的な必要性
2024年4月にBCPの策定が義務化された
2024年4月より、すべての介護事業所でBCPの策定が義務化されました。 これは、自然災害や感染症が発生した場合でも、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であるとの認識からです。過去の災害や感染症の流行により、多くの介護事業所が運営上の困難に直面したことが背景にあります。
BCP未策定の場合は業務継続計画未策定減算が適用される
BCPを策定していない介護事業所は、令和6年の介護報酬改定で新設された「業務継続計画未策定減算」として減算の対象となるリスクがあります。具体的な減算率としては、施設や居住系サービスでは3%、その他のサービスでは1%の減算が適用される可能性があります。 また、運営基準違反として指導対象となり、最悪の場合、指定取消などの行政処分を受ける恐れもあります。
業務継続計画回策定減算を回避するため、今すぐBCP策定を始めませんか?
介護のコミミでは、BCPの策定に必要な書類作成の業務を効率化できるよう、訪問系サービス向けのBCP書類サンプルとひな形を無料でプレゼントしています。
ぜひ、以下から気軽にダウンロードしてご活用ください。
参考までに、厚生労働省では業務継続計画未策定減算の算定要件を以下のように定めています。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時 の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
『令和6年度介護報酬改定における改定事項について』(厚生労働省)より引用
また、業務継続計画未策定減算は一部以下のような猶予が設けられていましたが、いずれの経過措置も令和7年(2025年)3月31日をもって終了するため注意が必要です。
- 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない
- 訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。
『令和6年度介護報酬改定における改定事項について』(厚生労働省)より引用
BCPには何を記載したら良い?
いざ、これから新しくBCPを策定しようと思っても、どんな内容を事業継続計画として記載すべきかイメージしにくいかもしれないので、簡単に解説します。
介護事業所のBCPに記載すべきことはたった2つ
介護事業所のBCPに記載すべき項目は、実は「自然災害への対策」と「感染症への対策」の2つで十分なのです。
「自然災害への対策」と「感染症への対策」の具体的な書き方と記入例を記載した、訪問系サービス向けのBCP書類サンプルを無料でダウンロードいただけます。
無料でダウンロードする自然災害への対策
自然災害発生時は、職員と利用者の安否確認を行うことが最優先となり、状況によっては、事業・サービスを一時的に停止せざるを得ない場合もあるかもしれません。その際に、業務の優先順位を見極めつつ、安全確保と復旧作業を並行して進めることが重要になります。
感染症への対策
感染症が発生した際は、利用者や他の職員への影響を最小限にとどめるため、業務の縮小や一時閉鎖などを検討し、正しい情報の判断と迅速な行動ができるよう、BCPに計画を落とし込んでおくことが重要になります。
これらを踏まえて、以下では事業種別ごとに具体的に押さえておくべきポイントも見ていきましょう。
施設系事業所のBCPに記載すべきこと
自然災害への対策
- リスク評価と現状把握(施設所在地のリスク評価、建物の耐震性・非常用設備の確認)
- 避難計画の策定(高齢者に合わせた避難経路・集合場所の設定、地域防災計画との連携)
- 定期訓練の実施(避難訓練・シミュレーションの実施による迅速対応の習熟)
感染症への対策
- 感染防止の基本対策(定期的な消毒、換気、マスクや手指消毒剤の常備)
- 隔離・対応体制の整備(疑わしい場合の隔離ルームの確保、保健所や医療機関との連携)
訪問系事業所のBCPに記載すべきポイント
自然災害への対策
- 地域リスクと移動手段の確保(訪問エリアごとのリスク評価、代替ルート・交通手段の整備)
- 連絡・調整体制の強化(スタッフと利用者間の緊急連絡手段の確保、対応マニュアルの整備)
感染症への対策
- 個人防護と健康管理の徹底(マスク、手袋、フェイスシールド等の使用、訪問前の健康チェック)
- リスク低減のための事前調整(訪問先状況の確認、オンライン相談やリモート支援の検討)
通所系事業所のBCPに記載すべきポイント
自然災害への対策
- 施設内安全対策の徹底(安全点検、避難経路・非常口の明示、定期的な避難訓練)
- 送迎体制と地域連携(送迎の再確認、緊急時の代替送迎手段の確保、地域防災組織との連携)
感染症への対策
- 利用者・スタッフの健康管理(体温測定、健康チェックの徹底、早期発見と迅速対応)
- 施設運営の工夫(座席配置や利用人数の調整、定期的な消毒・換気)
BCP策定に必要な5つのステップ
BCP策定の手順としては大まかに以下のようなステップを踏むことになります。
- 情報共有と即時対応のための体制構築
- リスクアセスメントの実施
- 優先業務の特定
- 対策の策定と実施
- 研修・訓練と見直し
各ステップの大事なポイントを、以下にて1つずつ解説していきます。
1.情報共有と即時対応のための体制構築
自然災害や感染症などの非常事態に迅速に対応するにには、情報の集約・共有が円滑に行われる体制を構築しておくことが重要になります。そのため、あらかじめ最終的な意思決定者を決めておくことや、各業務の担当者を決めておくこと、関係者の連絡先、連絡フローの整理が必要です。
2.リスクアセスメントの実施
体制が構築できたら、事業所が直面し得るリスクを特定、評価しながら自然災害や感染症の発生リスクを洗い出し、その影響度や発生頻度を評価します。
3.優先業務の特定
次に、緊急時に優先すべき業務やサービスを特定します。これにより、緊急時において限られたリソースで重要な業務を継続するための指針を明確にします。
4.対策の策定と実施
特定したリスクと優先業務に基づき、具体的な対策を立案し、実施します。例えば、非常用物資の備蓄、代替施設の確保、感染症対策の強化などが挙げられます。
5.研修・訓練と見直し
BCPは策定して終わりではなく、策定したBCPが有効に機能するよう、定期的な研修や訓練を実施したり、計画の見直しを行う必要があります。これにより、職員の対応力を高め、計画の実効性を確保します。
BCPの研修・訓練を負担なく実施する方法
先述の5つのステップで紹介した通り、どれだけ入念なBCPを作成したとしても、事前に立てた計画が意図通りの機能と効果を果たすためには、日頃から職員がBCPの内容を理解し、いざという時に適切な対応ができるようにするための定期的な研修や訓練が必要です。
とはいえ、こういった研修や訓練を準備するにも、日常的な業務の忙しさを考えると大きな負担になるかもしれないので、ここでは少ない負担で実施できる研修や訓練の方法を紹介します。
※介護BCPにおける研修実施の重要性や実施方法についての詳細は以下の記事でも解説しているので、「BCPはすでに策定できたが研修をまだ実施できていない」という方はぜひ参考にしてください。
研修サービスを利用する
講義や実技などを交えて、現場職員に向けたBCP研修を行うサービスもたくさんあります。
特に、eラーニングを活用した研修であれば、低コストで始められるものもあるほか、研修を準備する職員も研修を受ける職員の時間の負担も少なく済むのでおすすめです。
介護のコミミでは無料で始められるeラーニングを紹介している記事もあるので、ぜひ参考にしてください。
厚生労働省の研修を利用する
厚生労働省が公開している「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」では、動画形式でBCP作成方法から訓練について無料で解説しています。
また、業務継続ガイドラインの資料やBCPのひな形も配布しているので、これからBCP策定を始める方はぜひ活用したいところです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
BCPは策定して終わりではなく、事業所が存続する限り継続していくべき活動なので、この記事を通して皆さんの事業所運営の役に立てれば幸いです。
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する