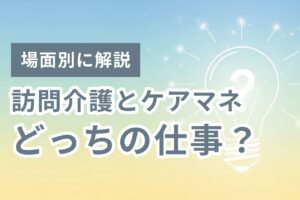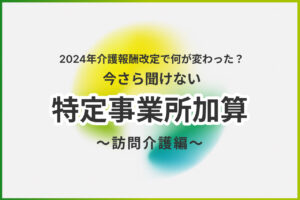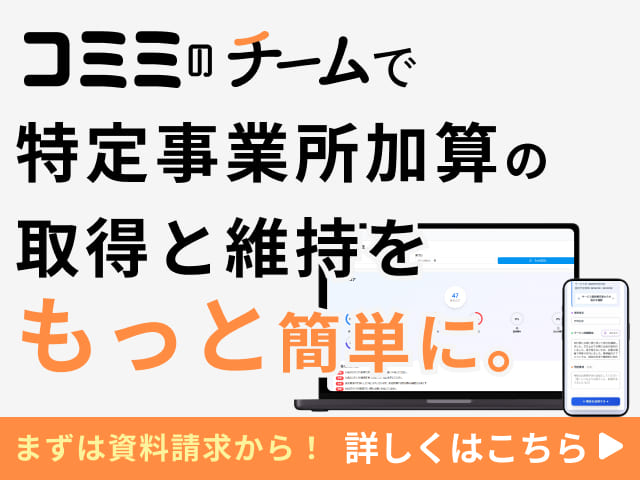【もう迷わない】訪問介護計画書の記入例と作成の流れ | 書き方や運営指導対策も解説
介護施設の経営・運営改善
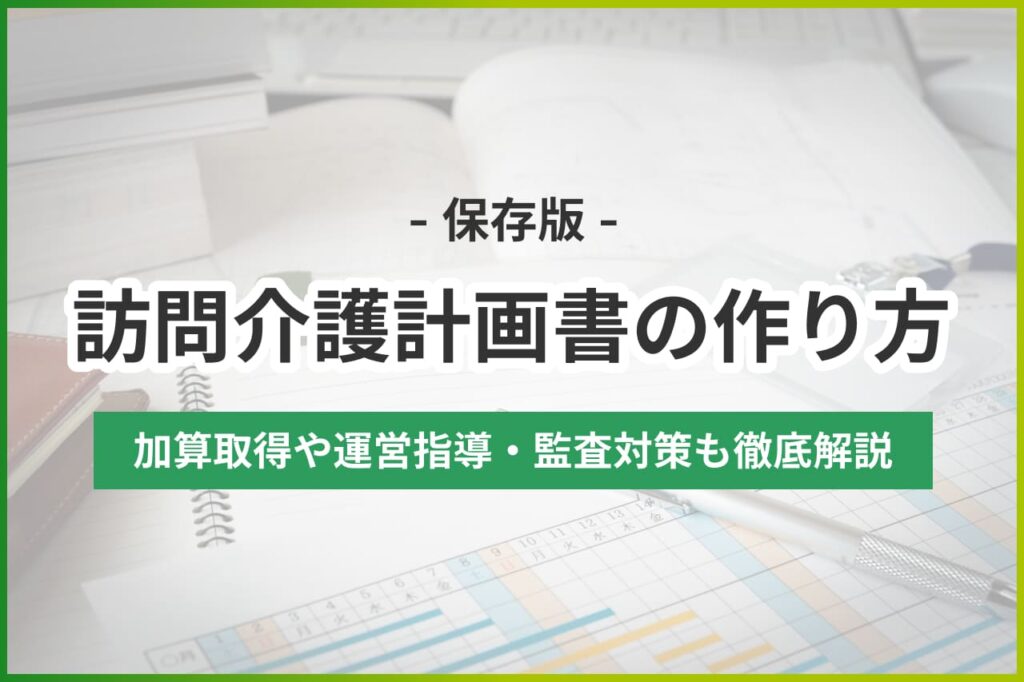
新しくサービス提供責任者になった方や、開業されたばかりの方は、「訪問介護計画書」の作成や運用で迷うことや疑問に感じることも多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では訪問介護計画書を作成する目的から具体的な書き方、運営指導対策や加算取得に活かす方法まで、現場で本当に役立つポイントを網羅的に解説します。
特に、訪問介護計画書の記載例を複数パターン掲載しているので、この記事を最後まで読むことで訪問介護計画書の作成に迷うことを減らすことができるでしょう。
1.訪問介護計画書とは?
訪問介護計画書は、訪問介護サービスを提供する際に必ず作成が求められる重要な書類です。
訪問介護計画書を作成する目的と役割
訪問介護計画書を作成する目的は、利用者一人ひとりに適したサービスを計画的に提供し、その人らしい生活を支援することです。具体的には以下のような役割を果たします。
1. 個別ケアの実現
利用者の身体状況、生活環境、本人・家族の意向を総合的にアセスメントし、その人に最適なサービス内容を明確化します。画一的なサービスではなく、利用者の尊厳を保持しながら自立支援を図ることが可能になります。
2. サービスの質の向上と統一
計画書により援助目標や具体的な援助内容が明文化されることで、複数のヘルパーが関わる場合でも一貫したサービスを提供できます。また、定期的な評価・見直しを通じてサービスの質を継続的に改善していくことができます。
3. 法的要件の遵守
指定基準(厚生省令)により訪問介護計画書の作成は義務付けられており、運営指導や監査では必ず確認される重要書類です。適切な作成・運用により、事業所の法令遵守体制を示すことができます。
そのため、訪問介護計画書の作成・管理は運営指導(実地指導)の監査対象にもなります。
4. 利用者・家族との合意形成
計画書の説明・同意を通じて、利用者・家族とサービス内容について共通理解を図ります。これにより信頼関係を構築し、トラブルの予防にもつながります。
5. 多職種連携の促進
ケアマネジャーや他のサービス事業者との情報共有ツールとしても機能し、チームケアの質を高める役割を担います。
訪問介護計画書の作成はサ責の仕事
訪問介護計画書の作成は、サービス提供責任者の仕事の1つです。サービス提供責任者は、ケアマネジャーが作成したケアプランを基に、具体的な訪問介護サービスの内容を決定し、ヘルパーに指示を出す役割を担います。
※サービス提供責任者の業務内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
訪問介護計画書はケアプランに基づいて作成される
訪問介護計画書は、ケアマネジャーが作成したケアプラン(居宅サービス計画書)に基づいて作成されることが法的に定められています*。ケアプランと訪問介護計画書の内容に齟齬があると、利用者のニーズに適したサービスが提供できず、サービスの質の低下や利用者・家族の不満につながる可能性があります。そのため、ケアプランの内容を正確に反映し、整合性を保った計画書を作成することが重要です。
*参考:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生労働省
ケアプランと訪問介護計画書の違いは?
ケアプランと訪問介護計画書の違いは、ケアプランは提供すべきサービスの全体的な方向性を示す役割を担っているのに対し、訪問介護計画書では、ケアプランを実現するためのサービス内容を具体化する役割が求められます。
ケアプランにないサービスを訪問介護計画書に記載し、実際に提供しても介護報酬を請求することはできないので、注意しましょう。
2.訪問介護計画書を作成するタイミングと流れ
訪問介護計画書は、訪問介護のサービス提供を開始する前に必ず作成し、利用者・家族への説明と同意を得る必要があります。以下、作成から運用までの具体的な流れを解説します。
訪問介護計画書を作成するタイミング
訪問介護計画書の作成タイミングは以下の通りです:
| 新規利用開始時 | 初回サービス提供前までに作成 |
|---|---|
| ケアプラン変更時 | 居宅サービス計画書の変更に伴い速やかに見直し |
| 定期見直し時 | 最低6ヶ月に1回の定期的な見直し |
| 利用者の状態変化時 | 心身状況や生活環境の大きな変化があった場合 |
訪問介護計画書の作成から運用までの流れ
ステップ1:アセスメントの実施
ケアマネジャーから提供されたケアプランを基に、利用者の心身状況、生活環境、本人・家族の意向を詳細に把握します。必要に応じて利用者宅を訪問し、直接面談を行います。
ステップ2:計画書の作成
アセスメント結果を踏まえ、援助目標と具体的なサービス内容を設定します。ケアプランとの整合性を確認し、実現可能で具体的な計画を立案します。
ステップ3:利用者・家族への説明と同意
作成した計画書の内容を利用者・家族に分かりやすく説明し、書面による同意を得ます。疑問や要望があれば調整を行います。
ステップ4:ヘルパーへの指示・情報共有
サービスを担当するヘルパーに対し、計画書の内容を説明し、統一したサービス提供ができるよう指示を行います。
ステップ5:サービス提供と記録
計画書に基づいてサービスを提供し、実施状況や利用者の反応を記録します。計画通りに実施できない場合は理由を明確にします。
ステップ6:モニタリングと評価
定期的にサービス提供状況を評価し、目標達成度や利用者の満足度を確認します。必要に応じて計画の見直しを行います。
この一連の流れを適切に実施することで、利用者のニーズに応じた質の高いサービス提供と、運営指導での指摘回避が可能になります。
3.訪問介護計画書の記載項目と記入例
ここからは、訪問介護計画書の具体的な記載項目と、記入例を紹介します。
訪問介護計画書の最新様式と記載項目
訪問介護計画書における、最新の記載項目は主に以下の通りです。(令和3年度の介護報酬改定に伴い、介護サービス計画書の様式や記載項目も一部見直されています)
| 計画作成者(サービス提供責任者)氏名・作成年月日 | 計画書を作成したサービス提供責任者の氏名と作成日を記載します。責任の所在を明確にし、いつ作成されたかを示す重要な項目です。 |
|---|---|
| 利用者情報(氏名・住所・生年月日・要介護度等) | 利用者の基本情報を記載します。氏名、住所、生年月日、要介護度、介護保険証番号などが含まれ、利用者を特定するための必須項目です。 |
| 日常生活全般の状況(アセスメント結果) | 利用者の心身の状況、生活環境、ADL(日常生活動作)の状況などを具体的に記載します。サービス提供の根拠となる重要な情報です。 |
| 援助目標(長期・短期) | 利用者の自立支援に向けた具体的な目標を設定します。長期目標は概ね6ヶ月程度、短期目標は1〜3ヶ月程度の期間で達成可能な目標を記載します。 |
| 本人・家族の意向・希望 | 利用者本人や家族が希望するサービス内容や生活に対する意向を記載します。利用者の尊厳を保持し、意思を尊重したサービス提供の基盤となります。 |
| 具体的援助内容(サービス区分・内容・所要時間・留意事項) | 身体介護・生活援助の区分、具体的なサービス内容、所要時間、提供時の注意点などを詳細に記載します。ヘルパーが統一したサービスを提供するための指針となります。 |
| 頻度・期間・週間予定表 | サービス提供の頻度(週何回)、提供期間、曜日・時間帯などのスケジュールを記載します。計画的なサービス提供のための重要な情報です。 |
| サービス提供に関する評価(目標達成度・満足度・見直しの必要性) | 設定した目標の達成状況、利用者の満足度、計画の見直しの必要性などを定期的に評価し記載します。サービスの質の向上と継続的改善のために必要です。 |
| 説明日・説明者、事業所情報、同意の確認 | 利用者・家族への説明を行った日付と説明者、事業所の名称・連絡先、利用者・家族からの同意確認を記載します。法的要件を満たすための必須項目です。 |
※主たる介護者・連絡先や居宅介護支援事業所・担当ケアマネジャーは、アセスメントやケアプランとの連携に関連する情報として記載される場合があります。
最新の様式は自治体や事業所によって微細な違いがあるため、必ず最新の行政通知や自治体の指導を確認しましょう。
訪問介護計画書の書き方・記入例
訪問介護計画書の記載は、目標達成に向けた取り組みの内容やサービス内容を具体的に、誰もが理解できるように記載することが重要です。利用者ごとに個別性を持たせることが求められます。
以下は具体的な訪問介護計画書の記入例です。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 日常生活全般の状況 | 記入例1:一人暮らし。足腰の痛みがあり、歩行が不安定なため、ひとりで通院することができない。部屋の掃除や整理整頓ができていない。 記入例2:夫婦二人暮らし。認知症の症状があり、服薬管理や金銭管理が困難。入浴時の転倒リスクがあるため見守りが必要。 記入例3:息子夫婦と同居。脳梗塞後遺症により右半身麻痺があり、車椅子を使用。食事摂取時にむせ込みがあり、誤嚥のリスクがある。 |
| 援助目標 | 記入例1:安全に定期的に通院できることで病状の維持・安定を図る。居室内が整理され、衛生的な環境で生活することができる。 記入例2:適切な服薬管理により健康状態を維持し、安全に入浴できる環境を整える。認知症の進行を遅らせ、在宅生活を継続する。 記入例3:残存機能を活用し、できる限り自立した日常生活を送る。誤嚥を予防し、安全に食事摂取ができるようになる。 |
| 本人・家族の希望 | 記入例1:子供の手を借りずに生活していきたい。きれいな部屋で過ごしたい。 記入例2:夫婦で穏やかに過ごしたい。できるだけ自宅で生活を続けたい。家族の負担を軽減したい。 記入例3:家族と一緒に食事を楽しみたい。リハビリを頑張って少しでも動けるようになりたい。 |
| 具体的援助内容 | 記入例1:生活援助(掃除)を週2回、1回45分以上実施。移動介助を伴う通院支援(片道)を月2回実施。 記入例2:身体介護(入浴介助)を週2回、1回60分実施。生活援助(服薬確認・買い物)を週3回、1回45分実施。 記入例3:身体介護(食事介助・移乗介助)を毎日、1回90分実施。生活援助(調理・洗濯)を週3回、1回60分実施。 |
| 留意事項 | 記入例1:歩行車の使用状況を確認し、転倒リスクに注意する。 記入例2:認知症の症状の変化を観察し、服薬の飲み忘れがないか確認する。入浴時は滑り止めマットの設置を確認する。 記入例3:食事摂取時は姿勢に注意し、とろみ剤の使用を徹底する。移乗時は車椅子のブレーキ確認を必ず行う。 |
上記以外にも、利用者の生活背景や希望を具体的に文章で補足することで、よりわかりやすく、利用者の個別性を反映した計画書となります。
4.訪問介護計画書でよくある運営指導(実地指導)や監査の指摘ポイントと対策
訪問介護計画書の記載や運用に関して、運営指導(実地指導)や監査で確認される主なポイントとしては、全項目の記載漏れや個別性の不足、モニタリング・見直し記録の未実施などが挙げられます。
- 全項目を漏れなく記載する
- 利用者ごとの個別性を必ず盛り込む
- モニタリング・見直しの記録を定期的に残す
電子化やICT活用は、業務効率化等の観点から推奨されており、記録の電磁的記録による保存も認められています。導入時には、個人情報保護や安全管理に関するガイドライン遵守など、求められる基準を確認しましょう。
5.訪問介護計画書の作成で加算を逃さないためのポイント
加算取得のためには、計画書の記載内容が要件を満たしていることが必須です。
以下に訪問介護において、体制整備が重要となる主な加算とポイントをまとめました。(各加算の加算名をクリックすると、その加算の加算率や算定要件を確認することができます)
| 加算名 | 概要・主な要件 |
|---|---|
| 特定事業所加算 | 算定要件であるサービス提供責任者の配置や研修実施、記録体制等を満たすこと |
| 生活機能向上連携加算 | 算定要件である医師やリハビリ専門職等との連携体制を構築し、連携して作成した計画に基づいたサービスを提供すること(サービス内容を計画書に具体的に示すことが重要です) |
| 初回加算 | 新規利用者の初回訪問時等に、サービス提供責任者が対応すること |
| 介護職員等処遇改善加算 | 算定要件である職員研修の実施やキャリアパス要件等を満たすこと |
上記のうち、特定事業所加算については、加算率が最大20%となるため、訪問介護の売上向上においては最も重要な加算として、押さえておくと良いでしょう。
その他の訪問介護の加算情報については、以下の記事でも解説しています。ぜひ、併せてご確認ください。
6.訪問介護計画書のモニタリング・見直し・記録の運用ルール
訪問介護計画書は作成して終わりではなく、定期的なモニタリングと見直しが求められます。
- モニタリングは、訪問介護計画の実施状況を把握するためにサービス提供責任者が行い、必要に応じて、また定期的に実施することが重要です。
- 利用者の状態変化や家族の要望があれば速やかに計画書を見直す
- 見直し内容を記録し、必要に応じてケアマネジャー等の関係者と情報共有することが重要です。
- 記録は電磁的記録による保存も認められています。
これにより、運営指導(実地指導)や監査時のエビデンスとしても有効です。
7.訪問介護計画書の電子化・介護ソフト活用の最新動向
訪問介護計画書や記録の電子化(電磁的記録による対応)は、令和3年度介護報酬改定で原則認められています。
電子化により、業務効率化などの効果が期待できます。主要な介護ソフトも、最新様式への対応が進んでいます。導入時には、適切な個人情報の取り扱いや安全管理に関するガイドライン遵守など、求められる基準を確認しましょう。
介護のコミミでは、訪問系サービス向けおすすめ介護ソフトの情報を比較できる介護ソフト比較表を無料でプレゼントしています。以下から、比較表をダウンロード・印刷できますので、ぜひ介護ソフト導入・切り替えの情報収集にお役立てください。
【無料】訪問系サービス向け人気ソフト比較表をダウンロードする
8.訪問介護計画書の適切な管理と運用
訪問介護計画書は適切な記録の保存を行う必要があります。
訪問介護計画書の管理のポイント
- 個人情報保護・セキュリティ対策を徹底
- サービスの評価や質改善に向けた取り組みが必要です。
- サービス提供責任者、ヘルパー、ケアマネジャー等関係者間での適切な情報共有・連携が重要です。
これにより、適切なサービス提供と質の確保につながります。
9.訪問介護計画書に関するよくある質問(FAQ)
Q. 計画書の様式は全国共通ですか?
標準様式は提示されていますが、事業所ごとに様式を定めても差し支えありません。自治体ごとに細部が異なる場合もあるため、必ず最新の通知を確認してください。Q. 電子化は義務ですか?
義務ではありません。利用者等の同意を得た上で、説明や同意、記録の保存等を電磁的記録で行うことが原則認められています。導入前に運用方法や留意事項を確認が必要です。Q. モニタリングや見直しの頻度は?
必要に応じて随時、及び定期的に見直しを行います。Q. 加算取得のために特に注意すべき点は?
加算の要件(人員配置、研修、会議、重度者対応など)を満たす体制整備が重要です。適切に記録を整備することも含まれます。10.まとめ
訪問介護計画書は、単なる書類作成ではなく、事業所の経営・サービス品質・加算取得・運営指導(実地指導)・監査対応すべてに直結する重要な業務です。
最新の法改正・ICT動向を押さえつつ、個別性・適切な評価と記録・効率化 を意識した運用を徹底しましょう。
「適切な計画作成・関係者との連携・サービスの評価と見直し・効率的な情報管理」を強化することで、質の高い事業所運営が実現できます。
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する