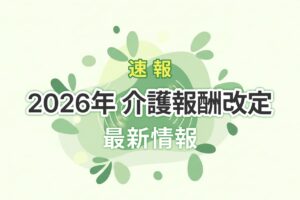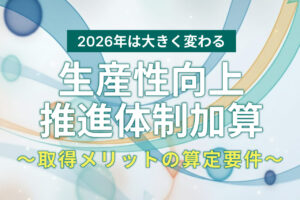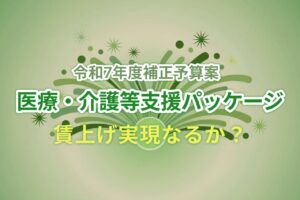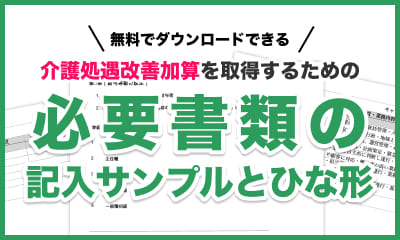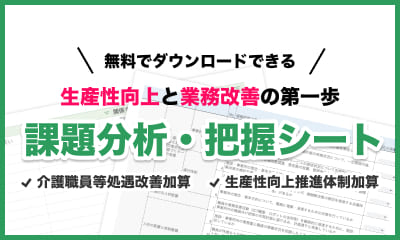介護職員等処遇改善加算とは?2026年最新の算定要件をわかりやすく解説!
介護報酬の加算・減算
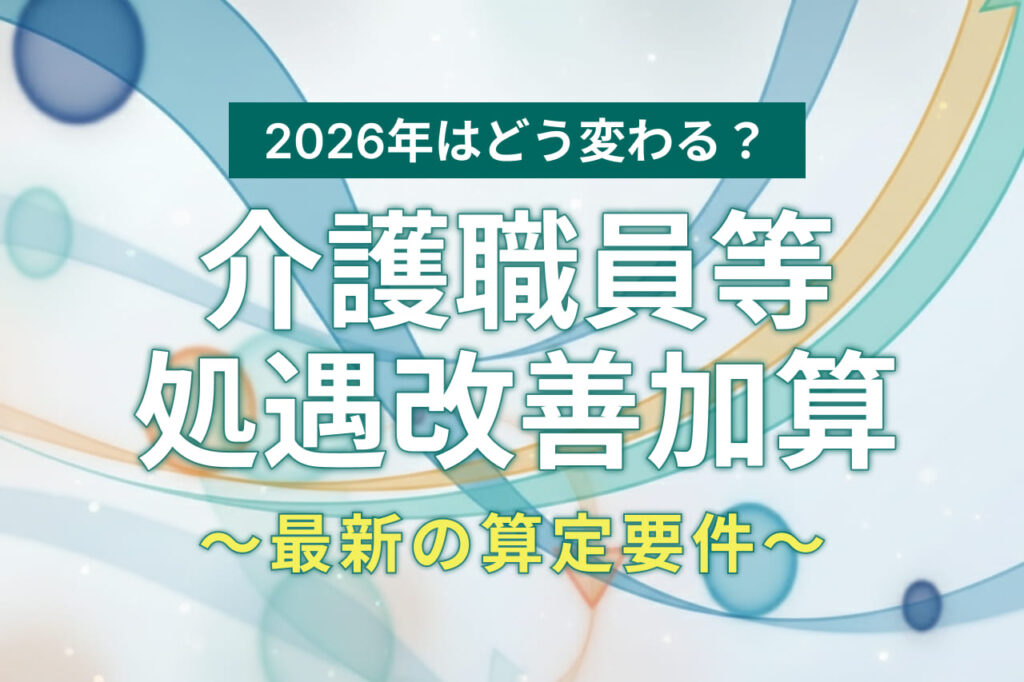
介護職員等処遇改善加算は令和6年度(2024年度)の介護報酬改定で新設された加算です。厚生労働省の公表資料(2026年1月時点)では、令和8年度介護報酬改定(期中改定)が行われ、2026年6月より改定版が施行されることが示されています。
令和8年度改定では、処遇改善加算について算定率の見直しに加え、生産性向上・協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分(加算Ⅰ・Ⅱの加算率上乗せ)の設定、対象の拡大(介護職員のみ→介護従事者へ)、ならびに訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等への新設が示されました。
※本記事は2026年1月19日時点で公開されている資料に基づき作成しています。最終的な告示・通知等で内容が確定し、差異が生じた場合は随時更新します。
出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(社保審・介護給付費分科会 資料1)
また、2026年は介護職員等処遇改善加算として新設された当初より設けられていた、一部算定要件における経過措置が3月いっぱいで終了する見込みです(経過措置の有無・期限は告示・通知等で必ず確認してください)。
そこでこの記事では、介護職員等処遇改善加算について2026年度(令和8年度)に押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、
- 処遇改善加算の区分ごとの加算率などの基本情報
- 処遇改善加算に関する経過措置や新要件などの2026年度(令和8年度)における最新情報
- 処遇改善加算の各算定要件の内容と満たす方法
などが分かるので、ぜひ最後までお読みください。
※令和8年度介護報酬改定についての最新情報は、以下の記事で随時更新しています。
ただでさえ複雑な処遇改善加算の算定要件を1つずつ満たすために、それぞれの書類をゼロから作成するのはとても大変ですよね。
そこで介護のコミミでは、算定要件を満たすために必要な書類を作成する負担を軽減するために、各算定要件ごとに合わせた書類のひな形・サンプルを無料でプレゼントしています。
ひな形・プレゼントを活用して、書類作成にかかる時間を削減しましょう!
無料プレゼント
ひな形・サンプルを入手する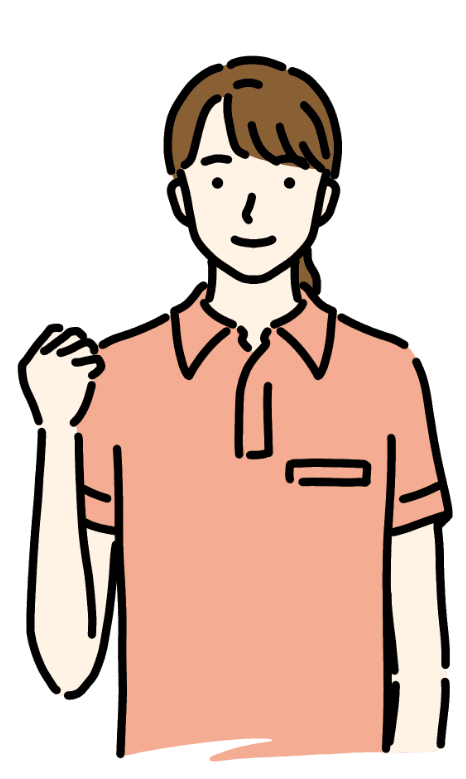
介護職員等処遇改善加算とは
介護職員等処遇改善加算は、2024年度の介護報酬改定で新設された加算です。
簡単にまとめると、以下の従来の3加算を一本化し、制度の簡素化と取得率の引上げを図ったものです。
- 介護職員処遇改善加算(以下、旧処遇改善加算)
- 介護職員等特定処遇改善加算(以下、旧特定加算)
- 及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、旧ベースアップ等加算)
一本化の具体的な目的は以下の3点です。
- 事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減するため
- 利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくするため
- 事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とするため
介護職員等処遇改善加算は2024年6月より開始され、同年6月以降も一定額以上の賃金改善を達成するよう、加算率の引き上げや配分方法の工夫が行われる予定です。これにより介護現場で働く方々の賃金が、2024年度は2.5%、2025年度は2.0%のベースアップへとつながるものと期待されています。
先述の通り、旧加算からの円滑な移行を目指すため、開始当初にいくつかの経過措置が設けられており、最新の情報を把握していないと、加算が無効となってしまうため、ここからは2026年に押さえておくべきポイントを解説します。

処遇改善加算の概要や取得方法をまとめたガイドブックを無料プレゼントしているよ!情報の整理や共有に活用してね!
無料ですぐにもらえる
処遇改善加算のガイドブックを入手する2026年に押さえておくべき3つのポイント
介護職員等処遇改善加算において、2026年に押さえておくべきポイントはズバリ、以下の3点です。
- 令和8年度介護報酬改定(2026年6月施行)による算定率の見直しと新たな加算区分(上乗せ区分)の設定
- 一部算定要件に認められていた経過措置が2026年3月末に終了する
- 訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等への加算新設(対象サービスの拡大)
それぞれ詳しく解説します。
1.令和8年度介護報酬改定による新要件の追加と加算率の上乗せ
令和8年度介護報酬改定(2026年6月施行)では、介護職員等処遇改善加算について、算定率(加算率)の見直しとあわせて、生産性向上・協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分が示されました。これにより、加算Ⅰ・Ⅱについて上乗せ後の区分(例:Ⅰイ/Ⅰロ、Ⅱイ/Ⅱロ)が設けられ、事業者の取組状況に応じて加算率が変わる整理となっています。

また、令和8年度の特例要件として、以下のア~ウのいずれかを満たすことが示されています。
- ア)訪問・通所サービス等:ケアプランデータ連携システムに加入し、実績の報告を行う
- イ)施設サービス等:生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを取得し、実績の報告を行う
- ウ)共通:社会福祉連携推進法人に所属していること
加えて、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大することが示されています。介護職員だけでなく、介護現場でサービス提供に従事する職員全体の賃上げに活用できるように整理された点が大きな変更点です。
出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(2026年1月時点の公表資料)
なお、令和8年度改定の施行は2026年6月とされているため、該当する事業所は早めに準備を進めることが推奨されます。
ケアプランデータ連携システムや生産性向上推進体制加算については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
2.一部算定要件に認められていた経過措置が2026年3月末に終了する
2024年に介護職員等処遇改善加算として一本化された際に、加算の算定要件についても経過措置が設けられました。
これらの経過措置は当初2025年3月31日が期日だったものが、2025年2月10日に厚生労働省が発表した方針により、一部は2025年度中に要件整備を行うことを誓約することで、2026年3月末まで延長できることとなりましたが、この経過措置の終了が迫っているため、満たせていない算定要件がある事業所は早急な対応が必要です。
以下に、要件整備の誓約によって延長できる算定要件をまとめました。
各算定要件の内容については、後述の「介護職員等処遇改善加算の区分ごとの算定要件」にて、詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
参考:『介護保険最新情報Vol.1353』(厚生労働省)
介護のコミミでは、令和7年度中の要件整備が必要とされている各算定要件を満たすための、具体的な記載方法を示したサンプルや、書類作成に使用できるひな形を無料でプレゼントしています。
ひな形を活用することで書類作成の時間を大幅に削減することができるので、ぜひ以下よりダウンロードして書類作成にお役立てください。
キャリアパス要件Ⅰに必要な書類のサンプル・ひな形の入手はこちら
キャリアパス要件Ⅱに必要な書類のサンプル・ひな形の入手はこちら
3.加算の対象サービスの拡大
令和8年度介護報酬改定(2026年6月施行)では、介護職員等処遇改善加算の対象サービスが拡大し、これまで対象外だった一部サービスに新たに処遇改善加算が新設されることが示されています。
具体的には、以下のサービスが新たに対象となります。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅介護支援・介護予防支援
公表資料では、これらの新設サービスに係る加算率(算定率)の目安として、訪問看護:1.8%、訪問リハ:1.5%、居宅介護支援・介護予防支援:2.1%が示されています。
また、新たに対象となる訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等は、加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件)または令和8年度特例要件により算定可能と整理されています(申請時点は誓約で算定可能とする配慮が示されています)。
出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
介護職員等処遇改善加算の加算率と算定要件
ここでは介護職員等の具体的な加算率や算定要件をまとめています。加算取得の検討の参考にして下さい。
介護職員等処遇改善加算の区分ごとの加算率
2026年6月施行の令和8年度介護報酬改定(2026年1月19日時点の公表資料)では、処遇改善加算の算定率が見直され、加算Ⅰ・Ⅱに上乗せ後の区分(Ⅰイ/Ⅰロ、Ⅱイ/Ⅱロ)が設けられています。主な算定率は以下の通りです。
| サービス区分 | 加算区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
| イ | ロ | イ | ロ | |||
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 24.9% | 26.6% | 20.7% | 17.0% |
| 夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 26.7% | 27.8% | 24.6% | 25.7% | 20.4% | 16.7% |
| 訪問入浴介護(介護予防を含む) | 12.2% | 13.3% | 11.6% | 12.7% | 10.1% | 8.5% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 11.8% | 9.9% | 8.3% |
| 地域密着型通所介護 | 11.7% | 12.7% | 11.5% | 12.5% | 10.5% | 8.9% |
| 通所リハビリテーション(介護予防を含む) | 10.3% | 11.1% | 10.0% | 10.8% | 8.3% | 7.0% |
| 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(介護予防を含む) | 14.8% | 15.9% | 14.2% | 15.3% | 13.0% | 10.8% |
| 認知症対応型通所介護(介護予防を含む) | 21.6% | 23.6% | 20.9% | 22.9% | 18.5% | 15.7% |
| 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む) | 17.1% | 18.6% | 16.8% | 18.3% | 15.6% | 12.8% |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 16.8% | 17.7% | 16.5% | 17.4% | 15.3% | 12.5% |
| 認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む) | 21.0% | 22.8% | 20.2% | 22.0% | 17.9% | 14.9% |
| 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護 | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 17.2% | 13.6% | 11.3% |
| 介護老人保健施設・短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 9.0% | 9.7% | 8.6% | 9.3% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院・短期入所療養介護(介護医療院)・短期入所療養介護(病院等) | 6.2% | 6.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 4.0% |
| 【新設】訪問看護 | 1.8% | |||||
| 【新設】訪問リハビリテーション | 1.5% | |||||
| 【新設】居宅介護支援・介護予防支援 | 2.1% | |||||
出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる整理が示されています。
※注:介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする
介護職員等処遇改善加算の区分ごとの算定要件
介護職員等処遇改善加算の算定要件については、区分ごとに必要な要件が異なったり、一部経過措置があったりするので、しっかり理解しておきましょう。
以下は、2026年1月時点で示されている、2026年6月施行の最新の算定要件です。
※2026年6月施行となる項目は赤太字にしています
| 要件 | 加算I | 加算II | 加算III | 加算IV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ | ロ | イ | ロ | ||||
| 月額賃金改善要件I(月給による賃金改善) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 月額賃金改善要件II(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善) | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | |
| キャリアパス要件I(任用要件・賃金体系の整備等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャリアパス要件II(研修の実施等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャリアパス要件III(昇給の仕組みの整備等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| キャリアパス要件IV(改善後の年額賃金要件) | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件) | ○ | ○ | – | – | – | – | |
| 職場環境等要件 | 区分ごとに1以上の取組(生産性向上は2以上) | – | – | – | – | ○ | ○ |
| 区分ごとに2以上の取組(生産性向上は3以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| HP掲載等を通じた見える化(取組内容の具体的記載) | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 生産性向上や協働化の取組 | – | ○ | – | ○ | – | – | |
出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(加算Ⅰ・Ⅱのイ/ロ区分、上乗せの考え方)/厚生労働省老健局長通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(基本要件の考え方)
※注:(○)は新加算Ⅰ~Ⅳの算定前に旧処遇改善加算を算定しており、かつ旧ベースアップ等支援加算が算定だった場合に満たす必要がある要件
ここからは、処遇改善加算の各算定要件について、それぞれ詳しく解説していきます。
月額賃金改善要件Ⅰとは(令和6年度の適用猶予あり)
月額賃金改善要件Ⅰは、介護職員等処遇改善加算Ⅳを算定した場合に得られる加算額の1/2以上を、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下、基本給等)により賃金改善することを求める要件です。
例えば、介護報酬が1,000万円の訪問介護事業所が介護職員等処遇改善加算Ⅳを算定する場合(令和8年度改定・2026年6月施行の公表資料では、訪問介護の加算Ⅳは17.0%)、加算額は170万円(=1,000万円×17.0%)となりますから、そのうちの1/2である85万円以上を基本給等で賃金改善する必要があります。
介護職員等処遇改善加算ⅠからⅢまでの加算を取得する場合も、介護職員等処遇改善加算Ⅳを算定した場合に得られる加算額を基準として、同様の賃金改善を求められます。
なお、月額賃金改善要件Ⅰは、2024年度中は適用が猶予されますが、2025年度以降の算定に向けた準備を求める観点から、2024年度の届出の際にも任意の記載事項とされています。
月額賃金改善要件Ⅱとは
月額賃金改善要件Ⅱは、旧処遇改善加算を算定していたが旧ベースアップ等加算を算定していなかった事業所が、2026年3月末日までに介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを新規に算定する場合に適用される要件です。旧ベースアップ等加算を算定した場合の加算額の3分の2以上を基本給等で改善することが求められます。
なお、旧ベースアップ等加算に相当する加算額は、介護職員等処遇改善加算の加算額に一定の係数を乗じて算出します。
キャリアパス要件Ⅰとは(令和7年度中の経過措置あり)
キャリアパス要件Ⅰは、介護職員の任用要件(賃金に関するものを含む)及び賃金体系を定めることを求める要件です。具体的には、次の3点を全て満たす必要があります。
- 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること
- 上記1に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く)について定めていること
- 上記1及び2の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること
介護のコミミでは、上記1・2で必要となるキャリアパス表について、具体的な記載方法を示したサンプルや、書類作成に使用できるひな形を無料でプレゼントしています。
ひな形を活用することで書類作成の時間を大幅に削減することができるので、ぜひ以下よりダウンロードして書類作成にお役立てください。
なお、本要件については令和7年度中の経過措置が認められており、就業規則等の整備を2026年3月末までに行うことを誓約すれば、当該年度当初から要件を満たしたものとみなされます
キャリアパス要件Ⅱとは(令和7年度中の経過措置あり)
キャリアパス要件Ⅱは、資質向上のための目標及び具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保することを求める要件です。
具体的には、次の2点を満たす必要があります。
- 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び次のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること
- 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと
- 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること
- 上記1について、全ての介護職員に周知していること。
介護のコミミでは、上記1で必要となる研修計画について、具体的な年間研修計画表のひな形を無料でプレゼントしています。
ひな形を活用することで書類作成の時間を大幅に削減することができるので、ぜひ以下よりダウンロードして書類作成にお役立てください。
また、本要件についても令和7年度中は経過措置が認められており、研修の計画策定等を2026年3月末までに行うことを誓約すれば、当該年度当初から要件を満たしたものとみなされます。
なお、研修体制の整備は介護職員向けeラーニングを導入することで、コストだけでなく研修準備や実施などの業務負担を軽減することもできます
以下の記事では、無料お試しから始めることができるおすすめの介護職員向けeラーニングを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
キャリアパス要件Ⅲとは(令和7年度中の経過措置あり)
キャリアパス要件Ⅲは、経験や資格等に応じた昇給の仕組みを設けることを求める要件です。
具体的には、次の2点を満たす必要があります。
- 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
具体的には、次のいずれかに該当する仕組みであること
- 経験に応じて昇給する仕組み:「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
- 資格等に応じて昇給する仕組み:介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組み
- 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み:「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み
- 上記1の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
介護のコミミでは、キャリパす要件Ⅲで必要となる各種規定について、具体的な記載方法を示したサンプルや、書類作成に使用できるひな形を無料でプレゼントしています。
ひな形を活用することで書類作成の時間を大幅に削減することができるので、ぜひ以下よりダウンロードして書類作成にお役立てください。
また、本要件についても令和7年度中の経過措置が認められており、就業規則等の整備や昇給の仕組みの整備を2026年3月末までに行うことを誓約すれば、当該年度当初から要件を満たしたものとみなされます。
キャリアパス要件Ⅳとは
キャリアパス要件Ⅳは、経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金が年額440万円以上となることを求める要件です。
ただし、次のような例外的な場合であって、合理的な説明がある場合は当てはまりません。
- 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
- 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
なお、旧3加算の一本化により旧特定加算による賃金改善額が月額8万円以上の改善継続が難しくなった背景もあり、令和7年度以降、月額8万円以上の要件については廃止されることになりました。
キャリアパス要件Ⅴとは
キャリアパス要件Ⅴは、一定以上の介護福祉士等を配置することを求める要件です。具体的には、サービス種類ごとに下表に掲げる加算の算定が必要とされています。
| サービス区分 | 加算区分 | ||
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 特定事業所加算 I | 特定事業所加算 II | – |
| 夜間対応型訪問介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| (介護予防)訪問入浴介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| 通所介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| 地域密着型通所介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | サービス提供体制強化加算 III イ又は Ⅳロ |
| (介護予防)通所リハビリテーション | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | 入居継続支援加算 Ⅰ 又は Ⅱ |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | 入居継続支援加算 Ⅰ 又は Ⅱ |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| 介護老人福祉施設 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | 日常生活機能支援加算I又はII |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | 日常生活機能支援加算I又はII |
| (介護予防)短期入所生活介護 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| 介護老人保健施設 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | 併設本体施設において旧特定加算Ⅰ 又は新加算Ⅰ の届出あり |
| (介護予防)短期入所療養介護(老健) | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | 併設本体施設において旧特定加算Ⅰ 又は新加算Ⅰ の届出あり |
| (介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外)) | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | 併設本体施設において旧特定加算Ⅰ 又は新加算Ⅰ の届出あり |
| 介護医療院 | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | – |
| (介護予防)短期入所療養介護(医療院) | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | 併設本体施設において旧特定加算Ⅰ 又は新加算Ⅰ の届出あり |
| 訪問型サービス(総合事業) | 併設本体施設において旧特定加算Ⅰ 又は新加算Ⅰ の届出あり | 旧特定加算Ⅰ 又はIIに準じる市町村独自の加算 | – |
| 通所型サービス(総合事業) | サービス提供体制強化加算 I | サービス提供体制強化加算 II | サービス提供体制強化加算I又はIIに準じる市町村独自の加算 |
引用元:厚生労働省老健局長通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
職場環境要件とは(令和7年度の経過措置あり)
職場環境等要件は、介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのいずれを算定するにあたっても満たすことが求められる要件です。
2025年度以降は、下表の6区分について、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、各区分ごとに2以上の取組を実施(「生産性向上のための取組」のみ3以上の取組を実施(うち⑰又は⑱は必須))し、新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は、各区分ごとに1以上の取組を実施(「生産性向上のための取組」のみ2以上の取組を実施)する必要があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | 1. 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
| 2. 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |
| 3. 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | |
| 4. 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | |
| 資質の向上やキャリアアップに 向けた支援 |
5. 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する研修の受講支援等 |
| 6. 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |
| 7. エルダー・メンター制度等導入 | |
| 8. キャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | 9. 休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
| 10. 勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
| 11. 有給休暇の取得しやすい雰囲気作りと取得状況の確認 | |
| 12. 情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消 | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | 13. 職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
| 14. 健康診断・ストレスチェックや、休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
| 15. 介護技術の修得支援、腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |
| 16. 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成 | |
| 生産性向上(業務改善及び働く 環境改善)のための取組 |
17. 業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、研修会の活用等) |
| 18. 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等) | |
| 19. 5S活動の実践による職場環境の整備 | |
| 20. 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | |
| 21. 介護ソフトや情報端末(タブレット・スマートフォン等)の導入 | |
| 22. 介護ロボットやICT機器(インカム、ビジネスチャットツール等)の導入 | |
| 23. 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備 | |
| 24. 協働化を通じた職場環境の改善(共同設置、ICTインフラの整備、人事管理システムの共通化等) | |
| やりがい・働きがいの醸成 | 25. ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化 |
| 26. 地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |
| 27. 介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |
| 28. ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
令和7年(2025年)より、介護職員等処遇改善加算ⅠおよびⅡにおいて必須となった要件「18.現場の課題の見える化」(生産性向上のための取組)では、生産性向上ガイドラインに基づいて、現場の課題を見える化することが求められています。
介護のコミミでは、こういった現場の課題の見える化を実践するための「課題把握シート」や「課題分析シート」を無料でプレゼントしているので、ぜひ以下よりダウンロードしてご活用ください。
介護職員等処遇改善加算に関するよくある質問
処遇改善加算でピンハネはできる?
処遇改善加算は原則ピンハネはできない制度となっております。
ピンハネできない主な理由は以下の3つです。
- 処遇改善手当の全額を介護スタッフに支払わなければならないため
- 就業規則に処遇改善手当の支給方法を明記しなければならないため
- ピンハネが発覚した場合は返還しなければならないため
指定権者(都道府県等)に計画書や実績書を提出し、指定権者(都道府県等)から国保連に情報提供されたのちに、加算の支払いが行われる仕組みとなっております。
ピンハネ、内部告、未払い違法などは良くある質問となりますが、これらは原則できません。
また、ピンハネを疑われないためにも以下の対策を実施しておくと良いでしょう。
- 就業規則に支給方法を明記する
- 給与明細に記載する
- 介護スタッフが相談しやすい体制を整える
- 疑われた際は丁寧に説明する
処遇改善加算でピンハネするとどうなる?
上述の通り、処遇改善加算は原則ピンハネできません。
ピンハネをした場合は、以下のようなペナルティが課される可能性があるため、注意しましょう。
- 報酬の返還を命じられる
- 加算金を徴収される
- 指定取消処分の対象となる
処遇改善加算1と2の違いは?
処遇改善加算ⅠとⅡの主な違いは以下の通りです。
- 加算率の違い:加算Ⅰの方が加算Ⅱよりも高い加算率が設定されています
- キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件):加算Ⅰでは必須、加算Ⅱでは不要
- 職場環境等要件:加算Ⅰは区分Ⅰ(3区分以上で計6項目以上)、加算Ⅱは区分Ⅱ(1区分以上で計3項目以上)
つまり、加算Ⅰを取得するには、加算Ⅱの要件に加えて「介護福祉士等の配置要件」を満たす必要があるという点が最大の違いとなります。
処遇改善加算の配分ルールは?
処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの配分ルールとしては、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める」とされています。
「新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一する」ことが原則です。
処遇改善加算の計画書記入例は?
厚生労働省のホームページ上で公開されている、介護職員の処遇改善の計画書記入例は以下からダウンロード可能です。
出典:厚生労働省 処遇改善計画書記入例
処遇改善加算の作成用、基本情報入力シートとなりますので、計画書の記入例として参考にしてみてください。
処遇改善加算の計算方法
処遇改善加算の計算方法としては、以下の3つのステップで進めることが可能です。まずは、1ヵ月あたりの総単位数を計算します。
- 総単位数 = 基本サービス単位数 + 加算と減算の合計
次に、総単位数に加算率を掛けましょう。
- 処遇改善加算の単位数=(処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数)×加算率
最後に処遇改善加算の総単位数を金額に換算します。
- 処遇改善加算の総額=(処遇改善加算の単位数)× 地域区分
補足
※各単位数の参照元は以下でご確認ください
※地域区分の参照元は「地域区分」にてご確認ください。
上で計算した「処遇改善加算の総額」が処遇改善加算の計算方法の答えとなります。
また、エクセルでの処遇改善加算計算方法を知りたい方は、各都道府県で発行しているエクセルをダウンロードするか、厚生労働省のHP上で必要な別紙様式のエクセルからダウンロード可能です。
計算方法は計算ソフトでも可能
処遇改善加算に限らず、複雑な計算方法には介護ソフトが必須です。
計算だけでなく、必要な手続きなども自動ツールで簡単に行うことも可能ですので、この機会に介護ソフトの入れ替えや導入も検討してみましょう。
無料でご相談いただけます
加算の算定にかかる事務処理手順
介護職員等処遇改善加算を算定手順を簡単にまとめると、
- 体制等状況一覧表等の届出(居宅系サービスの場合には算定開始月の前月15日まで、施設系サービスの場合は当月1日まで)
- 処遇改善計画書等の作成・提出 (算定開始月の前々月の末日まで)
- 実績報告書等の作成・提出(各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで)
が必要となります。
複数の事業所を有する事業者については、処遇改善の計画等について法人単位で一括して届出書を作成することも可能です。
また、小規模事業者(同一法人内の事業所数が10以下)や、2024年3月以前に加算を算定しておらず同年6月以降に介護職員等処遇改善加算Ⅲ又はⅣを新規に算定する事業所については、別様式を用いた処遇改善計画書・実績報告書等の作成・提出が可能となっています。
最後に
2024年度の介護報酬改定では、介護現場で働く職員の処遇改善を図るため、新たな介護職員等処遇改善加算が創設されました。
本記事では、介護職員等処遇改善加算の概要と算定要件、事務処理手順等について簡単に分かりやすく説明してきました。
介護職員等処遇改善加算は、従来の加算を一本化し、事業者及び職員にとってよりわかりやすく、取得しやすい仕組みとなっています。
一方で、キャリアパス要件の適合や職場環境等要件の充足など、算定要件はより高度化・多様化しています。
介護人材の確保・定着は喫緊の課題であり、処遇改善は採用や離職防止の重要な要素の一つです。
加算の趣旨を理解し、適切に算定・実施することで、魅力ある職場づくりにつなげていきましょう。
また、その他介護報酬改定2024の変更点を知りたい方は、以下の記事を読めば要件をすぐに知ることができます。
最短60秒入力!今すぐ無料相談!
ただでさえ複雑な処遇改善加算の算定要件を1つずつ満たすために、それぞれの書類をゼロから作成するのはとても大変ですよね。
そこで介護のコミミでは、算定要件を満たすために必要な書類を作成する負担を軽減するために、各算定要件ごとに合わせた書類のひな形・サンプルを無料でプレゼントしています。
ひな形・プレゼントを活用して、書類作成にかかる時間を削減しましょう!
無料プレゼント
ひな形・サンプルを入手する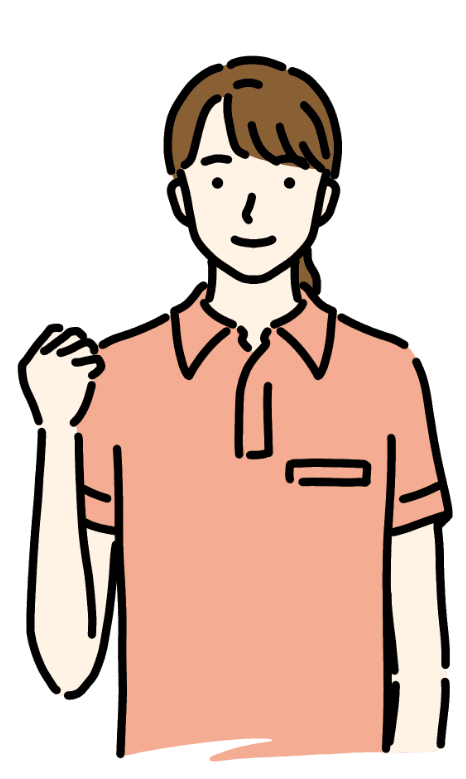
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する