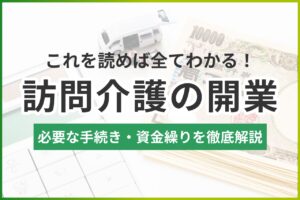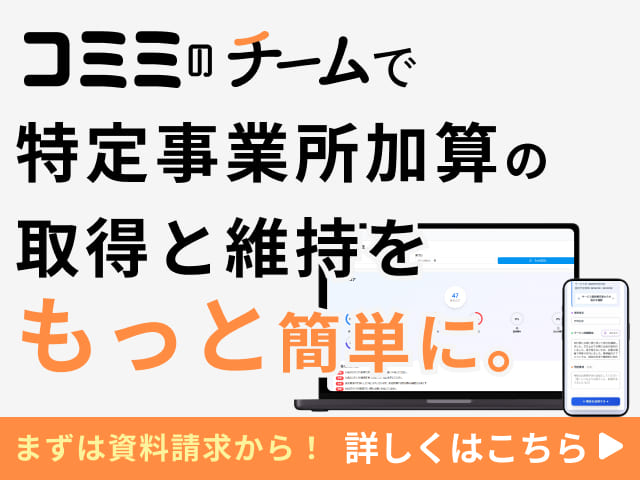訪問介護とケアマネ、どっちの仕事?役割分担の判断基準を場面別に解説
介護現場の声・悩み

「利用者さんの状態が変わったけど、これって私が対応すべき?それともケアマネさんに連絡?」「家族から相談を受けたけど、サ責として答えていいのかな…」
訪問介護の現場で働いていると、このような疑問は日常茶飯事です。特にサービス提供責任者(サ責)やヘルパーとして働き始めたばかりの方は、ケアマネージャーとの役割分担が曖昧に感じられ、「これって自分の仕事なのか、それともケアマネの仕事なのか」と迷うことが多いのではないでしょうか。
実は、この悩みは決してあなただけのものではありません。訪問介護とケアマネージャーは密接に連携しながら働くため、業務の境界線が曖昧になりやすいのです。
そこで、この記事では訪問介護の現場でよくある「これはどっちの仕事?」という疑問を、具体的な事例とともに徹底解説します。明日からの業務にすぐ活かせる実践的な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
この記事でわかること
- 訪問介護(サ責・ヘルパー)とケアマネージャーの基本的な役割の違い
- 場面別・ケース別の具体的な判断基準
- 実務で迷ったときの判断フローチャート
- スムーズな連携のための実践ポイント

この記事の筆者の伊藤です。業務の役割分担を正しく理解することで、不要な業務負担や悩みごとを回避できて、本来の業務に集中できるようになるはずなので、ぜひこの記事を通じて一緒に勉強していきましょう。
- 事例1:利用者が「買い物の内容を変えたい」と言った
- 事例2:利用者が「デイサービスの日を変えたい」と言った
- 事例3:ヘルパーが「利用者の歩行が不安定になった」と報告
- 事例4:利用者が「もっと訪問回数を増やしたい」と希望
- 事例5:ヘルパーが訪問したら利用者が不在だった
- 事例6:利用者の家族から「ヘルパーを変えてほしい」と依頼
- 事例7:福祉用具の追加が必要そう
- 事例8:訪問介護計画書の内容変更
訪問介護とケアマネージャーの基本的な役割の違い
まずは、訪問介護とケアマネージャーそれぞれの基本的な役割を整理しましょう。役割分担の基本を理解することが、日々の判断の土台となります。
ケアマネージャーの役割とは
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、利用者の介護サービス全体を統括する専門職です。訪問介護だけでなく、デイサービスや福祉用具、訪問看護など、複数のサービスを組み合わせて利用者を支援します。
厚生労働省が公開している資料では以下のように定義されています。
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者とされています。
出典:『介護支援専門員(ケアマネジャー) 』厚生労働省
ケアマネージャーの主な業務は以下の通りです。
- ケアプランの作成:利用者のアセスメントを行い、どのようなサービスをどれくらい利用するかを計画します
- サービス事業所との調整:訪問介護事業所やデイサービスなど、各サービス提供事業所との連絡調整を行います
- モニタリング:月に1回以上利用者宅を訪問し、ケアプランが適切に機能しているか確認します
- 給付管理:介護保険の利用状況を管理し、給付管理票を作成します
- サービス担当者会議の開催:関係するサービス事業所を集め、情報共有と連携を図ります
つまり、ケアマネージャーは「利用者の生活全体を見渡す司令塔」のような存在です。複数のサービスを組み合わせ、利用者にとって最適な支援体制を構築する役割を担っています。
サービス提供責任者(サ責)の役割とは
一方、サービス提供責任者は、訪問介護サービスに特化した責任者です。ケアマネージャーが作成したケアプランの中の「訪問介護部分」を、具体的にどう実施するかを計画し、管理します。
サービス提供責任者の主な業務は以下の通りです。
- 訪問介護計画書の作成:ケアプランに基づき、訪問介護の具体的な支援内容を計画します
- 利用者・家族との調整:訪問介護サービスの契約や、サービス内容の説明、相談対応を行います
- ヘルパーの管理・指導:ヘルパーへの指示や同行訪問、技術指導を行います
- 訪問介護のモニタリング:定期的に利用者宅を訪問し、サービスが適切に提供されているか確認します
- ケアマネージャーとの連携:利用者の状態変化や訪問介護に関する情報をケアマネに報告します
- 記録の管理:ヘルパーの訪問記録や実績の管理を行います
サ責は「訪問介護サービスの責任者」として、ケアマネと連携しながらも、訪問介護の専門家として独立した判断と責任を持ちます。
サービス提供責任者の業務内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
ヘルパー(訪問介護員)の役割とは
ヘルパーは、実際に利用者宅を訪問してサービスを提供する専門職です。サ責が作成した訪問介護計画書に基づき、身体介護や生活援助を行います。
ヘルパーの主な業務は以下の通りです。
- 身体介護・生活援助の実施:入浴介助、排泄介助、食事介助、掃除、調理などを行います
- 訪問記録の作成:サービス内容や利用者の様子を記録します
- サ責への報告:利用者の状態変化や気になることをサ責に報告します
- 利用者・家族とのコミュニケーション:日常的な会話や簡単な相談対応を行います
ヘルパーは利用者と最も接触時間が長いため、細かな変化に気づく重要な役割を担っています。その気づきをサ責に適切に報告することが、チームケアの質を高めます。
ケアマネとの役割分担の基本原則
ここまでの内容を整理すると、役割分担の基本原則は以下のようになります。
| 職種 | 役割 |
|---|---|
| ケアマネージャー | ケアプラン全体を統括し、複数のサービスを調整する |
| サービス提供責任者 | 訪問介護サービスの責任者として、訪問介護の計画・実施・管理を行う |
| ヘルパー | 訪問介護計画書に基づいて実際のサービスを提供し、気づきをサ責に報告する |
つまり、「ケアプラン全体に関わることはケアマネ、訪問介護サービスに特化したことはサ責・ヘルパー」という基本的な切り分けができます。ただし、実際の現場ではこの境界線が曖昧になるケースも多いため、次の章で具体的な場面ごとに見ていきましょう。
これはどっちの仕事?具体的な判断基準を場面別に解説
基本的な役割はわかっても、実際の現場では「この場面ではどう判断すればいいの?」と迷うことが多いものです。ここでは、よくある場面ごとに具体的な判断基準を解説します。
1.アセスメントと計画の作成
アセスメントや計画作成は、ケアマネとサ責の両方が行うため、特に混同しやすい業務です。
ケアマネージャーのアセスメント・計画作成は、利用者の生活全般を対象とします。心身の状態、生活環境、家族関係、経済状況、本人の希望など、幅広い視点から情報を収集し、「どのようなサービスが必要か」「どの事業所を利用するか」といったケアプラン全体を作成します。これには訪問介護だけでなく、デイサービスや福祉用具、場合によっては医療サービスなども含まれます。
一方、サ責のアセスメント・計画作成は、訪問介護サービスに特化しています。ケアマネが作成したケアプランの中の「訪問介護部分」について、「いつ」「誰が」「何を」「どのように」行うかを具体化した訪問介護計画書を作成します。例えば、ケアプランに「週3回の訪問介護」と書かれていたら、その3回の訪問で具体的にどのような支援を行うかを詳細に計画するのがサ責の役割です。
そのため、判断軸としてはケアプラン全体に関わることか、訪問介護サービスの具体的な実施方法かがポイントとなるでしょう。

訪問介護計画書はケアマネが作成したケアプランに基づいて作成する必要があります。ケアプランにないものを訪問介護計画書に記載して、実際にサービスを提供したとしても、介護報酬を請求できないので注意しましょう。
2.モニタリング
モニタリングも、ケアマネとサ責の両方が行う業務ですが、その目的と範囲が異なります。
ケアマネージャーのモニタリングは、月に1回以上(要介護3以上の場合など状況により頻度は変わります)利用者宅を訪問し、ケアプラン全体が適切に機能しているかを確認します。訪問介護だけでなく、デイサービスの利用状況、福祉用具の適合性、家族の介護負担など、生活全般の変化を把握します。
サ責のモニタリングは、訪問介護サービスが計画通りに提供されているか、利用者の満足度はどうか、新たなニーズはないかなど、訪問介護に特化した内容を確認します。頻度は事業所や利用者の状況により異なりますが、定期的に実施します。
具体例を挙げると、利用者が「最近デイサービスで疲れるようになった」と話した場合、これはケアプラン全体に関わる変化なので、サ責が気づいたとしてもケアマネに情報提供することが重要です。一方、「掃除の順番を変えてほしい」といった訪問介護の具体的な内容については、サ責が判断して対応できます。
3.サービス担当者会議
サービス担当者会議は、利用者に関わる複数のサービス事業所が集まり、情報共有や連携を図る重要な場です。
ケアマネージャーが会議を招集し、進行します。ケアプランの説明や、各事業所への役割の確認、今後の方針の検討などを行います。
サ責(場合によってはヘルパー)は、会議に参加し、訪問介護の状況を報告します。「現在どのような支援を行っているか」「利用者の様子で気になる点」「他のサービスとの連携で必要なこと」などを伝え、他のサービス事業所からの情報も共有します。
つまり、会議の主催・進行はケアマネ、訪問介護の状況報告はサ責・ヘルパーという役割分担になります。サ責としては、会議の前に訪問介護の状況をしっかり整理しておき、建設的な意見を提供することが求められます。
4.利用者の状態変化への対応
これは現場で最も判断に迷う場面の一つです。利用者の状態変化にはさまざまなケースがあり、対応する人も状況により異なります。
急な体調不良の場合
ヘルパーが訪問中に利用者の体調不良に気づいた場合、まずサ責に報告します。サ責が状況を判断し、必要に応じてケアマネに連絡します。緊急性が高い場合(意識がない、激しい痛みなど)は、救急車を呼ぶことが最優先ですが、その後必ずサ責とケアマネに報告します。
このような緊急時の対応フローは、事業所内で事前に共有しておくことが重要です。「どのような状況でサ責に連絡すべきか」「サ責がケアマネに連絡する基準は何か」を明確にしておくと、迷わず対応できます。
入院・退院の場合
利用者が入院することになった場合、ケアマネが主導して対応します。入院中のケアプラン変更、退院後のサービス調整などを行います。サ責は、入院の情報をケアマネに伝え、退院後の訪問介護についてケアマネと連携しながら準備します。
退院時には、ケアマネが医療機関と連携して情報収集を行いますが、サ責も退院前カンファレンスに参加し、訪問介護で注意すべき点(ADLの変化、医療的な配慮など)を確認することが望ましいです。
サービス内容の変更希望の場合
これは内容により判断が分かれます。
- 訪問介護計画の範囲内での変更(例:掃除する部屋の順番を変える、調理のメニューを変えるなど)→ サ責が判断して対応
- サービスの回数や時間の変更(例:週2回を週3回に増やす、1時間を1.5時間にするなど)→ ケアプラン変更が必要なのでケアマネに相談
- 新しいサービスの追加(例:今まで生活援助だけだったが身体介護も必要になったなど)→ ケアマネに相談し、ケアプラン変更
つまり、ケアプランの変更を伴うかどうかが判断の分かれ目です。ケアプランの範囲内で対応できることはサ責の裁量で、ケアプランを超える変更はケアマネの領域となります。
5.ご家族への対応
ご家族からの相談や要望も、内容により対応する人が変わります。
ケアプラン全体に関わる相談(例:「デイサービスも利用したい」「ショートステイを検討したい」など)は、ケアマネの役割です。サ責やヘルパーが相談を受けた場合は、「ケアマネさんに相談してみてください」と案内し、ケアマネにも情報共有します。
訪問介護サービスに関する相談(例:「ヘルパーさんの訪問時間を変更したい」「掃除の場所を増やしてほしい」など)は、サ責が対応します。ケアプラン変更が必要な場合は、サ責からケアマネに連絡します。
ヘルパーは、サービス提供時の日常的なコミュニケーションを行います。「今日はどうでしたか?」「最近お変わりありませんか?」といった会話の中で、重要な情報をキャッチしたらサ責に報告します。
家族対応で大切なのは、「誰に相談すればいいかを案内すること」です。たとえ自分の担当範囲でなくても、「それはケアマネさんに相談するといいですよ」「サ責から連絡させますね」と、適切な窓口に繋ぐことで、利用者・家族の安心につながります。
6.サービスの調整や多職種連携
サービスの調整や多職種連携も、範囲により担当が異なります。
他のサービス事業所との調整(例:デイサービスと訪問介護の時間が重ならないように調整する、訪問看護との連携など)は、ケアマネが行います。ケアマネは全体を見渡しているため、各事業所間の調整役を担います。
訪問介護事業所内の調整(例:ヘルパーのシフト調整、担当ヘルパーの変更など)は、サ責が行います。
ただし、訪問介護のシフトを変更した結果、他のサービスと重なる可能性がある場合は、サ責からケアマネに事前に相談・連絡することが望ましいです。連携がスムーズになり、利用者の混乱も防げます。
7.クレームへの対応
クレームは、内容により一次対応する人が変わります。
訪問介護サービスに関するクレーム(例:「ヘルパーの態度が悪い」「掃除が雑」「時間に遅れる」など)は、まずサ責が対応します。事実確認を行い、謝罪や改善策を提示します。場合によっては管理者や事業所全体で対応することもあります。
ケアプラン全体や他のサービスに関するクレームは、ケアマネが対応します。ただし、訪問介護に関連する部分があれば、サ責と連携して対応します。
クレーム対応で重要なのは、迅速な初動と情報共有です。ヘルパーがクレームを受けた場合は、すぐにサ責に報告し、サ責は状況によりケアマネにも情報共有します。隠したり、放置したりすると、問題が大きくなることがあります。
実際によくある「どっちの仕事?」を事例を用いて判定
ここからは、実際の現場でよく遭遇する具体的なケースを取り上げ、「これは訪問介護の仕事か、ケアマネの仕事か」を判定していきます。
事例1:利用者が「買い物の内容を変えたい」と言った
答え:サ責が対応(訪問介護計画の範囲内なら)
買い物支援は訪問介護の生活援助の一環ですので、基本的にはサ責の判断で対応できます。例えば、「いつもキャベツを買っているけど、今日は白菜にしたい」「牛乳の銘柄を変えたい」といった日常的な変更は、ヘルパーがその場で対応し、サ責に報告すれば問題ありません。
ただし、買い物の頻度を増やしたい(週1回を週2回にするなど)、買い物の時間を長くしたいといった場合は、ケアプラン変更が必要になる可能性があるため、サ責からケアマネに相談します。
対応フロー:ヘルパーが要望を聞く → サ責に報告 → サ責が判断(計画範囲内なら対応、範囲外ならケアマネに相談)
事例2:利用者が「デイサービスの日を変えたい」と言った
答え:ケアマネ(ケアプラン変更が必要)
デイサービスは訪問介護とは別のサービスですので、ケアマネが対応します。ヘルパーやサ責が相談を受けた場合は、「ケアマネさんに相談してみてくださいね」と案内し、同時にケアマネにも「利用者さんがデイサービスの曜日変更を希望されています」と情報共有すると、スムーズに進みます。
ただし、デイサービスの日が変わると訪問介護の予定も調整が必要になる場合があります。ケアマネから「デイの日が変わるので、訪問介護の日も調整できますか?」と連絡が来たら、サ責が事業所内で調整します。
対応フロー:利用者・家族がケアマネに相談 → ケアマネがデイサービス事業所と調整 → 必要に応じてサ責にも連絡 → サ責が訪問介護の予定を調整
事例3:ヘルパーが「利用者の歩行が不安定になった」と報告
答え:サ責に報告 → サ責がケアマネに連絡
利用者の身体機能の変化は、ケアプラン全体に影響する重要な情報です。まずヘルパーはサ責に報告し、サ責は状況を確認した上でケアマネに連絡します。
歩行が不安定になった場合、訪問介護での見守りや介助が必要になるだけでなく、福祉用具(杖や歩行器)の検討、訪問リハビリの導入、場合によっては主治医への相談なども必要になる可能性があります。これらはケアプラン全体に関わるため、ケアマネが中心となって対応します。
サ責は、訪問介護での具体的な変化(いつから、どのような場面で、どの程度不安定か)を詳しくケアマネに伝えることで、適切な対応につなげることができます。
情報共有のタイミング:すぐに転倒の危険がある場合は、当日中にケアマネに連絡。緊急性は低いが継続的な変化として気になる場合は、数日以内に連絡し、状況を共有します。
事例4:利用者が「もっと訪問回数を増やしたい」と希望
答え:ケアマネ(ケアプラン変更が必要)
訪問回数の変更は、ケアプランの変更を伴うため、ケアマネが対応します。ヘルパーやサ責が要望を聞いた場合は、「なぜ増やしたいのか」「どの程度増やしたいのか」といった具体的なニーズを確認し、ケアマネに情報提供します。
ケアマネは、介護保険の限度額内で可能かどうか、他のサービスとのバランスはどうか、本当に訪問回数を増やすことが最適な解決策かなどを総合的に判断します。場合によっては、訪問介護の回数を増やすのではなく、デイサービスの利用を提案することもあります。
サ責が最初に相談を受けた場合の対応:利用者の話をよく聞き、背景にあるニーズを理解する → 「ケアマネさんと相談して、どのような対応ができるか検討しますね」と伝える → ケアマネに詳しい情報を提供する
事例5:ヘルパーが訪問したら利用者が不在だった
答え:まずサ責に報告 → 状況によりケアマネへ
利用者が予定通り在宅していなかった場合、まずヘルパーはサ責に報告します。サ責は、家族に連絡したり、状況を確認したりします。
単なる日程の勘違いであれば、サ責と利用者・家族で調整して解決します。しかし、利用者と連絡が取れない、家族も所在を知らない、認知症で徘徊の可能性があるなど、緊急性が高い場合は、サ責はケアマネにも連絡します。ケアマネは家族やケースワーカーなど、より広い範囲で情報収集や対応を行います。
緊急度による判断基準:
- 日程の勘違い、事前連絡なしの外出(本人に連絡がつく)→ サ責が対応
- 連絡がつかない、徘徊の可能性、安否確認が必要 → サ責からケアマネに連絡、場合によっては警察にも連絡
事例6:利用者の家族から「ヘルパーを変えてほしい」と依頼
答え:サ責(訪問介護事業所内の調整)
ヘルパーの変更は、訪問介護事業所内の人員調整ですので、サ責が対応します。まず、なぜ変更を希望するのか理由をしっかり聞き、ヘルパーとの相性の問題なのか、サービス内容に不満があるのかなどを把握します。
担当ヘルパーの変更が適切と判断した場合は、事業所内で調整します。ただし、サービス内容そのものに問題がある場合は、ヘルパーを変えるだけでなく、サ責として改善策を検討する必要があります。
ケアマネへの報告も重要です。「家族の要望でヘルパーを変更しました」と事後報告することで、ケアマネも状況を把握でき、今後の連携がスムーズになります。
対応手順:家族から要望を聞く → 理由を詳しく確認 → サ責が判断してヘルパーを調整 → 新しいヘルパーに引き継ぎ → ケアマネに報告
事例7:福祉用具の追加が必要そう
答え:ケアマネに情報提供
福祉用具は訪問介護とは別のサービスですので、ケアマネが福祉用具事業所と連携して対応します。しかし、実際に利用者の生活を見ているサ責やヘルパーが「手すりがあった方が安全そう」「ポータブルトイレが必要では?」と気づくことは非常に重要です。
サ責やヘルパーができることは、気づきをケアマネに伝えることです。「最近、トイレまでの移動が大変そうです。ポータブルトイレの検討はいかがでしょうか」といった具体的な情報提供により、ケアマネは適切なサービス調整ができます。
このように、訪問介護の担当者は、自分の担当範囲を超えることでも「気づいたら情報提供する」という姿勢が、利用者にとってより良い支援につながります。
事例8:訪問介護計画書の内容変更
答え:サ責(軽微な変更)、ケアマネ連携が必要な場合も
訪問介護計画書はサ責が作成するものなので、基本的にはサ責が変更します。ただし、ケアプランとの整合性を保つ必要があります。
軽微な変更(例:掃除する部屋の順番を変える、調理の具体的なメニューを調整するなど)は、サ責の判断で変更し、ケアマネへは報告程度で済みます。
ケアプランに影響する変更(例:生活援助から身体介護に変更する、サービス時間を大幅に変更するなど)は、ケアマネと相談してケアプランも変更してもらう必要があります。
訪問介護計画書はケアプランに基づいて作成されるため、ケアプランの範囲を超える変更はできないという原則を覚えておきましょう。

ここまで紹介した事例にないケースが発生した時のために、次章では迷った時の判断フローチャートも解説します。いざという時の判断軸としてご活用ください。
迷ったときの判断フローチャート
ここまで様々なケースを見てきましたが、実際の現場では判断に迷うこともあります。そんなときに使える、シンプルな判断フローチャートをご紹介します。
判断フローチャート
ステップ1:訪問介護サービスだけの問題か?
- はい → サ責が対応(次のステップへ)
- いいえ(他のサービスや生活全般に関わる)→ ケアマネに相談
ステップ2:ケアプラン変更が必要か?
- はい(回数・時間の変更、サービス内容の大幅な変更など)→ ケアマネに相談
- いいえ(訪問介護計画の範囲内での調整)→ サ責が対応可能
ステップ3:緊急性はあるか?
- 高い(急な体調変化、安否確認など)→ サ責に即報告 → サ責がケアマネにも連絡
- 低い(日常的な調整など)→ 通常の報告ルートで対応
この3つのステップで、ほとんどの場面で判断できます。特に重要なのは「訪問介護サービスだけの問題か」という最初の問いです。訪問介護の範囲内であればサ責が対応し、それを超える場合はケアマネと連携するという基本を押さえておきましょう。
判断に迷ったときの実践的なコツ
フローチャートに従っても判断に迷う場合は、以下の対応がおすすめです。
- サ責に相談する(ヘルパーの場合):迷ったらまずサ責に報告。サ責が判断します
- ケアマネに情報共有する(サ責の場合):自分の範囲で対応できるが、念のためケアマネにも共有しておくと安心
- 事業所内でルールを決めておく:「こういう場合はこう対応する」というルールを事前に共有しておくと迷わない
- 判断を記録する:「こういう理由でこう判断した」と記録しておくと、後で振り返ることができ、チーム内での学びにもなる
最も避けたいのは、「誰かがやるだろう」と放置することです。迷ったら、まず誰かに相談・報告することが、利用者の安全と適切なケアにつながります。
役割が曖昧になりやすいポイントと対処法
ここまで明確な判断基準をお伝えしてきましたが、実際の現場では「グレーゾーン」も存在します。役割分担が曖昧になりやすい理由と、その対処法を見ていきましょう。
「グレーゾーン」が生まれる理由
訪問介護とケアマネの役割分担が曖昧になる理由には、いくつかのパターンがあります。
連携の重要性
そもそも、訪問介護とケアマネは完全に独立した存在ではなく、連携しながら利用者を支える関係です。そのため、業務の境界線が重なる部分も多く、「これは絶対にこっち」と明確に切り分けられないこともあります。
例えば、利用者の状態変化への対応は、サ責が気づいてケアマネに情報提供し、ケアマネが全体を調整し、サ責が訪問介護の具体的な対応を変更するという連携プロセスが必要です。このような連携が必要な場面では、「どちらか一方だけの仕事」とは言い切れません。
事業所によるルールの違い
また、事業所や地域により、慣習や運用ルールが異なることもグレーゾーンを生む原因です。ある事業所では「この程度の変更はサ責の判断でOK」とされていることが、別の事業所では「必ずケアマネに確認」となっていることもあります。
このような違いは、事業所の方針や、ケアマネとの関係性、地域の慣習などにより生じます。そのため、自分の事業所のルールを確認しておくことが重要です。
ケアマネから無理な依頼をされたとき
現場でよく聞かれる悩みの一つが、「ケアマネから訪問介護の範囲を超えた依頼をされる」というものです。例えば、「利用者の通院同行をしてほしい」「庭の草むしりをしてほしい」など、介護保険の訪問介護では対応できない内容を依頼されることがあります。
訪問介護でできること・できないこと
まず、訪問介護で対応できる範囲を明確にしておきましょう。
- 対応できること:身体介護(食事介助、入浴介助、排泄介助など)、生活援助(掃除、洗濯、調理、買い物など)で、利用者本人の日常生活に直接必要な行為
- 対応できないこと:医療行為(一部の例外を除く)、利用者以外のためのサービス(家族の食事作りなど)、日常生活の範囲を超えること(庭の草むしり、ペットの世話など)
ケアマネがこのルールを知らないわけではありませんが、利用者や家族の強い要望を受けて、無理を承知で依頼してくることもあります。
断り方の具体例とコミュニケーション術
訪問介護の範囲を超える依頼を受けた場合、適切に断ることも専門職としての責任です。ただし、断り方には工夫が必要です。
良くない断り方
「それは訪問介護ではできません」(理由を説明せず、冷たく断る)
良い断り方
「お気持ちはよくわかります。ただ、通院同行は介護保険の訪問介護では対応できないことになっています。代わりに、通院介助のサービスを提供している事業所をご紹介できますので、一緒に検討しませんか?」
ポイントは以下の3つです。
- 共感を示す:「お気持ちはわかります」「必要性は理解しています」など、相手の立場を理解していることを伝える
- 理由を明確に説明する:「介護保険のルールで」「訪問介護の範囲では」と、個人的な判断ではなく制度上の理由であることを説明する
- 代替案を提示する:「できない」で終わらせず、「こういう方法はどうでしょう」と建設的な提案をする
このようなコミュニケーションにより、ケアマネとの関係を壊さずに、適切な範囲でサービスを提供することができます。
ケアマネとの連携がうまくいかないとき
ケアマネとの連携に悩むサ責も少なくありません。よくある連携トラブルと改善策を見ていきましょう。
よくある連携トラブル
- ケアマネからの連絡が少ない:利用者の状況変化を教えてくれない、サービス担当者会議の案内が遅いなど
- ケアマネへの報告がいつも後回しになる:サ責側も忙しく、報告が遅れてしまう
- 役割分担の認識がずれている:お互いに「これはそっちの仕事」と思っている
- 情報共有の方法が定まっていない:電話がいいのか、FAXがいいのか、対面がいいのか
改善のための工夫
連携をスムーズにするには、以下のような工夫が効果的です。
- 定期的な情報共有の機会を作る:「毎月○日に情報交換しましょう」など、定期的な連絡のタイミングを決めておく
- 報告のフォーマットを統一する:「利用者の状況」「気になる点」「相談事項」など、項目を決めておくと報告しやすい
- 役割分担を明文化する:契約時や初回の打ち合わせで、「こういう場合はサ責が対応」「こういう場合はケアマネに連絡」と確認しておく
- 「報告・連絡・相談」を意識する:報告(事実を伝える)、連絡(情報を共有する)、相談(判断に迷うことを相談する)を使い分ける
- お互いの大変さを理解する:ケアマネは多くの利用者を担当し多忙、サ責も複数の利用者とヘルパーの管理で多忙。お互いの状況を理解し、協力する姿勢が大切
連携は「やらなければならない義務」ではなく、「利用者により良いケアを提供するための手段」です。この目的を共有できれば、多少の行き違いがあっても、お互いに協力して乗り越えられます。
スムーズな連携のための実践ポイント
最後に、訪問介護とケアマネがスムーズに連携するための、より具体的な実践ポイントをお伝えします。
サ責が押さえるべき報告・連絡のタイミング
サ責として、どのようなタイミングでケアマネに報告・連絡すべきか、具体的な基準を持っておくことが重要です。
必ずケアマネに報告すべき事項
- 利用者の身体状況の大きな変化:転倒、体調不良、ADLの低下、認知症の進行など
- 入院・退院:入院した際は速やかに、退院の情報を得た際も早めに連絡
- サービス拒否や利用中止の希望:一時的なものでも、理由と状況を報告
- 家族状況の変化:主介護者の体調不良、家族関係のトラブルなど、ケアプランに影響する変化
- クレームや苦情:小さなことでも共有しておくと、後で問題が大きくなるのを防げる
- ケアプラン変更の必要性:サービス回数や内容の変更が必要と感じた場合
- 他のサービスとの連携が必要な事項:デイサービスでの様子、訪問看護との情報共有が必要なことなど
報告の優先順位
すべてをすぐに報告する必要はありません。緊急度と重要度により優先順位をつけましょう。
- 即座に連絡(当日中):緊急の体調変化、入院、重大な事故、安否確認が必要な状況など
- 数日以内に連絡:ADLの変化、家族状況の変化、サービス内容の調整が必要な事項など
- 定期報告で共有:日常的な様子、小さな気づき、特に問題はないが知っておいてほしいことなど
事業所によっては、「毎月の報告書をケアマネに提出する」といったルールがある場合もあります。そのルールに従いつつ、緊急性の高いことは都度連絡するという使い分けが大切です。
ヘルパーが意識すべきこと
ヘルパーは、利用者と最も長く接する立場です。その気づきがチームケアの質を大きく左右します。
サ責への報告内容
ヘルパーがサ責に報告すべき内容は、以下のようなものです。
- 利用者の様子の変化:表情、口調、活気、食欲、排泄、睡眠など
- 身体状況の変化:歩行、立ち座り、入浴時の身体状態、皮膚の状態など
- 生活環境の変化:室内の様子、物が増えた・減った、家族の出入りなど
- 利用者や家族からの相談・要望:サービスに関することだけでなく、生活全般の困りごとも
- サービス提供時の気づき:「いつもと違う」と感じたこと、うまくいったこと、難しかったことなど
「こんな小さなこと報告していいのかな」と迷うこともあるかもしれませんが、小さな変化の積み重ねが大きな問題を未然に防ぐこともあります。迷ったら報告する、という姿勢が大切です。
記録の書き方
ヘルパーの記録は、サ責やケアマネが利用者の状況を把握する重要な情報源です。記録を書く際のポイントは以下の通りです。
- 事実を具体的に書く:「元気がなかった」ではなく「いつもは笑顔で挨拶してくれるが、今日は表情が硬く、挨拶の声も小さかった」
- 利用者の言葉を記録する:「〇〇さんは『最近膝が痛い』と話していた」など、本人の言葉をそのまま記録
- 対応したことも書く:気づいたことだけでなく、自分がどう対応したかも記録すると、次回の参考になる
- 時系列で書く:訪問の流れに沿って、時系列で記録すると読みやすい
良い記録は、サ責やケアマネとの連携をスムーズにし、チーム全体で利用者を支える力になります。
事業所内でルールを明確にする
個々のサ責やヘルパーが頑張るだけでなく、事業所全体でルールを整備することも重要です。
連絡フローの整備
「どのような場合に、誰に、どのように連絡するか」をフローチャートやマニュアルにしておくと、迷わず対応できます。例えば:
- 緊急時の連絡先(サ責、管理者、ケアマネ、家族)の一覧
- 緊急度別の連絡フロー(緊急時は電話、通常時はFAXなど)
- 報告すべき内容のチェックリスト
これらを事業所内で共有し、新人ヘルパーにも研修で伝えることで、チーム全体の対応力が向上します。
判断基準の共有
この記事で紹介したような判断基準を、事業所内で共有しておくことも有効です。例えば、定期的なミーティングで「こういうケースがあったけど、どう対応すべきだった?」と事例を共有し、チームで学び合う機会を作ると良いでしょう。
また、ケアマネとも事前に「このような場合はサ責で対応します」「このような場合は連絡します」と認識を合わせておくと、日々の連携がスムーズになります。
訪問介護とケアマネの役割分担でよくある質問
最後に、訪問介護とケアマネの役割分担について、現場でよく聞かれる質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 訪問介護計画書とケアプランの違いは?
A. ケアプランは、ケアマネが作成する利用者の生活全体を支援する計画です。訪問介護、デイサービス、福祉用具など、複数のサービスが含まれます。一方、訪問介護計画書は、サ責が作成する訪問介護サービスに特化した計画です。ケアプランの中の「訪問介護部分」を、より具体的に「いつ、誰が、何を、どのように」行うかを示します。訪問介護計画書はケアプランに基づいて作成されるため、ケアプランの範囲を超えることはできません。
Q2. サービス担当者会議は誰が招集する?
A. サービス担当者会議はケアマネが招集します。ケアプランの作成時や変更時、定期的な見直しの際などに開催されます。サ責やヘルパーは参加者として会議に出席し、訪問介護の状況を報告したり、他のサービス事業所と情報共有したりします。会議の日程調整や案内もケアマネが行いますので、案内を受けたら可能な限り参加するようにしましょう。
Q3. 利用者の状態報告はどのタイミングで?
A. 緊急度により異なります。緊急性が高い場合(急な体調変化、転倒、入院など)は、当日中にケアマネに連絡します。緊急性は低いが重要な変化(ADLの低下、認知症の進行、家族状況の変化など)は、数日以内に連絡します。日常的な様子は、定期的な報告書や次回のモニタリング時に共有すれば十分です。「これは緊急か?」と判断に迷ったら、早めに連絡する方が安全です。
Q4. ケアマネへの報告は電話?書面?
A. 緊急時は電話、通常時は書面やFAXが一般的ですが、ケアマネの希望や事業所のルールにより異なります。最近はメールやチャットツールを使う事業所も増えています。契約時や初回の打ち合わせで、「普段の連絡はどの方法が良いですか?」「緊急時の連絡先は?」と確認しておくとスムーズです。また、電話で報告した内容も、後で書面に残しておくと記録として有効です。
Q5. ヘルパーが直接ケアマネに連絡してもいい?
A. 基本的にはサ責を通して連絡するのが原則です。サ責は訪問介護サービス全体を把握しており、適切な判断ができます。ただし、緊急時でサ責に連絡が取れない場合や、事業所のルールで「緊急時はヘルパーから直接連絡してもよい」となっている場合は、直接連絡することもあります。いずれの場合も、後でサ責に報告することを忘れずに。
Q6. サ責とケアマネ、どちらが上?
A. 上下関係ではありません。サ責とケアマネは、それぞれ異なる専門性を持ち、対等な立場で連携するパートナーです。ケアマネはケアプラン全体を統括し、サ責は訪問介護の専門家として独立した判断と責任を持ちます。お互いの専門性を尊重し、利用者のために協力し合う関係が理想です。
Q7. ケアマネがいない場合はどうする?
A. 介護保険サービスを利用する場合、通常はケアマネがケアプランを作成します。もし「ケアマネがいない」という場合は、セルフプラン(利用者自身が作成)か、まだケアマネが決まっていない状態かもしれません。その場合は、地域包括支援センターや市町村の介護保険窓口に相談するよう、利用者・家族に案内しましょう。訪問介護サービスを提供するには、基本的にケアプランが必要です。
Q8. 役割分担で困ったときの相談先は?
A. まずは事業所内のサ責や管理者に相談しましょう。それでも解決しない場合や、ケアマネとの関係が難しい場合は、地域包括支援センターに相談することもできます。地域包括支援センターは、地域の介護サービス事業所やケアマネを支援する役割も持っていますので、客観的なアドバイスを得られることがあります。また、事業所が加盟している訪問介護事業所の協議会などでも、事例相談を受け付けていることがあります。
まとめ:役割分担を理解して、より良いケアの提供を
ここまで、訪問介護とケアマネージャーの役割分担について、基本から具体的なケースまで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
役割分担の基本
- ケアマネージャー:ケアプラン全体を統括し、複数のサービスを調整する司令塔
- サービス提供責任者:訪問介護サービスの責任者として、計画・実施・管理を行う専門家
- ヘルパー:実際にサービスを提供し、利用者の変化に気づく最前線の支援者
判断の基本原則
- 訪問介護サービスだけの問題 → サ責が対応
- ケアプラン全体や他のサービスに関わる問題 → ケアマネに相談
- ケアプラン変更が必要 → ケアマネに相談
- 緊急性が高い → サ責に即報告 → サ責がケアマネにも連絡
ただし、これらの基本原則よりも大切なことがあります。それは、「迷ったら連携・相談する」という姿勢です。
訪問介護とケアマネは、完全に独立した存在ではなく、利用者を中心に協力し合うチームです。役割分担を理解することは重要ですが、それ以上に、お互いの専門性を尊重し、情報を共有し、困ったときには助け合う関係を築くことが、より良いケアにつながります。
「これは自分の仕事か、ケアマネの仕事か」と悩むことは、決して悪いことではありません。それは、あなたが責任を持って仕事をしている証拠です。ただ、一人で抱え込まず、チームで解決していく姿勢が大切です。

この記事が、日々の業務の中で「どっちの仕事?」と迷ったときの道しるべになれば幸いです。訪問介護の現場で働くあなたの専門性と判断力は、利用者の生活を支える大きな力です。自信を持って、そしてチームと連携しながら、これからも質の高いケアを提供できると良いですね。
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する