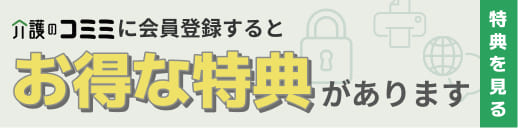介護情報基盤とは?2026年に向けて事業所が今すべきこと
介護施設の経営・運営改善

「また新しいシステムが導入されるのか…」「今でも事務作業に追われているのに、さらに負担が増えるのでは?」そんな不安を抱えている介護事業所の経営者・管理者の方も多いのではないでしょうか。
2026年4月から段階的に運用が開始される「介護情報基盤」は、確かに介護業界のデジタル化を推進する国家レベルの重要な新システムです。
確かに、新しいシステムの導入にあたって様々な不安や課題もあります。しかし、適切な準備と理解があれば、介護情報基盤は事業所運営の強力な味方となります。
そこでこの記事では、介護事業所の経営者・管理者のみなさんに向けて、介護情報基盤の全体像から具体的な準備方法、経営改善に活かす方法まで、厚生労働省の公式資料に基づいて詳しく解説いたします。この記事を読むことで、導入への不安を解消し、むしろ他の事業所に先駆けて業務効率化を実現するチャンスとして捉えらることができるようになるでしょう。

こんにちは、この記事の著者の伊藤です。新しいシステムとなるとどこか複雑で難しい印象もありますが、この記事を通じて私と一緒にひとつずつ勉強しましょう!
介護情報基盤とは?2026年導入される新システムの全体像

「介護情報基盤って何か複雑で難しそう」という方のために、まずは簡単に全体像から見ていきましょう。
介護情報基盤の定義と目的
介護情報基盤とは、介護サービス利用者に関する情報を、利用者、自治体、介護事業所、医療機関などが電子的に閲覧・共有するための新しいデジタルシステムです。この革新的な基盤により、要介護認定情報、ケアプラン、請求・給付情報などが一元的にデジタル管理され、関係者間のスムーズな情報交換が実現されます。
この介護情報基盤は、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」に基づき整備が進められており、厚生労働省の公式資料では、多様な主体が協働して高齢者を地域で支えていく地域包括ケアシステムの深化・推進に繋がるシステムとして位置づけられています。
厚生労働省が推進するこのシステムの最大の目的は、介護現場における業務効率化と、利用者へのサービス品質向上の両立です。従来の紙ベースでの情報管理から脱却し、リアルタイムでの情報共有を可能にすることで、介護業界全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させます。
従来の介護情報管理との違い
これまでの介護現場では、利用者の情報管理は主に紙媒体や各事業所独自のシステムで行われてきました。この従来の方法では、以下のような課題が存在していました。
- 情報の重複入力による事務負担の増大
- 関係機関間での情報共有に時間がかかる
- 書類の紛失や情報の更新漏れのリスク
- 利用者の状況変化への迅速な対応が困難
介護情報基盤の導入により、これらの課題は大幅に改善されます。一度入力された情報は関係者全員が即座に閲覧でき、更新情報もリアルタイムで反映されるため、より効率的で正確な介護サービスの提供が可能になります。
政府が推進する背景と社会的意義
日本は2040年頃に高齢者人口がピークを迎えると予測されており、特に要介護認定率が高い85歳以上の人口が急速に増加します。一方で、生産年齢人口の減少により、介護分野における深刻な人材不足が懸念されています。
このような社会情勢の中で、限られた人的資源を最大限に活用し、質の高い介護サービスを持続的に提供するためには、ICTを活用した業務効率化が不可欠です。介護情報基盤は、この社会的課題に対する国家レベルでの解決策として位置づけられています。
介護情報基盤の導入スケジュールと最新動向

介護情報基盤はいつから始まるのでしょうか。2025年8月時点で公表されている情報を元に大まかなスケジュールを整理してみましょう。
2026年4月から段階的運用開始
厚生労働省は、2026年4月から準備が整った自治体から順次、介護情報基盤の運用を開始する予定です。これは介護情報基盤に係る規定の施行期日が「公布後4年以内の政令で定める日」とされており、令和8年4月1日(2026年4月1日)の施行を目指して準備が進められているためです(厚生労働省資料より)。
初期段階では、システム基盤が整備された先進的な自治体や、積極的にデジタル化に取り組んでいる介護事業所から運用が開始されます。これらの先行事例から得られる知見やノウハウは、後続の自治体や事業所の導入支援に活用される予定です。
全国展開に向けた段階的実施
政府の計画では、2026年度以降、希望する自治体から順次運用を開始し、全国実施を目指しています。全国展開の完了目標時期については、現在のところ明確な期限は示されておらず、各自治体の準備状況に応じて段階的に進められる予定です。
全国展開が完了すれば、日本全国どこでも統一された介護情報管理システムが利用可能となり、利用者が転居した場合でも、継続的で一貫性のある介護サービスの提供が実現されます。
自治体の準備状況と導入に向けた課題
介護情報基盤の導入に向けて、各自治体では準備が進められていますが、様々な課題が存在しています。厚生労働省は、市町村のシステム改修の対応状況について意見照会・調査を行う予定としており、具体的な準備状況の把握を進めています。
想定される課題として、以下のような点が考えられます。
- 市町村の介護保険事務システムの標準準拠システムへの移行対応
- 既存システムの改修が必要となる場合の技術的対応
- システム導入に伴う職員研修や体制整備
- 介護事業所との連携体制の構築
これらの課題に対応するため、厚生労働省はシステム設計・開発にかかる調整のほか、事業者支援策の構築を行うとしており、自治体や事業所への支援体制の整備が進められています。

ここまでの情報で、介護情報基盤システムが日本の高齢化社会においてとても重要な役割を期待されていることが分かりますね。
一方で個々の事業所や利用者にはどんなメリットがあるか、もう少し一緒に深掘りしてみましょう!
介護情報基盤導入で変わる5つのメリット

ここからは、介護事業所目線で介護情報基盤の導入メリットを見ていきましょう。
業務効率化による人件費削減効果
介護情報基盤の最も大きなメリットの一つは、業務効率化による大幅な人件費削減効果です。従来、介護事業所では、同じ情報を複数の書類に何度も記入する重複作業が多く発生していました。
新システムでは、一度入力した情報が自動的に関連する全ての書類やシステムに反映されるため、事務作業時間を大幅に短縮できます。
削減された時間とコストは、利用者への直接的なケアサービスに振り向けることができ、サービスの質向上と経営効率化の両立が可能になります。
情報共有の迅速化とサービス品質向上
関係機関間での情報共有が迅速化されることで、利用者の状況変化に対する対応スピードが格段に向上します。例えば、利用者の体調変化や要介護度の変更があった場合、関係する全ての事業所や医療機関に即座に情報が共有されます。
これにより、ケアプランの見直しや緊急対応がより迅速かつ適切に実施でき、利用者の安全性と満足度の向上につながります。また、医療と介護の連携もスムーズになり、包括的なケアの提供が実現されます。
利用者満足度向上と選択肢の拡大
利用者自身がマイナポータルを通じて、自分のケアプランやサービス利用状況を確認できるようになります。これまで「知らされる」立場だった利用者が、「自ら確認し、選択する」主体的な立場に変わることで、サービスへの理解と満足度が向上します。
また、LIFE(科学的介護情報システム)との連携により、利用者の状態改善の推移や効果的なケア方法に関するデータも可視化され、より個別化されたサービス選択が可能になります。
事務負担軽減と職員のやりがい向上
紙ベースの事務作業が大幅に削減されることで、介護職員は本来の専門性を活かしたケアワークに集中できるようになります。これは職員のやりがい向上と専門性の発揮につながり、結果的に離職率の低下と人材定着にも寄与します。
特に、新人職員にとっては複雑な事務手続きの負担が軽減されるため、介護の専門技術習得により多くの時間を割くことができ、早期の戦力化が期待できます。
コンプライアンス強化とリスク管理
デジタル化により、すべての業務プロセスが記録・追跡可能になるため、コンプライアンスの強化とリスク管理の向上が実現されます。不正請求の防止や、監査対応の効率化など、事業運営の透明性と信頼性が大幅に向上します。
また、システム上でのアクセス権限管理により、個人情報保護も従来以上に強化され、利用者や家族からの信頼獲得にもつながります。
介護事業所が直面する導入課題と解決策
システム改修費用の負担と補助金活用
介護情報基盤への対応には、既存システムの改修や新規導入が必要となり、相応の費用負担が発生します。特に小規模な介護事業所にとって、この初期投資は大きな負担となる可能性があります。
この課題に対して、厚生労働省はシステム設計・開発にかかる調整のほか、事業者支援策の構築を行うとしており、何らかの支援策が検討されていることが示されています。ただし、具体的な補助金制度の開始時期や内容については、現在のところ明確な発表はされていません。

例えば今使っている介護ソフトが介護情報基盤に対応する予定かどうかをメーカー担当者に確認したり、必要に応じてソフトを切り替るなどの検討も必要になります!
また、複数の事業所でシステムを共同利用することで、一事業所あたりの負担を軽減する方法も推奨されており、地域の事業所同士で連携した導入計画を立てることが重要です。
職員のITリテラシー不足への対応
介護現場では、ITに不慣れな職員も多く、新システムの導入に対する不安や抵抗感が課題となることが予想されます。こういった問題を解決するためには、段階的な研修の実施が不可欠でしょう。
セキュリティ対策の強化方法
個人情報を扱う介護情報基盤では、高度なセキュリティ対策が必要不可欠です。具体的には、各事業所で以下のセキュリティ対策を実施する必要があります。
- 端末認証システムの導入
- ウイルス対策ソフトの最新版維持
- アクセス権限の適切な管理
- 定期的なセキュリティ研修の実施
- ネットワーク環境の暗号化
これらの対策には専門知識が必要なため、ITセキュリティ専門業者との連携や、セキュリティ対策を含んだパッケージサービスの活用も検討すべきです。
利用者・家族への説明とコミュニケーション
システム変更に伴い、利用者や家族に対する丁寧な説明が重要になります。特に高齢者の中には、個人情報のデジタル化に不安を感じる方も多いため、メリットとセキュリティ対策について分かりやすく説明する必要があります。
介護情報基盤導入に向けた具体的な準備の手順
介護情報基盤の開始までにまだ少し時間があるかもしれませんが、準備の手順だけでも早めに把握しておいて、時間に余裕があるうちに着実に準備を進めておくと良いでしょう。
必要な機器の準備
介護情報基盤の利用には、以下の機器の準備が必要です。
ハードウェア要件
- インターネット接続可能なパソコンまたはタブレット
- マイナンバーカード読み取り用ICカードリーダー
- プリンター(必要に応じて)
- セキュリティ対策用のルーター
ソフトウェア要件
- 最新版のウェブブラウザ
- ウイルス対策ソフト
- 端末認証用ソフトウェア
- 既存システムとの連携ソフト(必要に応じて)
インターネット環境とセキュリティ対策
安定したインターネット環境の確保は、システム運用の基盤となります。推奨される環境は以下の通りです。
- 光回線による高速・安定接続
- 冗長化されたネットワーク構成
- VPN接続によるセキュリティ強化
- 定期的な通信速度測定と最適化
また、Wi-Fi環境を整備する場合は、WPA3などの最新暗号化方式を採用し、定期的なパスワード変更を実施することが重要です。
職員研修とマニュアル整備
システム導入成功の鍵は、職員の習熟度にあります。効果的な研修プログラムの構成要素は以下の通りです。
- システム概要と目的の理解
- 基本操作方法の習得
- 業務フロー別の実践演習
- トラブル対応方法の学習
- セキュリティ意識の向上
研修と併せて、日常的に参照できる操作マニュアルの整備も重要です。マニュアルは、画面キャプチャを多用した視覚的で分かりやすい内容とし、定期的な更新を行うことが推奨されます。
介護情報基盤の運用開始後の活用方法
ここでは、実際に介護情報基盤が開始した後のイメージについて解説します。実際の運用イメージを把握しておくことで、事前準備も有意義になるはずです。
ケアプランデータ連携システムとの統合
介護情報基盤は、既存の「ケアプランデータ連携システム」と統合される予定です。この統合により、ケアマネジャーが作成したケアプランを、サービス提供事業所が即座に確認・活用できるようになります。
ケアプランデータ連携システムに統合するメリットとして、以下が挙げられます。
- ケアプラン変更の即座な反映
- サービス提供記録の一元管理
- 多職種連携の効率化
- 利用者の状況変化への迅速な対応
マイナンバーカードを活用した業務フロー
マイナンバーカードの活用により、利用者の本人確認と情報アクセスが大幅に効率化されます。具体的な活用場面は以下の通りです。
- 初回利用時の本人確認と情報登録
- サービス利用時の迅速な情報確認
- 緊急時の医療情報アクセス
- 家族による代理確認(適切な権限設定下で)
ただし、マイナンバーカードを持参できない利用者への配慮も必要で、従来の確認方法も併用できる体制を整備することが重要です。
LIFE情報の効果的な活用方法
LIFE(科学的介護情報システム)との連携により、利用者の状態改善に関するデータを効果的に活用できます。具体的な活用方法は以下の通りです。
- 個別ケアプランの根拠データとしての活用
- サービス効果の客観的評価
- 他事業所との比較による改善点の発見
- 家族への説明資料としての活用
これらのデータを活用することで、より科学的で効果的な介護サービスの提供が可能になり、利用者の状態改善と事業所の質向上の両立が実現されます。
他事業所・医療機関との連携強化
介護情報基盤により、地域の介護事業所や医療機関との連携が格段に強化されます。具体的な連携の効果は以下の通りです。
- 転院・転所時の情報引き継ぎの円滑化
- 緊急時の迅速な情報共有
- 多職種カンファレンスの効率化
- 地域包括ケアシステムの実効性向上
この連携強化により、利用者にとってより継続性のある包括的なケアの提供が実現され、地域全体の介護・医療の質向上につながります。
介護情報基盤の導入準備はいつから始めるべき?
介護情報基盤の導入に向けた準備はいつから始めるべきでしょうか。答えはは、ゆっくりでも良いので今から始めるべきです。その理由を解説します。
早期導入による先行メリットがある
介護情報基盤の早期導入により、事業所は以下の先行者メリットを享受できます。
- 業務効率化による低コスト運営の実現
- 高品質サービス提供による差別化
- 職員満足度向上による人材確保の優位性
- 利用者・家族からの信頼獲得
特に、システムに習熟した職員のノウハウは、後発事業所では短期間で習得することが困難な競争優位性となります。
利用者・家族に付加価値を提供できる
システムの透明性と利便性を活かして、利用者・家族により高い満足度を提供できます。
- サービス内容の可視化による安心感の提供
- 状態改善の客観的データによる効果実感
- 24時間いつでもアクセス可能な情報提供
- 緊急時の迅速な対応体制
人材採用・定着が期待できる
介護情報基盤の導入は、人材採用と定着にも大きなメリットをもたらすでしょう。
- 働きやすい職場環境のアピール
- 専門性を活かせる業務環境の提供
- キャリアアップ支援体制の充実
- 先進的な事業所としてのブランドイメージ向上
まとめ:介護情報基盤で実現する介護事業所の未来
介護情報基盤は、2026年4月から段階的に運用が開始される、介護業界のデジタル化を推進する重要なインフラです。
導入には課題もありますが、厚生労働省による事業者支援策の構築や段階的な導入スケジュールにより、多くの事業所が対応可能な環境が整備されつつあります。重要なのは、早期の準備開始と戦略的な活用計画の策定です。
介護情報基盤を単なるシステム導入ではなく、事業所の未来を切り開く投資として捉え、利用者により良いサービスを提供するための重要な一歩として、積極的に取り組んでいくことをお勧めします。
参考資料
本記事は、厚生労働省「介護情報基盤について」(令和6年7月8日 社会保障審議会介護保険部会第113回資料)等の公式情報を参考に作成しています。
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する