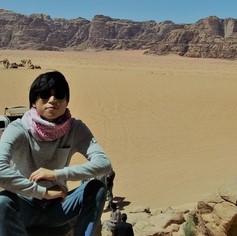ケアマネは辛いよ!仕事が大変な理由と解消法を紹介!
介護現場の声・悩み働きやすい職場の選び方


ケアマネの業務って本当に大変・・・。必要な仕事ではあるけど、こんなに大変だと辞めようか悩む。他のケアマネさんはどう思ってるのかな?辛さを抜けるにはどうすればいい?
このような疑問にお答えします。
介護保険サービス利用に必須のケアプラン作成に関わるのが、ケアマネジャーです。
利用者一人ひとりのニーズをつかみ、課題解消に向けたサービス調整が主な業務で、利用者とサービスを提供する事業所にとっては欠かせない存在ですよね。
しかし実際にケアマネとして働いている人の中には「仕事が辛い」と感じ、残念ながら退職してしまうようなケースも少なくありません。
多くのケアマネは、実際にどのようなことに対して大変さを感じているのでしょうか?
今回はケアマネの仕事が大変な理由と、辛いと感じても辞めないで済む解消法を紹介します。
ケアマネは辛い!多くの人が大変さを感じている主な理由5つ

ケアマネの仕事に辛さを感じているのは、あなただけではありません。
たくさんの人たちが多くの苦労を抱えているのです。
まずは他のケアマネが大変さを感じている、主な理由を5つ見ていきましょう。
とにかく仕事量が多い
1つ目の理由は、とにかく仕事量が多いことです。
前述したように、ケアマネの主な業務は利用者のケアプラン作成。しかし実際には、ケアプラン作成に関係する業務が非常に多くあります。
利用者の自宅への訪問と面接、家族からの聞き取り、アセスメントのまとめ、ケアプランの作成、担当者会議の開催、関係機関とのやりとり、モニタリングなど、やるべきことは膨大です。
さらに慢性的な人材不足から、1人のケアマネが抱える利用者数も決して少なくありません。
やってもやっても終わりが見えない仕事量の多さに、疲弊と大変さを感じているケアマネはたくさんいます。
介護保険だけでなく幅広い知識が求められる
ケアマネに必要とされる知識は、介護保険だけではありません。
ケアプラン作成に介護保険の知識はマストですが、介護保険以外の知識も仕事をする上では求められます。
利用者から介護方法や医療に関する相談を受けることもあり、ある程度は答えられるようにしておかなければいけません。
介護保険や介護に関する制度は絶えず変化をするので、常に新しい情報にアンテナを張り巡らせておく必要もあるでしょう。
さらに利用者と信頼関係を築き、本音を語ってもらうための面接技法や心理学理論なども重要です。
幅広い知識を得るために常に勉強をしなければいけず、通常業務と合わせて負担となっていきます。
ケアプランの内容次第で利用者の生活が変わるプレッシャーが大きい
ケアマネジャーが作ったケアプランの内容で、利用者に介護サービスが提供されるようになります。
介護に関するニーズを抱える利用者にとっては、提供されるサービス内容次第で生活がガラっと変わるといっても過言ではありません。
ケアマネには常に利用者の生活を左右するプレッシャーが付きまとい、新人やベテラン問わずにストレスと感じる人がいます。
事業所と利用者の間にはさまれる
事業所と利用者の間にはさまれるのが4つ目の理由です。
ケアマネが関わるのは利用者やその家族、サービス事業所、行政、医療機関と実にさまざま。
たくさんの人たちの間に入って、中心でそれぞれをつなぐ役割をケアマネが担っています。
真ん中に立つということは、間にはさまれるということ。
事業所からは利用者に対する文句を言われたり、反対に利用者からはサービスに関する文句を言われたりすることもあるでしょう。
また医療機関に介護や日常生活の視点が欠けていると、医療優先とする頭ごなしの指示を受けるかもしれません。
それぞれの間で板ばさみとなりやすく、ケアマネが大変さを感じる部分でもあります。
資格更新の負担が大きい
最後の理由が、資格更新の負担が大きいことです。
ケアマネの資格は一度取得しても、一生有効ではありません。5年後ごとに更新する必要があります。
さらに更新には、数十時間の研修受講が必須です。
ただでさえ日常業務で多忙を極めているにも関わらず、5年一度とはいえ更新のために数十時間の研修を受けるのは大変なこと。
資格更新の負担が大きいことも、ケアマネが大変さを感じている理由の一つです。
介護業界で転職を考えているけど、転職先が自分に合った職場かわからない。
そんな方のために、独自の指標を用いて働きやすい職場の情報だけを集めた「介護のコミミいい職場検索」で、あなたに合った職場を探すことができます。
働きやすい職場が見つかる
近くのいい職場を探す
ケアマネが辛いと感じたらどうする?辞めないで済む7つの解決法

ケアマネの仕事は確かに大変です。
辞めたいと思うことも多々あることでしょう。
しかしせっかく資格を取得して就いた仕事です。
辛いと感じた時に、辞めないで済むための7つの解決法を紹介します。
ケアマネの仕事自体を好きなのかどうか考えてみる
まずは、ケアマネの仕事自体が好きなのかどうかを考えてみてください。
忙しくて時間にも心にも余裕がなくなると、物事の本質が見えなくなります。
確かにケアマネの仕事は多忙で、ストレスに感じることもたくさんあるでしょう。
しかし仕事に対するやりがいや魅力を再認識することで、退職せずに続けられるようになることもあります。
ケアマネのメリットを思い返してみる
2つ目はケアマネのメリットを思い返してみることです。
ケアマネになる前には、介護施設で介護職として働いていた人も多いのではないでしょうか。
もちろん勤務する施設にもよりますが、介護職は重労働です。
利用者の直接介護で腰を痛めたり、夜勤を含む不規則勤務で体調を崩したりすることも少なくありません。
また対応する利用者によっては、身体的・精神的な暴力をふるわれることもあるでしょう。
ケアマネは基本的にデスクワーク。事務作業は多くなりますが、腰痛を含む身体への負担は介護職よりも少ないはずです。
また基本的には日勤勤務なので、規則正しい生活を送れることもできます。
ケアマネのメリットをもう一度確認してみることで、仕事を続けられるかもしれませんよ。
業務をスケジューリング化させる
仕事量が多くて大変さを感じている人におすすめなのが、業務のスケジューリング化です。
抱えている仕事内容を可視化させることで、効率よく仕事を進めることができるようになります。
仕事に優先順位を付けて、何日のどの時間帯に行うのかを一つずつ決めてみましょう。
持っている仕事量は変わらなくても効率良く処理できるようになれば、仕事のストレスを減らすことができますよ。
知識の習得はひたすら学ぶしかない
4つ目は知識の習得はひたすら学ぶしかないことです。
介護保険サービスを始め、各種の福祉サービスや制度、地域資源、医療、面接技法など習得するべきことは山ほどあります。
特にケアマネになりたての頃は習得すべき知識量の多さに圧倒されますが、ひたすら学んで身につける以外に方法はありません。
最初は大変ですが一度ある程度の知識が身につけば、その後は少しずつ楽になっていきます。
できることには限界があることを知る
ケアマネとしてできることには限界があると知ることも大切ですね。
利用者に思うようなサービスを提供することができず、歯がゆい思いをすることもあるでしょう。
またニーズを上手くアセスメントできずに、サービス調整がスムーズにいかないこともあります。
ケアマネはスーパーマンではありません。
課題を解決したい、利用者のためにサポートをしたいと思っても、できることには限界があります。事前に限界があることを理解しておくことで、必要以上のストレスを感じずに済むでしょう。
一人で業務や責任を抱え込まないようにする
6つ目は、一人で業務や責任を抱え込まないようにすることです。
多くのケアマネはそれぞれでたくさんのケースを担当しているため、例え同じ事業所内でも同僚や上司に相談しにくい環境があります。
しかし一人で抱え込んでしまうと大きな負担になり、プレッシャーも大きくなってしまうでしょう。
事業所内で他のスタッフに遠慮をせずに相談をしてください。
もし相談相手がいない場合は外に目を向けてみましょう。
ケースに関わっているサービス事業所や行政の他、地域のケアマネ部会などに参加をして情報や悩みを共有するのもおすすめです。
オンとオフを上手に切り替える
最後の解決法が、オンとオフを上手に切り替えることです。
せっかく仕事が終わっても、オフの時間に仕事を持ち込むのは良くありません。
オフの時間は仕事を忘れて、プライベートを楽しみましょう。
美味しいものを食べたり、旅行をしたり、買い物に行ったりと、好きなことに没頭してください。
オンとオフを上手に切り替えることで、大変なケアマネの仕事もきっと乗り越えられるはずです。
施設ケアマネや在宅ケアマネなど、働くフィールドを変えてみるのも方法の一つ

どうしてもケアマネの仕事を続けられないと感じたら、働くフィールドを変えてみてはいかがでしょうか。
ケアマネには主に特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設系で働く人と、居宅支援事業所といった在宅系で働く人に分けられます。
どちらも利用者のケアプランを作成することに変わりはありません。
しかしそれぞれに特徴は異なります。
施設ケアマネが持つ利用者数は、1人当たり最大100人。
人数は多くなりますが、施設内サービスのケアプランだけを作成します。
また利用者が生活をしているので、ケアプラン作成のための面接などもスムーズに行えるのは大きなメリットですね。
ただし空き時間で利用者介護を求められる場合もあります。
在宅ケアマネが持つ利用者数は、1人当たり最大35名。
施設ケアマネよりも少ないですが、自宅や事業所訪問などの手間を考えると、決して少ないとはいえません。
施設系と在宅系で、ケアマネの働き方は異なります。
施設系は合わなかったけど、在宅系は合った。またその逆もありえるので、働くフィールドを変えてみるのも一つの方法ですね。
まとめ
利用者のケアプランを作成するケアマネは仕事量が多いことを始め、辛いと感じる人が少なくありません。
確かに仕事内容は大変ですが、「辛い」「辞めたい」と思う前に解決できる方法がないかを考えてみましょう。
仕事のメリットを思い返す、業務をスケジューリング化させる、一人で仕事を抱え込まないなど、退職する前にできることはまだあるはずです。
どうしても退職したいと思ったら、働くフィールドを変えてみるのも一つの方法ですね。
基本的な業務内容は同じでも働く場所が異なれば、また頑張って働けるようになるかもしれません。
![]() 【まとめ記事】介護ソフトで後悔しないために読んでほしい記事9選
【まとめ記事】介護ソフトで後悔しないために読んでほしい記事9選
![]() 介護の人事担当が選ぶおすすめ求人サイトランキング!転職を有利にするには?
介護の人事担当が選ぶおすすめ求人サイトランキング!転職を有利にするには?
介護業界で転職を考えているけど、転職先が自分に合った職場かわからない。
そんな方のために、独自の指標を用いて働きやすい職場の情報だけを集めた「介護のコミミいい職場検索」で、あなたに合った職場を探すことができます。
働きやすい職場が見つかる
近くのいい職場を探す
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する