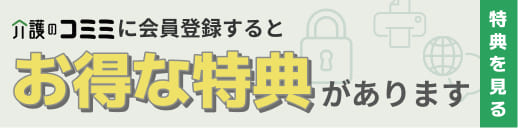就労選択支援とは?2025年10月開始の新制度を事業所向けにわかりやすく解説
介護施設の経営・運営改善

2025年10月1日から新たにスタートする「就労選択支援」は、障害のある方が自分に適した働き方や支援サービスを選択できるよう支援する制度です。就労移行支援や就労継続支援を実施している事業所にとって、この新制度への対応は今後の事業運営に大きく影響する重要な変更となります。
そこで、この記事では、就労選択支援の制度概要から実施に向けた準備事項まで、事業所の経営者・管理者が知っておくべき基本情報を解説いたします。新制度への準備を進める際の参考としてお役立てください。
就労選択支援とは?新制度の基本概要

就労選択支援は、令和6年度障害福祉サービス報酬改定において新設された障害福祉サービスの一つです。2025年10月1日から施行され、障害のある方が自身の希望や適性、能力に合った就労先や支援サービスを適切に選択できるよう支援することを目的としています。
参考:厚生労働省『就労選択支援の実施について』(令和7年3月31日)制度創設の背景と目的
従来、就労移行支援や就労継続支援などのサービスを利用する際は、利用者自身が事業所に問い合わせ、見学や体験を経て利用を決定していました。しかし、このプロセスでは以下のような課題が指摘されていました。
- 利用者の適性と事業所のサービス内容のミスマッチが発生
- 客観的なアセスメントが不十分なまま利用開始となるケース
- 結果として就労が定着しない、または適切でない支援を受け続ける状況
- 利用者が自分に最適なサービスを見つけられない
就労選択支援は、これらの課題を解消し、利用者と支援者が協働してアセスメントを行うことで、より適切な支援サービスや就労先の選択を可能にする制度として創設されました。
従来の課題とミスマッチ解消への取り組み
新制度では、専門的なアセスメントツールや実際の作業体験を通じて、利用者の強みや課題を多角的に評価します。これにより、単なる希望ベースではなく、客観的なデータに基づいた支援サービスの選択が可能となり、就労定着率の向上が期待されています。
また、ハローワークや医療機関、教育機関との連携を強化することで、利用者を取り巻く環境全体を考慮した包括的な支援計画の策定を実現します。
就労選択支援の対象者と適用スケジュール
就労選択支援の対象者は、新たに就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)の利用を希望する方、または既にこれらのサービスを利用している方です。
参考:厚生労働省『就労選択支援実施マニュアル』対象者と適用時期
就労選択支援の対象者と各サービスへの適用時期は以下の通りです。
| サービス種別 | 新たに利用する意向がある障害者 | 既に利用しており、支給決定の更新の意向がある障害者 | |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 現行の就労アセスメント対象者 ( 下記以外の者 ) | 令和7年10月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
| ・50歳に達している者 ・障害基礎年金1級受給者 ・就労経験ありの者(就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者) |
希望に応じて利用 | ||
| 就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | ||
| 就労移行支援 | 希望に応じて利用 |
令和9年4月から原則利用 ※標準利用期間を超えて継続する場合 |
|
この表に示されている通り、就労継続支援B型については2025年10月から、就労継続支援A型については2027年4月から、新規利用者に対して就労選択支援の利用が原則として必要となります。
利用期間
就労選択支援の利用期間は原則1か月とされています。ただし、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2か月の支給決定を行うことが可能です。
この期間中に、以下のような支援を集中的に実施します。
- 作業体験や企業実習を通じた適性評価
- 職業興味検査などの客観的アセスメント
- 関係機関との連携による情報収集
- 個別就労選択プランの作成
就労選択支援の実施要件と事業所の条件
就労選択支援を実施する事業所には、質の高いアセスメントと適切な支援を提供するための明確な要件が設けられています。
実施主体の要件
就労選択支援を実施できる事業所は、以下の要件を満たす必要があります。
- 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者
- 過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された実績を有すること
- 都道府県知事が認める就労支援の経験及び実績を有すること
地域連携の要件
実施事業所は、地域の支援体制との連携を重視し、以下の活動を継続的に行うことが求められます。
- 自立支援協議会への定期的な参加:地域の障害者支援に関する情報共有と連携体制の構築
- ハローワークへの定期的な訪問等:最新の求人情報や雇用動向の収集、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努める
- 企業との関係構築:利用者に対して進路選択に資する情報を提供する
人員配置基準
就労選択支援の人員配置基準は以下の通りです。
- 就労選択支援員:15:1以上の配置が必要
- 就労選択支援員養成研修の修了が要件
- サービス管理責任者の配置は不要:就労選択支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要とし、サービス管理責任者の配置は求めない
なお、経過措置として、就労選択支援員養成研修開始から2年間は基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなします。
就労選択支援の利用の流れとアセスメント内容
就労選択支援は、体系的なプロセスに基づいて実施されます。利用者が最適な支援サービスや就労先を選択できるよう、段階的にアセスメントと支援計画の策定を行います。
相談・申請から終了までの4ステップ
ステップ1:相談・申請
- 利用者または家族が市町村窓口や計画相談支援事業所に相談
- 就労選択支援の利用希望を確認
- 障害福祉サービス受給者証の申請手続き
- 実施事業所との利用契約締結
ステップ2:アセスメントの実施
- 利用者の基本情報と希望の聞き取り
- 事業所内での作業体験の実施
- 企業実習の調整と実施
- 職業興味検査や適性検査の実施
- 関係機関からの情報収集
ステップ3:計画作成と関係機関連携
- アセスメント結果の分析と評価
- ハローワーク、医療機関、教育機関との情報共有
- 個別就労選択プランの作成
- 利用者・家族への結果説明と合意形成
ステップ4:サービス終了と次のステップへの移行
- 就労選択支援評価書の作成
- 推奨する支援サービスや就労先の提示
- 次の支援機関への引き継ぎ
- 必要に応じたフォローアップ
作業体験・企業実習の具体的内容
就労選択支援では、実際の作業や職場環境を体験することで、より実践的なアセスメントを実施します。
- 事業所内作業体験:軽作業、事務作業、製造作業など多様な作業を通じた適性評価
- 企業実習:実際の企業での短期間の実習体験
- 職場見学:様々な職場環境の見学と適応可能性の確認
- 模擬面接:就職活動に向けた準備とコミュニケーション能力の評価
個別就労選択プランの作成方法
収集した情報とアセスメント結果に基づき、以下の要素を含む個別就労選択プランを作成します。
- 利用者の強みと課題の整理
- 適性のある職種・業務内容
- 必要な合理的配慮の内容
- 推奨する支援サービス
- 就労に向けた具体的なステップ
- 継続的な支援の必要性
就労選択支援の報酬体系と加算制度
就労選択支援の報酬体系が厚生労働省により設定され、事業所の安定的な運営と質の高いサービス提供を支援する仕組みが整備されています。
基本報酬の単位数
就労選択支援の基本報酬は以下の通りです。
| 報酬項目 | 単位数 |
|---|---|
| 就労選択支援サービス費 | 1,210単位/月 |
| 特定事業所集中減算* | 200単位/月 |
※正当な理由がないまま、過去6か月間にアセスメントを受けた利用者のうち、就労移行支援・就労継続支援A型・B型のいずれかのサービスを同じ事業者が8割(80%)を超えて提供している場合に適用される減算。
処遇改善加算の適用
就労選択支援においても、他の障害福祉サービスと同様に「福祉・介護職員等処遇改善加算」が適用されます。これにより、就労選択支援に従事する職員の処遇改善と人材確保を図ることができます。
既存の就労系サービスへの影響と移行スケジュール

就労選択支援の導入により、既存の就労系障害福祉サービスの利用方法に大きな変更が生じます。事業所は、この変更に適切に対応するため、移行スケジュールを把握し、必要な準備を進める必要があります。
就労継続支援B型への影響
令和7年(2025年)10月1日以降、新たに就労継続支援B型の利用を希望する方は、原則として就労選択支援を先に利用することが求められます。これにより、以下の影響が想定されます。
- 新規利用者の受け入れプロセスが変更
- 就労選択支援実施事業所との連携体制構築が必要
- 利用者の事業所選択がより慎重になる可能性
- ミスマッチの減少による利用者の定着率向上が期待
就労継続支援A型への影響
就労継続支援A型については、令和9年(2027年)4月1日から新規利用者に対して就労選択支援の先行利用が原則となります。B型より約1年半遅れての実施となり、この期間を活用して準備を進めることが重要です。
就労移行支援への影響
就労移行支援については、当面は就労選択支援の利用は任意とされています。しかし、より効果的な支援のため、以下の点に注意が必要です。
- 利用者がより適切な支援を受けられるよう、就労選択支援の活用を推奨
- 就労移行支援事業所も就労選択支援の実施を検討
- 既存利用者の支援計画見直し時における活用
事業所が就労選択支援導入で準備すべきこと
就労選択支援の実施を検討している事業所は、制度開始までに以下の準備を進める必要があります。計画的な準備により、スムーズな制度導入と質の高いサービス提供を実現できます。
指定申請の手続きと必要な実績
就労選択支援の指定申請には、以下の要件を満たす必要があります。
- 過去3年以内の就職実績:3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された実績の証明
- 既存の指定:就労移行支援又は就労継続支援の指定を受けていること
- 地域連携実績:自立支援協議会への参加、ハローワークとの連携実績
- 人員配置計画:就労選択支援員の配置計画(15:1以上)
職員研修と体制整備
質の高い就労選択支援を提供するため、以下の研修と体制整備が重要です。
- 就労選択支援員養成研修:必須の研修プログラムの受講
- アセスメント技法研修:客観的評価手法の習得
- 企業実習調整研修:企業との連携方法の習得
- 関係機関連携研修:ハローワーク、医療機関との効果的な連携方法
関係機関との連携体制構築
効果的な就労選択支援の実施には、以下の関係機関との連携体制が不可欠です。
- ハローワーク:求人情報の提供、就職活動支援、定期的な訪問による情報収集
- 地域の企業:実習受け入れ、雇用機会の提供
- 医療機関:利用者の健康状態、必要な配慮事項の確認
- 教育機関:特別支援学校等からの移行支援
- 相談支援事業所:利用者の総合的な支援計画との調整
- 自立支援協議会:定期的な参加による地域連携の強化
これらの準備を計画的に進めることで、2025年10月の制度開始に向けて万全な体制を整えることができます。また、既存の就労移行支援や就労継続支援と組み合わせることで、より包括的な就労支援サービスの提供も可能となります。
まとめ
就労選択支援は、障害のある方の就労定着率向上と適切なサービス選択を支援する重要な制度です。2025年10月からの本格実施に向けて、事業所は実施要件の確認、人員体制の整備、関係機関との連携体制構築など、様々な準備を進める必要があります。
特に、就労継続支援B型事業所にとっては、2025年10月以降の新規利用者受け入れに直接影響する重要な変更となります。過去3年以内の就職実績3人以上という要件や、就労選択支援員の配置基準など、具体的な準備事項を早めに確認し、対応を進めることが重要です。
新制度の導入は一時的な業務負荷増加をもたらす可能性がありますが、長期的には利用者のミスマッチ減少と定着率向上により、より安定した事業運営が期待できます。また、専門的なアセスメント能力を持つ事業所として、地域における競争優位性の確保にもつながるでしょう。
※障害福祉サービスの業務効率化を検討している方は、以下の記事で障害福祉ソフトの比較情報をご確認いただけます。
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する