スマート介護士とは?メリットや合格までの流れを徹底解説!
働きやすい職場の選び方
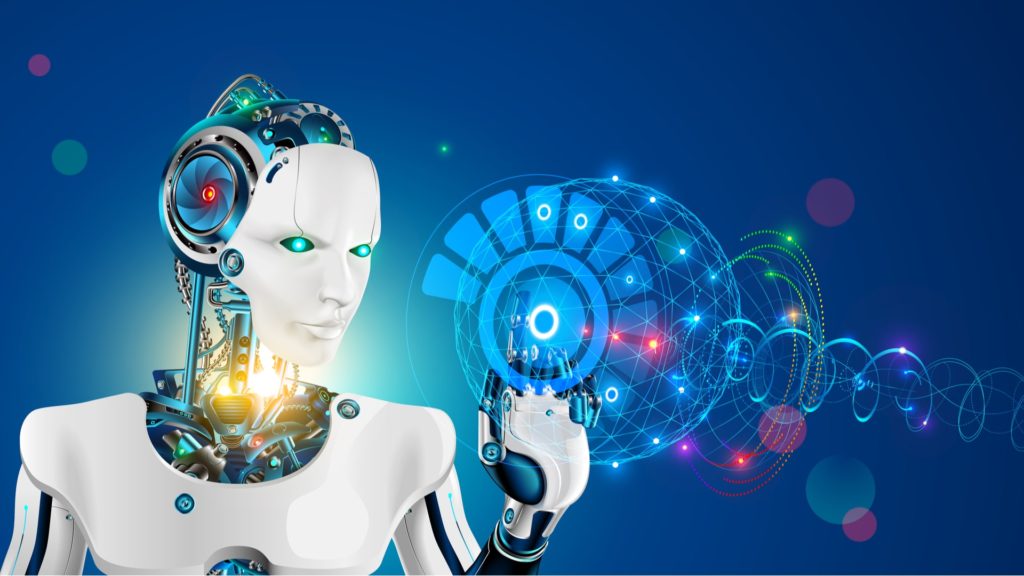
スマート介護士は、介護現場でロボットや情報通信技術(ICT)を活用して業務の効率化を目指す民間資格です。
本記事では、資格のメリットや取得方法、将来の展望について、実際にスマート介護士を受講した経験も参考にしながら、詳しく解説します。
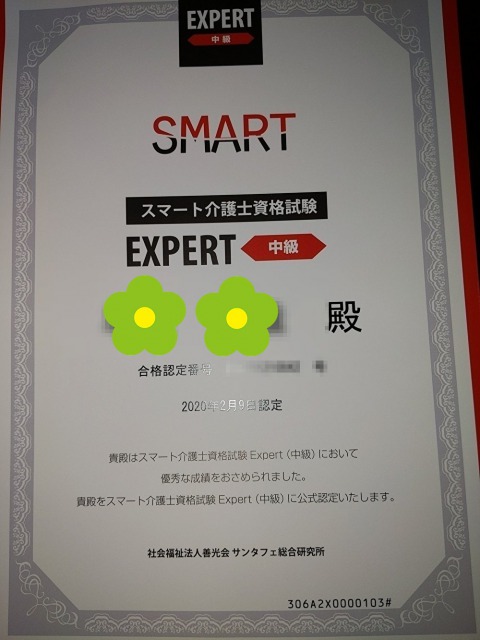
筆者プロフィール
大学卒業後、大手介護ソフトベンダーに7年間勤務。年間約50法人に介護ソフトを新規販売し、最年少で営業成績1位を獲得。課題抽出から業務改善に関するコンサルティング経験も多数。後に、「介護のテクノロジーを最適化する」という理念のもと(株)GiverLinkを設立し、同メディア「介護のコミミ」を通じ、月間10万人以上の介護職員に情報発信をしている。

スマート介護士Expertを2020年2月に取得しています!
介護業界で転職を考えているけど、転職先が自分に合った職場かわからない。
そんな方のために、独自の指標を用いて働きやすい職場の情報だけを集めた「介護のコミミいい職場検索」で、あなたに合った職場を探すことができます。
働きやすい職場が見つかる
近くのいい職場を探す
スマート介護士とは?
スマート介護士は、2019年に創設され、少子高齢化が進む日本において、慢性的な人材不足を補うために重要な役割を果たせると期待されています。
スマート介護士資格受験オンラインによると、以下の項目に当てはまる方の受講をおすすめしています。
- 介護DX・ICT・介護ロボットに興味がある人
- キャリアアップのために有望な資格を得たい人
- 現場のオペレーションを改善したい人
- LIFEや科学的介護などの最新情報を学びたい人
資格が生まれた背景と目的
日本は急速に少子高齢化が進んでおり、介護現場では慢性的な人材不足が深刻な問題となっています。
介護ロボットやセンサーの導入が進められているものの、これらの技術を十分に活用できていない施設が多いのが現状です。
厚生労働省が公表した「介護現場の生産性向上の推進/経営の協働化・大規模化」の、介護ロボット等の安全かつ有効活用するための委員会の設置有無別機器を導入したことによる利用者の行動等の変化の調査結果では、利用者の自立支援につながったと答えた割合は、46.3%でした。
こうした調査結果からも、介護ロボットは導入したものの技術を十分に活用できず、現場の課題が解決できていないと感じる事業所は多い背景が見えてきます。
狙いは介護ロボットとICTツールの普及
スマート介護士の資格は、介護ロボットやICTツールの普及を促進することを狙いとしており、介護の質と生産性を向上させることが期待されています。
スマート介護士は、介護ロボットの導入計画を立案し、現場の課題を分析して解決策を検討します。
また、他の職員に対してロボットの活用方法の研修を行い、業務全体の効率化を図る役割も担います。
国もデジタル⼈材の育成には注目している
国は、介護分野におけるKPIとして「デジタル中核人材育成数」を設定しています。
この計測は2023年に開始され、2029年までに10,000人のデジタル人材を育成することを目標としています。
さらに、2029年までに「ICT・介護ロボット等の導入事業者割合」を90%に達成することも目指しています。
この目標からも、国が介護分野におけるデジタル技術の普及と革新に本気で取り組んでいることが伺えます。
| 2023年 | 2026年 | 2029年 | 2040年 | |
| デジタル(中核)⼈材育成数 |
500名 |
5,000名 |
10,000名 |
– |
| ICT・介護ロボット等の導⼊事業者割合 |
29% |
50% |
90% |
90%以上 |
スマート介護士の取得メリット
スマート介護士を取得することで得られるメリットは多岐にわたります。
取得者個人にとってのメリットと、事業所にとってのメリットに分けて解説します。
取得者個人にとってのメリット
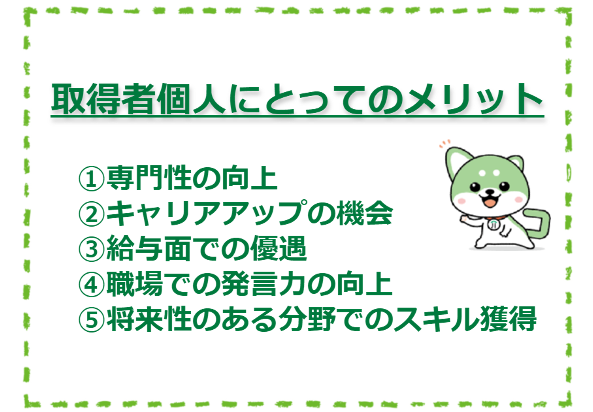
専門性の向上
介護ロボットやICTに関する深い知識と技能を習得することで、介護分野での専門性が高まります。
これにより、より高度な介護サービスの提供が可能になります。
キャリアアップの機会
スマート介護士の資格は、介護現場でのキャリアアップにつながる可能性があります。
例えば、介護ロボット導入プロジェクトのリーダーや、ICT活用の指導者としての役割を担うことができるかもしれません。
給与面での優遇
専門性の高い資格を持つことで、将来的に給与面での優遇を受けられる可能性があります。
今後、介護ロボットやICTの普及率が上がるにつれ、スマート介護士の資格に対して手当を支給するなどの、待遇改善を行うことで差別化を図る事業所も出てくるかもしれません。
職場での発言力の向上
ICTや介護ロボットに関する専門知識を持つことで、職場での発言力が高まりやすいです。
業務改善や新しい技術の導入に関して、重要な意見を述べる機会が増え、リーダーとしてキャリアの手助けともなるでしょう。
将来性のある分野でのスキル獲得
高齢化社会が進む中、介護分野でのICT活用は今後さらに重要性を増すと予想されます。
この分野でのスキルを早期に獲得することは、長期的なキャリア形成に有利に働くでしょう。
事業所にとってのメリット
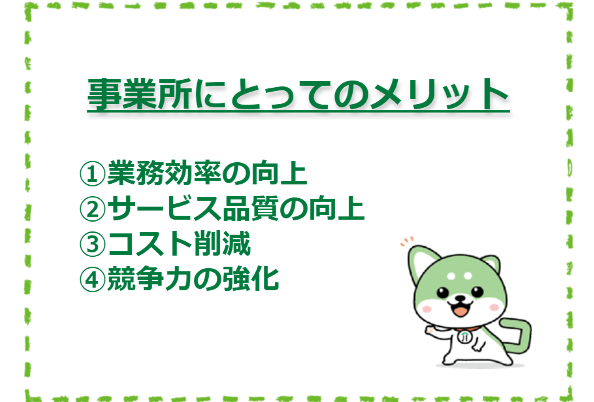
業務効率の向上
スマート介護士が介護ロボットやICTを効果的に活用することで、業務の効率化が図れます。
これにより、限られた人員でより質の高いサービスを提供することが可能になると考え、転職活動でも有利に働きやすいです。
サービス品質の向上
ICTや介護ロボットを適切に活用することで、より正確で安全な介護サービスの提供が可能になります。
これはここに利用者満足度の向上にもつながります。
コスト削減
業務の効率化により、長期的には人件費や運営コストの削減が期待できます。
また、ICT活用による記録の電子化などで、事務作業の負担も軽減されます。
競争力の強化
先進的な技術を導入し、効率的な運営を行う事業所は、競争力の強化につながります。
これは新規利用者の獲得や、優秀な人材の確保にも有利に働くでしょう。
スマート介護士の資格取得は、個人のキャリアアップと同時に、事業所の運営効率やサービス品質の向上にも大きく寄与します!
スマート介護士の資格コース
スマート介護士の資格コースは、Basic、Expert、Basic / Expert 併願の3つのコースがあり、それぞれの目標や経験に合わせて選択できます。
介護ロボットやICTツールの基礎から高度な活用まで、段階的に学べる構成となっています。
スマート介護士Basic
スマート介護士Basicは、介護ロボットやICTツールに興味がある方や、介護の基礎知識を学びたい方に最適なコースです。
- 試験形式:60分の選択式問題+記述式問題
- 受験料:6,800円(税込)
学習内容には、介護ロボットの基礎知識や活用方法、介護現場でのICT活用などが含まれます。
公式テキストを活用することで、効率的に学習を進められます。
スマート介護士Expert (中級)
スマート介護士Expertは、介護現場のオペレーションを分析・改善し、新しい技術を現場に浸透させる能力を養成します。
ユニットリーダーや施設長を目指す現役介護福祉士の方々にもおすすめです。
- 試験形式:60分の選択式問題+記述式問題(Basicより難易度が高い)
- 受験料:8,800円(税込)
Expertでは、介護ロボットやICTツールの導入計画立案、現場課題の分析と改善策の提案など、より実践的なスキルを習得します。
Basic / Expert 併願
Basic / Expert 併願は、2つの資格の受講が可能で、料金は13,860円(税込)です。
スマート介護士で過去に出題された問題例
本章では、Basic(初級)とExpert(中級)の過去問を、スマート介護士で紹介されている過去問題を参考に、ご紹介していきます。
スマート介護士Basic (初級)の過去問
介護における生産性と質の向上に関して、最も適切に説明しているものを選びなさい 。
①人員配置比率を高めることは至上命題であり、ある程度のサービス品質低下はやむを得ない
②利用者の自立支援に向けたサービス品質の向上が目的である
③利用者のQOLを高めるためには介護職員の人数を増やすことが必要である
④アウトプットとなる介護サービスの提供量を増やし、インプットとなる業務時間を減らすことが必要である
スマート介護士Expert (中級)の過去問
介護ソフトに関する以下の記述ついて、誤っているものを選択しなさい。
①介護ソフトは、利用者とその家族の要配慮個人情報の厳格な管理を目的に、クラウド化が原則禁止されている
②一気通貫型の介護ソフトは、国民健康保険団体連合会(国保連)への介護保険請求(伝送)機能に加えて「介護記録作成」「利用者情報の管理」といった機能が備わっている
③機能特化型の介護ソフトは、「伝送機能」「介護記録作成」「利用者情報の管理」等の機能に絞りこむことで利便性を高めている
④介護ソフトの導入は、「介護ソフトありき」ではなく「自分達の解決したい課題は何か」から検討をはじめることが重要である
参照元:スマート介護士資格受験オンライン
合格率は発表されていませんが、現場経験がある方は特に取得難易度は下がりやすいです!
スマート介護士の勉強方法は「公式テキスト」
スマート介護士資格 公式テキスト
公式テキストとしては、「三訂版 スマート介護士資格 公式テキスト」が当てはまります。
このテキストは、Basic(初級)とExpert(中級)の両方に対応しており、介護ICTや科学的介護についての最新情報が盛り込まれています。
テキストの主な内容は次の通りです。
- スマート介護士概論
- ケアテック基礎論
- 科学的介護基礎論
- ケアテック導入の実践理論
- 科学的介護の実践理論
この公式テキストは、介護現場でのデジタル技術活用に関する数少ない良書として評価されています。
また、模擬試験問題集も用意されているので、実践的な対策を立てることができます。
受験までの流れ
スマート介護士の受験までの流れは以下のとおりです。
- 受験申し込み: スマート介護士公式ページにアクセスし、受験の申し込みを行います。
- 受験料の支払い: 受験料をクレジットカードまたはコンビニ決済で支払います。
- 動作確認テスト: 試験はオンラインで実施されるため、使用予定のパソコンで動作確認テストを行います。
- 身分証明書の準備: 試験当日に本人確認を行うため、身分証明書のアップロードが必須となります。
- 試験受験: 指定された日時にオンラインで試験を受験します。
介護ロボットやICTに興味がある方はぜひ挑戦してみてください。
最後に
スマート介護士は、介護現場でロボットやICTを活用し、業務の効率化を目指す資格です。
高齢化社会が進む中、スマート介護士の需要はますます拡大すると予想されています。
今こそ、その一歩を踏み出す絶好のタイミングです。
これを機に、介護現場の革新に貢献できるスマート介護士資格にぜひチャレンジしてみてください!
介護業界で転職を考えているけど、転職先が自分に合った職場かわからない。
そんな方のために、独自の指標を用いて働きやすい職場の情報だけを集めた「介護のコミミいい職場検索」で、あなたに合った職場を探すことができます。
働きやすい職場が見つかる
近くのいい職場を探す
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する









