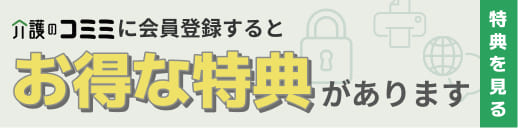介護現場のアセスメントとは?目的・流れ・実施方法を解説
介護施設の経営・運営改善


アセスメントってなんだろう?
どのように進めていけばいいのだろう?
このような疑問にお答えしていきます。
ケアマネージャーが行うアセスメントは、ケアプランの作成に欠かせないものです。
アセスメントの経験が少ない場合には、苦手意識を持ってしまうことも少なくありません。
そんなときには、アセスメントをより理解できるように、本来の目的や詳しい方法を再認識することをおすすめします。
この記事では、アセスメントの実施方法やポイント、アセスメントシートの作成方法などを解説します。
利用者が適切な介護サービスを受けられるよう、記事を参考にアセスメントしていきましょう。
ケアプランについて詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしていただけると幸いです。
関連記事 :ケアプランとは?介護サービス計画書作成後の流れまで解説
介護ソフトを導入したいけど、どれがいいのかわからない、、、。
そんな方はまずは口コミランキングで人気の介護ソフトを見てみましょう!
掲載数100件、総口コミ数800件以上の口コミランキングで本当に人気の介護ソフトがわかります!
気になる製品あれば無料で資料請求も可能!
総口コミ件数800件以上!
口コミランキングを見る
介護におけるアセスメントとは

アセスメントとは「評価・査定」という意味で、介護におけるアセスメントは利用者の情報を集めて分析し課題解決を明らかにするものです。
個々の利用者に適した介護サービスを提供するための「ケアプラン」を作成する際に行われます。
アセスメントする際には、目的を再認識しながら現状を正しく把握してアセスメントシートに記載することが大切です。
ここでは、アセスメントの目的、アセスメントシートの種類について詳しく解説します。
アセスメントの目的
アセスメントは、ケアプランを作成する過程で実施される利用者への調査です。
アセスメントの目的は、利用者や家族が抱える課題や目標などを明確にしてケアプランに記載し、利用者に合った介護サービスを提供することにあります。
ケアマネージャーがアセスメントをしっかり行う必要があるのは、利用者に対するケア全体の質をより向上させるためです。
アセスメントは基本的に介護サービスを提供する前の段階に行います。そのため、利用者のニーズや利用しているサービス、生活面の課題などの現状を把握することが大切です。
また、利用者本人だけでなく家族や交友関係、住まいや地域の環境などの状況についても情報を集めると、より正確なアセスメントになるでしょう。
アセスメントシートの種類
アセスメントを実施して集めた利用者の情報は、アセスメントシートに項目別に記載して活用します。
アセスメントシートには7種類の様式があるので、それぞれの特徴を知ってから必要に応じて使い分けましょう。
包括的自立支援プログラム
全国老人福祉施設協議会、全国老人保健施設協会、介護力強化病院連絡協議会によって開発されました。
使われているのは主に介護施設で、老人福祉施設では半数ほどが利用しています。
認定調査と連携しているため、要介護認定後には適切な介護サービスが可能になるのが特徴です。
居宅サービス計画ガイドライン
全国社会福祉協議会が開発しました。居宅介護支援事業所で多く採用され、利用者が持つ力を引き出すためのエンパワメントも行われます。
MDS-HC方式
施設・居宅のどちらにも使える様式です。在宅での介護サービスと施設の両方を利用しているケースに向いています。
R4
公益社団法人全国老人保健施設協会が開発しました。
介護老人保健施設向けのケアマネジメントシステム「R4」に対応しています。
ケアマネジメント実践記録方式
調査結果の分析項目が広く細やかなのが特徴です。
多くの時間を費やしますが、ニーズを詳しく把握できます。
日本介護福祉会方式
7つの領域に分けて調査結果を分析します。
領域は、衣・食・住・体の健康・心の健康・家族関係・社会関係と広範囲の情報が得られるため、利用者の現状を詳しく把握することが可能です。
日本訪問介護振興財団版方式
1回のアセスメントで終わらずに何度も記載できるのが特徴です。
そのため、これまでに実施されたアセスメントの内容も知ることができます。成人全般が活用できる様式です。
アセスメントシートに記載する内容

アセスメントシートには課題分析標準項目があり、内容によって大きく2つに分けられています。
「基本情報に関する項目」に記載するのは、利用者の氏名や住所などの個人情報のほかに、生活状況や介護保険、医療保険の情報です。
「課題分析(アセスメント)に関する項目」では、さらに詳しい情報を得るために、利用者の健康状態や認知機能、既往症などを記載します。
利用者のニーズに合った介護サービスを提供するために大切な項目です。
基本情報に関する項目
基本情報に関する項目は、大きく9つの分野に分けられています。
基本情報(受付、利用者等基本情報)
受付年月日、受付対応者や事業所名、受付方法や相談方法について記載する項目があります。
また、利用者本人の氏名や性別、年齢、住所などの基本情報のほか、家族状況の項目として利用者以外の家族などの基本情報も記載する項目があるのが特徴です。
生活状況
利用者の現在の生活状況、生活歴などについて記載する項目があります。
利用者の被保険者情報
利用者の被保険者情報として、介護保険や医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無などについて記載します。
現在利用しているサービスの状況
介護保険給付の対象か、対象外なのかにかかわらず利用者が現在受けているサービスの状況を記載します。
障害老人の日常生活自立度
障害のある高齢者の日常生活自立度について記載する項目です。
認知症である老人の日常生活自立度
認知症の高齢者について日常生活自立度を記載します。
主訴
利用者や家族の主訴や要望について記載する項目です。
認定情報
要介護状態区分や支給限度額など、利用者に対する認定結果について記載する項目です。
課題分析(アセスメント)理由
アセスメントを実施する理由について記載する項目です。初回・定期・退院退所時などの理由を記載します。
課題分析(アセスメント)に関する項目
課題分析(アセスメント)に関する項目の内容は、さらに次のような項目に分類されています。項目ごとの内容を確認しておきましょう。
健康状態
利用者の既往症や病気などの症状、痛みの状態について記載する項目です。
ADL
日常生活動作のことで、寝返りや起きあがり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄などの項目です。
IADL
ADLよりも高度な手段を使う日常生活動作で、調理や掃除、買物、金銭管理、服薬状況などの項目です。
認知
日常生活で利用者が意思決定するための認知能力について記載します。
コミュニケーション能力
他者への意思の伝達のほか、視力や聴力などを含むコミュニケーション能力の項目です。
社会との関わり
社会的活動への参加に対する意欲、社会との関わりの変化、喪失感、孤独感などを記載する項目です。
排尿・排便
失禁する場合はその状況、排尿など排泄後の後始末やコントロール方法、頻度などについて記載します。
じょく瘡、皮膚の問題
褥瘡があるときにはじょく瘡の程度、皮膚の清潔状況などについて記載します。
口腔衛生
歯や口腔内の状態や口腔衛生に関する項目です。
食事摂取
利用者の栄養の摂取状況や食事の回数、水分量などを記載します。
問題行動
暴言暴行や徘徊、介護への抵抗、収集癖、火の不始末、不潔行為、異食行動などの問題とされる行動がある場合に記載する項目です。
介護力
利用者の介護力について記載する項目で、介護者の有無、介護者に介護する意思はあるか、介護者の介護負担についてなど、主な介護者に関する情報を記載します。
居住環境
利用者の住まいについて、現状で住宅改修の必要性はあるか、危険個所の確認など、現在の居住環境について記載する項目です。
特別な状況
虐待などが疑われるケースや、終末期でターミナルケアを必要とするケースなど、特別な状況とされる内容を記載する項目です。
参考:一般社団法人 日本介護支援専門員協会「課題分析標準項目 項目の主な内容(例)」
アセスメントに大事な5つのポイント

ここでは、アセスメントする際に大切なポイントを解説します。
次に挙げる5つのポイントを確認してから、アセスメントを実施することが大切です。
・事前に情報を収集し専門職と連携を取る
・現状の問題、原因、リスク、対策を明確にする
・利用者がやりたくないこと、拒否していることを知る
・利用者・家族が目指す理想の姿を知る
・アセスメントシートは簡潔に誰が見てもわかる内容で書く
それぞれがどうしてアセスメントにおいて大切なのか、詳しく解説します。
事前に情報を収集し専門職と連携を取る
アセスメントは、実施前に利用者の情報を集めておくことで状況をより正確に把握できます。
事前の情報なしで利用者宅を訪問する場合、利用者から得られる情報が少なくなる可能性もあります。
ケアマネージャーが事前情報で利用者について理解しておくほうが会話の糸口をつかめるため、より多くの情報収集が可能になるでしょう。
利用者には、家族や通院している病院の医師や看護師、地域包括支援センターなど、多くの人や専門職が関係しています。
ADLやIADLを正確に把握するためには、理学療法士や作業療法士などリハビリの専門職からの情報収集も必要です。
アセスメントを実施する前に、利用者の関係者から詳しい情報を集めておくと、利用者への理解も深まり、その後の流れもよりスムーズに進むでしょう。
現状の問題、原因、リスク、対策を明確にする
介護のアセスメントでは、マネージャーが初めに利用者が抱える現状の課題を明確にしておくのがポイントです。
利用者が今の生活で困っていることや、生活に支障のあるものは何かを詳しく把握します。
より現状の課題を的確に把握するには、問題ごとに細かく分けてから具体的にチェックするといいでしょう。
たとえば、利用者が動作に支障がある場合なら、支障がでたときの状況について明らかにしていきます。
ふらついて転んでしまったのなら、転んだのはいつか、そのときの状況はどのようだったかなど、細かい情報を聴き取るのがポイントです。
現状の課題をしっかり把握できれば原因を特定しやすくなるため、リスクを洗い出して対策を講じることもできます。
利用者がやりたくないこと、拒否していることを知る
より良いアセスメントを実施するには、利用者がやりたくないことや拒否していることを知るのもポイントです。
介護サービスの利用者のなかには、特定の生活習慣やサービスを拒否する人もいます。
理由は人によって異なるため、アセスメントで本人から理由をじっくり聴き取ることが大切です。
たとえば、入浴を嫌がる利用者の理由が「恥ずかしい」のであれば、同性の入浴介助にするといった対策を取ることもできます。
また、認知機能低下による生活習慣の拒否の場合、着替えを嫌がるなどのケースも多くあります。
この場合も無理に着替えをさせると不安が増してしまうため「衣類を洗濯する」など、利用者が納得できるような声掛けが必要です。
利用者がいやがる理由を知れば、不安をなくすための対策が見つかるでしょう。
利用者・家族が目指す理想の姿を知る
アセスメントは、ケアマネージャーが必要と判断した内容だけで良いというものではありません。
一方的な判断にならないように十分注意する必要があります。
それには「利用者や家族が目指している理想は何か」を汲み取ってから、必要な介護サービスを選択するのがポイントです。
アセスメントで利用者本人や家族が求めているニーズをしっかり聴き取るなら、アセスメントをもとに作成したケアプランによって適切な介護サービスが提供できます。
ケアマネージャーが一方的に介護サービスを提案するのではなく、利用者や家族とともにより良い方法を模索していく姿勢が必要です。
そのためにも、利用者を取り巻く状況全体に目を向けてアセスメントを実施していきましょう。
アセスメントシートは簡潔に誰が見てもわかる内容で書く
利用者からの聴き取りをもとに作成するアセスメントシートは、簡潔に誰が見てもわかりやすいように書くのがポイントです。
聴き取った内容をそのまま書くのではなく、具体的な利用者のニーズや課題、解決策などを簡潔、かつ明確に記載します。
「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」の5W1Hも意識して書くようにすると、アセスメントシートの内容が明確に伝わるようになるでしょう。
その際に、ケアマネージャーが感じた点を記載してしまうと主観が入ってしまうので、客観性を保つことも重要です。
アセスメントシートには、最終的な目標は何か、目標を達成するために必要なことは何かを明確に記載します。
また、やりたくないことや拒否していること、利用者が自分でできる範囲などは、より具体的に書くと伝わりやすくなるでしょう。
参考:あずみ苑「アセスメントのポイントと「アセスメントシート」の書き方」
アセスメントの対応も介護ソフトで効率化!

ケアマネージャーが記載する項目の多いアセスメントの対応には、介護ソフトを活用する方法が有効です。
高齢化が進む昨今、介護業界はますます多忙になっていくと予想されています。
アセスメントの際には適切な介護ソフトを利用して業務の負担軽減を目指しましょう。
たとえば、介護ソフトにはアセスメントの内容をその場で簡単に記録できる機能もあります。
アセスメント後には情報の共有が簡単になるので、専門職間の連携もスムーズになるのもメリットです。
介護ソフトにはさまざまな製品があるので、資料請求を一括で行えるサービス「介護のコミミ」をおすすめします。
介護のコミミでは、介護ソフトの活用で事務作業を簡素化し本来のケア業務に集中できる環境を推進しています。
無料で100以上の介護ソフトから、ニーズに合うものを簡単に選べる介護のコミミを利用しましょう。
まとめ

アセスメント後に記入するアセスメントシートには、細かい項目が多数あります。
ケアマネージャーの業務を簡素化するには介護ソフトの活用がおすすめです。
業務改善を目指すことで、本来の目的である利用者のケアに集中できるメリットが得られます。
ただし、介護ソフトには多くの種類があるので選ぶだけでも時間がかかります。
介護のコミミの資料請求・体験版申し込みなら、簡単に多くの介護ソフトから適切なものを選ぶことが可能です。
ニーズに合った介護ソフトを活用すれば、経験が浅くても安心してアセスメントに集中できるでしょう。
![]() 【介護ソフト】シェア比較ランキング10選!大手分析、比較検討
【介護ソフト】シェア比較ランキング10選!大手分析、比較検討
介護ソフトを導入したいけど、どれがいいのかわからない、、、。
そんな方はまずは口コミランキングで人気の介護ソフトを見てみましょう!
掲載数100件、総口コミ数800件以上の口コミランキングで本当に人気の介護ソフトがわかります!
気になる製品あれば無料で資料請求も可能!
総口コミ件数800件以上!
口コミランキングを見る
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する