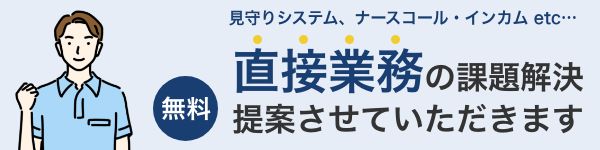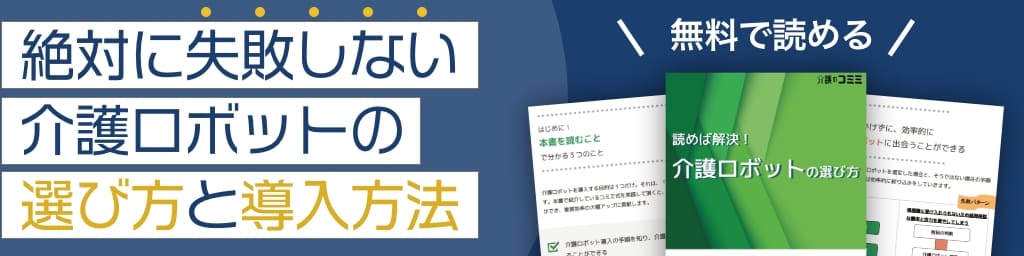AI搭載型の介護ロボットとは?導入から運用まで徹底解説
介護ロボット・センサーの選び方


AI機能がある介護ロボットって通常の介護ロボットと比べて何が違うのかな?
導入の実例などはある?
このように、AI搭載型と通常の介護ロボットではどのような違いがあるのか、詳しく知りたいという人もいらっしゃるでしょう。
介護ロボットを施設に導入すれば、介護スタッフの様々な業務負担を軽減できます。
実際に、AI搭載型を導入したことで、入居者の見守りや物品の運搬などの業務負担軽減に成功した施設もあります。
介護スタッフの負担を減らし、業務効率や生産性の向上を図りたい場合は、ぜひ最後までご覧ください。
本記事では、AI搭載型の特徴や導入するメリット、成功事例などがわかるため、AI搭載型の導入を検討する判断材料にできるでしょう。
介護の現場の人材不足や負担軽減など様々なメリットがある介護ロボット!
しかし導入コストも高いためなかなか導入に踏み切れない方も多くいます。
介護のコミミの「介護ロボットの選び方」を参考にすれば失敗しない導入が可能です!
介護ロボットの選定方法や事例を紹介しているので、導入を検討されている方はまずは無料でダウンロードから!
ロボット選びで失敗しない!
介護ロボットの選び方を知る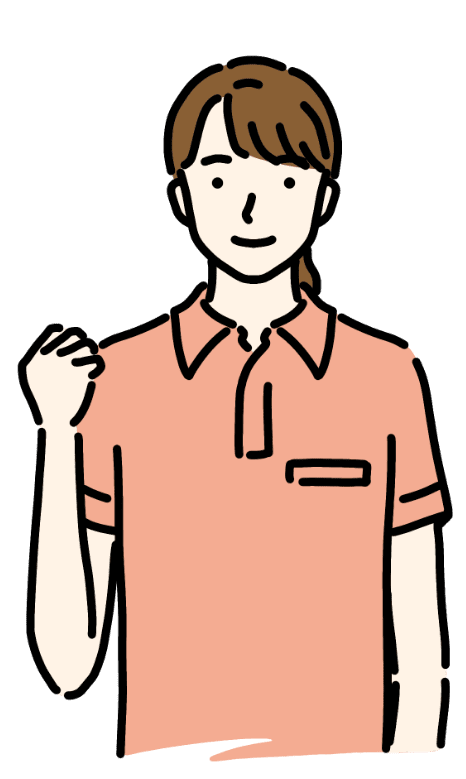
AI搭載型の介護ロボットとは
介護ロボットとは、介助動作の負担軽減や、介護が必要な人の自立支援などの目的で開発されたロボットです。
厚生労働省では、介護ロボットを6つの分野に分類しており、そこからさらに13項目に分けています。
たとえば、移乗介助の分野には、介護者が装着するタイプの介護ロボットと、ベッドなどに設置して介護が必要な人を抱きかかえる動作をサポートする非装着型のタイプが開発されています。
このように介護ロボットにはさまざまな用途や目的に合わせた種類があり、その中の一つが、AI搭載型の介護ロボットです。
一般的な介護ロボットでは、プログラムされた動作しかできませんが、AI搭載型の介護ロボットは取得したデータや情報を読み取って学習できるため、人や状況に合った対応が取れます。
また、介護が必要な人に寄り添った見守りや声かけを行うことも可能です。
AI搭載型介護ロボットにできること・メリット
AI搭載型の介護ロボットが介護現場で行える動作には、以下のようなものが挙げられます。
・顔や体格から人物を特定し、音声による挨拶を行う
・転倒等を検知し、スタッフへ発信する
・目的物を取得・保持し、エレベーターを利用した移動を行う
顔認識などの技術を用いることで、あらかじめ登録された入居者の顔や体格から人物の特定ができる上に、挨拶などの声かけも行えます。また、自動巡回中に転倒している入居者を検知すると、迅速に介護スタッフへ知らせてくれます。
さらに、特定のモノの情報を取得することで物品を運搬する、付き添いがいなくてもエレベーターの乗り降りができるなどの動作も可能です。
顔や体格を検知し、音声による挨拶を行う
AI搭載型の介護ロボットは、顔や体格などのデータを学習させることで、人物の検知や特定できます。
介護ロボットの種類によって、正面から顔がしっかりと認識できる場合に人物を特定するタイプもあれば、背面からでも体格などから人物を特定できるタイプもあります。
また、入居者と対面したときは、「○○さん、こんにちは」「お元気ですか」などの音声による挨拶や声かけなどの動作も可能です。
コミュニケーション機能が搭載されている介護ロボットは、顔やアームなどがある人型のタイプが多い傾向にあります。
人に似た見た目が親しみやすく、入居者の心の拠り所として活用できます。
転倒等を検知し、スタッフへ発信する
AI搭載型の介護ロボットは、物体検知や生体信号検知などの機能が搭載されている介護ロボットです。
転倒や発作を起こしている入居者を認識できるため、転倒者などを発見すると介護スタッフへ迅速に情報を発信してくれます。
介護スタッフは、介護ロボットから受信した画像などの情報をもとに、現場へ直行できるようになります。
介護ロボットに施設内の巡回を任せられるため、介護スタッフが訪室する頻度を減らせる上に、他の業務に集中できる環境を整えられるでしょう。
また、介護スタッフの訪室の頻度が減少すれば、入居者は度々受け答えをしなくて済むため、介護スタッフの訪室によるストレスの軽減にもつなげられます。
目的物を取得・保持し、エレベーターを利用した移動を行う
AI搭載型の介護ロボットには、車の自動運転技術にも利用されている「LiDAR」などの技術が採用されており、自力での移動や物品の運搬などの動作も可能です。
あらかじめ走行ルートなどを作成しておけば、走行ルートをもとに自立走行できます。
物体認識機能と組み合わせて活用すれば、エレベーターのボタンを押して乗り降りして指定の場所へ行き、特定の物品の運搬作業もこなせます。
また、アームの活用により、スライドドアなどの開閉も自力で行えるほか、障害物なども認識して避けられるため、介護スタッフが介護ロボットに付き添う必要がありません。
リネンや消耗品などの補充が必要になった場合など、介護ロボットに指示を出せば必要な物品を迅速に運んでくれます。
AI搭載型介護ロボットのデメリット
AIが搭載されている介護ロボットを導入するメリットは多いですが、その反面懸念すべきデメリットも存在します。
AI搭載型介護ロボットの理解を深めるためには、メリットだけでなくデメリットも把握しておくことが大切です。
そこで、ここからは以下のAI搭載型介護ロボットのデメリット2つを解説していきます。
- AIが判断を間違えたとき、責任の所在の決定が難しい
- 根拠の追及が難しい
AIが判断を間違えたとき、責任の所在の決定が難しい
AIを搭載した商品を導入して、それを利用し、ミスが起きることもあります。
その場合、責任の所在の判断が難しいというのが現状です。
例えば、購入した商品のAIが判断ミスをした場合、その責任の所在が商品販売者側なのか、購入者側なのかはっきりさせるのが難しい面があります。
現在の法律がAIの進化に追いついておらず、はっきりしていないことが原因です。
ミスや事故が起きたとき、責任の所在が不明確で不安という声がときどき聞かれるのも事実です。
根拠の追及が難しい
AIが導き出した結果に対しての根拠が理解できない可能性があるという点も、懸念されています。
特にエビデンスが重要となる医療現場では、導き出した結論の根拠を把握することは必須であるからです。
AIの考え方が理解できない場合、人の命を扱う医療現場では判断を任せることができなくなります。
ブラックボックスとなっているAIの思考回路を、人間が理解できないという点も懸念されるデメリットです。
AI搭載型介護ロボットの導入事例
ある介護老人保健施設では、コミュニケーション支援の分野に該当するAI搭載型のコミュニケーションロボットを導入しました。
この施設では、レクリエーションの準備に時間がかかり、休憩が取りづらい、入居者との個別のコミュニケーションを取る時間が少ないなどの課題がありました。
課題解決のために導入されたのがコミュニケーションロボットです。
介護ロボットは食堂に設置し、レクリエーションを行う、入居者に声かけをする、などの役割を担っています。
導入後、介護スタッフはレクリエーションの準備にかけていた時間を削減でき、入居者との個別のコミュニケーションの時間が取れるようになりました。
入居者の認知症・うつ予防につながる効果が期待できる反面、複数人から同時に話しかけられた場合は会話が難しい点が今後の課題とされています。
AI搭載型以外の介護ロボットの詳しい導入事例や導入の流れを知りたい人は、以下のページを参考にご覧ください。
参考:厚生労働省「介護ロボット導入活用事例集」
AI搭載型の介護ロボット導入後の課題
AI搭載型の介護ロボットを導入した場合、いくつか考慮しなければならない課題があります。
導入後の課題として、以下の3点が挙げられます。
・スタッフとの連携や効率的な協働体制
・患者さんのアフターケア
・介護ロボットのメンテナンス
まずは、介護スタッフと介護ロボット間でスムーズに連携が取れなければ、業務負担を軽減できません。
また、介護ロボットの導入にあたり、入居者のアフターケアをどのように行うのかを考慮する必要があります。
さらに、介護ロボットは機械である以上、導入後に定期的なメンテナンスが必要です。
それに伴う知識やトラブル時の対応、費用の負担なども踏まえた上で、導入を検討することが重要です。
スタッフとの連携や効率的な協働体制
介護ロボットを導入しても、介護スタッフとの連携がうまくいかなければ業務効率を上げるどころか、負担を増やすだけでなく介護サービスの質を落とす可能性があります。
また、介護スタッフの中に、「ロボットでは愛情のある介護やコミュニケーションは取れない」といった認識を持つ人がいる場合は、介護ロボットの適用範囲や導入によるメリットなどを導入前に理解してもらう必要があるでしょう。
介護ロボットの導入効果を得るためには、介護スタッフが介護ロボットの特性をしっかりと理解した上で、正しく活用していくことが求められます。
介護ロボットの見学や体験が可能な展示会などが定期的に開催されているほか、介護施設への貸し出しなどを行っているケースもあるため、実際に体験してみてから導入を検討することをおすすめします。
患者さんのアフターケア
介護ロボットを導入する際は、介護スタッフや施設関係者だけでなく、ロボットと直接触れ合う入居者からの理解を得る必要があります。
導入事例で紹介したコミュニケーションロボットを導入する場合、入居者の中にロボットの存在を不安に感じたり、どのように接すればいいのかがわからず困惑したりする人もいるでしょう。
介護ロボットの存在に慣れてもらうためにも、介護スタッフが積極的に介護ロボットをスタッフの一員として認め、入居者が介護ロボットに親近感を抱けるような接し方や、対応の仕方を検討しておくことも重要です。
AI搭載型の介護ロボットを導入する前に、どのような課題があるのかを想定し、解決につながる介護ロボットを選定するようにしましょう。
介護ロボットのメンテナンス
介護ロボットは機械であるため、定期的なメンテナンスや保守管理が必要です。
不具合や故障などが起きた場合はメーカーに問い合わせをする、エラーコードが表示された場合にマニュアルなどを確認するなどの作業に、介護ロボットに人員を割かれてしまいます。
また、保証期間を過ぎればメンテナンスや修理などに費用が発生するため、導入コストだけでなく、介護ロボットの導入後にかかるランニングコストなどの費用も考慮しておかなければなりません。
介護ロボットは、AIやICTシステムと組み合わせて利用するケースも多いことから、介護スタッフのITリテラシーや情報セキュリティなどの向上を図るための研修などの実施も必要です。
AI搭載型の介護ロボットの将来
AIの進化が、今後の介護業界の助けになる可能性は高いです。
現在の介護業界はさまざまな課題を抱えています。
特に、人手不足により、以下のようなことに悩む事業者は多いです。
- 介護士の疲労
- 2人介助の実施ができない
- 見守り不足
- コミュニケーション不足
上記のような介護ケア不足の悩みを解消してくれるのが、AI搭載型介護ロボットです。
今後進化していけば、ますます介護施設・事業所を助けられる存在となるでしょう。
また、AI搭載型介護ロボットの普及により、介護職員の仕事がなくなるのではないかと懸念している声も時々聞かれます。
結論から申し上げますと、その心配はありません。
介護の仕事は、「人」が相手であり、AIだけではまかないきれない部分があるからです。
AIをうまく使いながら、介護職員の負担を減らした仕事ができるようになるでしょう。
まとめ
AI搭載型の介護ロボットを導入すれば、介護スタッフの業務負担の軽減だけでなく、入居者の認知症・うつ予防の効果なども期待できます。
たとえば、レクリエーションをコミュニケーションロボットに任せられれば、空いた時間を別の業務や入居者との個別のコミュニケーションを取る時間に充てることも可能です。
ただし、上述した課題でも挙げたように、スタッフとの連携や介護ロボットのメンテナンスなどの課題もあるため、現場に合った介護ロボットを導入するようにしましょう。
介護のコミミでは、介護ロボットに関して詳しく解説した記事がありますので、介護ロボット導入検討している方は是非参考にしていただけると幸いです。
関連記事 :【介護ロボット】6種類に分けて徹底解説!課題や評判
関連記事 :介護ロボットはなぜ必要?注目される理由と導入メリット、今後の課題を解説
![]() 【介護ソフト】シェア比較ランキング10選!大手分析、比較検討
【介護ソフト】シェア比較ランキング10選!大手分析、比較検討
介護の現場の人材不足や負担軽減など様々なメリットがある介護ロボット!
しかし導入コストも高いためなかなか導入に踏み切れない方も多くいます。
介護のコミミの「介護ロボットの選び方」を参考にすれば失敗しない導入が可能です!
介護ロボットの選定方法や事例を紹介しているので、導入を検討されている方はまずは無料でダウンロードから!
ロボット選びで失敗しない!
介護ロボットの選び方を知る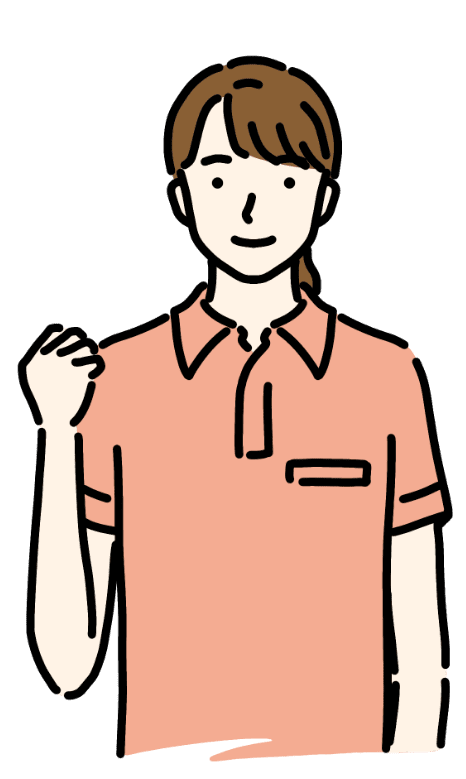
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する