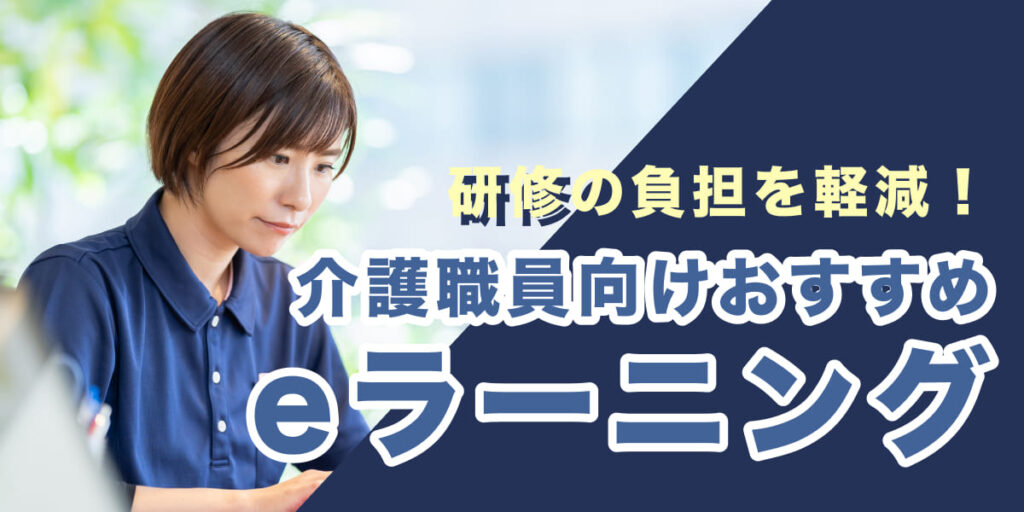【2025年義務化】介護BCP研修は何から始める?効率的な進め方と失敗しない方法
介護施設の経営・運営改善介護現場の声・悩み

介護事業所におけるBCP(業務継続計画)策定と研修の義務化が、2024年4月から本格施行されました。しかし、多くの現場では、「忙しくて研修の準備に手が回らない「手間をかけずに効率的な研修を実施したい」という切実な悩みを抱えているのではないでしょうか?
そこで、この記事では「介護BCP研修」の基本から、最新の公式資料・効率化ノウハウ・すぐ使えるテンプレートまで、実践に役立つ情報を網羅的にまとめました。
この記事を読むことで、あなたの事業所でも
- スムーズにBCP研修を実施できる
- 職員に効果的にBCPを周知できる
- 義務化対応に自信を持って臨める
ようになります。
BCPの研修をしなければいけないと分かっていながら、どうすれば良いか分からずなかなか動け出せていなかった方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事の筆者の伊藤です。2025年の完全義務化以降、介護のコミミでもBCP研修に関する反響がとても多いので、この記事を通じて少しでもお役に立てればと思います。
「記事を読むより、一刻も早く研修の負担を減らしたい」
「記事を読んでも、次に何をしたら良いかがわからない」
そんな方には、複数の研修サービスの一括資料請求して、無料体験から始めてみることをおすすめします。
研修の負担軽減に成功している事業所のほとんどは資料請求から始めています。
最短60秒!無料でできる
介護研修サービスの一括資料請求をする
1. 介護におけるBCPとは?いつから研修は義務化された?
BCP(業務継続計画)とは、地震・台風・水害といった自然災害や、インフルエンザ・新型コロナウイルスなどの感染症拡大時にも、介護サービスを中断せずに継続できる体制を整えるための計画のことです。
特に介護事業所では、緊急時において
- 利用者の生命・安全を守ること
- 必要最低限のサービスを維持すること
が強く求められます。
上記の目的を達成するために、BCPとして計画を策定し、職員に周知・研修を行うことが求められています。
BCPの策定と研修が義務化された背景
近年、自然災害や感染症といった緊急事態に備えるため、介護事業所にも業務継続計画(BCP)の策定と職員への周知・研修が求められるようになりました
特に、厚生労働省の通知により、2024年4月からBCPの策定と研修が義務化されたことで、すべての介護事業所にとって「BCP対応」は避けて通れないテーマとなっています。訪問系サービスなど一部で認められていた経過措置も令和7年3月31日で終了したため、2025年4月からは全ての事業所が待ったなしでBCP対応している必要があります。
これにより、
- 自然災害(地震・水害など)への備え
- 感染症拡大時の事業継続体制
- 職員の初動行動・役割分担の明確化
が、施設経営の「当たり前のリスクマネジメント」として強く求められる時代に突入しました。
※BCPが義務化された背景や、策定方法、未策定時の減算などについては以下の記事で詳しく解説しています。

BCP減算(業務継続計画未策定減算)は、BCPの未策定が発覚したタイミングから減算が適用されるではなく、発覚した以前の期間においても適用されるため、未策定の事業所はなるべく早くBCPを策定することをおすすめします。
とは言え日々の業務が忙しい中で、BCPを策定することはなかなか難しいですよね。そこで介護のコミミでは書類作成を効率化するためのひな形も無料でプレゼントしています。
介護のコミミでは、BCPの策定に必要な書類作成の業務を効率化できるよう、BCPの書類サンプルとひな形を無料でプレゼントしています。
以下より、訪問系サービス向けのBCP書類サンプルとひな形を無料でダウンロードいただき、ぜひご活用ください。
忙しくて研修の準備に手が回らない
いくらBCPの研修実施が義務化されたことに対し、BCP研修を担当することになった職員や管理者にとっては、以下のように感じることが多いのではないでしょうか。
- 「日常業務で手いっぱいで、研修準備に時間が取れない」
- 「何から手をつけていいか分からず、手間ばかりかかる」
- 「資料作成や進行準備が想像以上に大変」
限られた時間と人員で、いかに効果的な研修を実施するかが、大きな悩みになっています。

そんな研修に関する課題の解決策におすすめなのがeラーニングです。eラーニングを活用することで、研修の準備や実施にかかる時間を大幅に削減することができます。
2. 介護のBCP研修とは?具体的にどんなことを学ぶのかを解説
先述の通り、2025年4月より完全義務化となった介護事業所のBCPですが、大事なポイントはBCPを作っただけでは不十分で、職員全員が理解・行動できる状態を作ることです。そのため、BCP策定後に適切な研修を実施することが必要になるのです。

どれだけ立派なBCPを策定しても、職員の理解が不足していたり忘れてしまっていると、いざという時に機能しない可能性があり、せっかく作った計画がもったいないですよね。そこで、BCP研修では具体的にどんなことを学ぶのかを解説していきます。
BCP研修の対象者と必要な研修内容
まず、研修の対象となるのは、すべての職員(正職員・パート・派遣含む)です。役職や雇用形態に関係なく、災害・感染症発生時に業務に関与する可能性のある人すべてが対象となります。
研修内容は、以下のようなポイントをカバーする必要があります。
| 研修項目 | 内容例 |
|---|---|
| 初動対応の流れ | 通報、避難誘導、連絡体制 |
| 役割分担 | 指揮系統、班ごとの任務 |
| 利用者対応 | 移動支援、健康管理、安否確認 |
| 感染症対応 | 感染拡大防止策、ゾーニング |
| 事業継続体制 | 代替事業所活用、外部支援依頼方法 |
なお、厚労省のガイドラインでは「自然災害対応編」と「感染症対応編」に分けて、訓練・研修を行うことが推奨されています。
こうして見ると、研修で対応しなければいけない内容が多く、準備にも手間がかかるのではないかと感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで、研修準備の手間を少しでも減らすために、eラーニングを活用することを検討してみてはいかがでしょうか。
介護のコミミでは、eラーニング導入のメリットや、おすすめのeラーニングサービスを紹介しているので、以下から閲覧できる記事をぜひ参考にしてください。
eラーニング導入のメリットやおすすめサービスを知るBCP研修において自然災害編と感染症編の違いは?
厚生労働省のガイドラインでは、自然災害対応編と感染症対応編の2つに分けて研修を行うことが推奨されています。これは、自然災害と感染症という2つの異なるリスクに対して、それぞれに応じた想定訓練(机上訓練など)を別個に実施する必要があるためです。
具体的には、以下のような内容がそれぞれの編で対応すると良いでしょう。
| 編別 | 主な対応内容 |
|---|---|
| 自然災害対応編 | 地震・台風・豪雨などに備えた初動行動、避難誘導、地域との連携体制 |
| 感染症対応編 | 新型コロナウイルス等に備えた感染拡大防止策、ゾーニング、感染者発生時の対応マニュアル |
では具体的に、どのようにこれらの研修を実施していけば良いのでしょうか。次章では、厚生労働省が提供している公式研修資料や動画を活用して、研修準備を効率化する方法を紹介していきます。
3. BCP研修の公式資料・動画を活用する方法
BCP研修を実施しようと思った際に、最も手軽に研修資料を入手できる方法は、厚生労働省が公式に公開している資料や教材を活用することです。
そこで、ここでは厚生労働省の資料・ガイドライン・研修動画を手に入れる方法を解説していきます。
厚生労働省の資料・ガイドライン・研修動画を手に入れる方法は?
厚生労働省が公式に公開している資料や教材で特に役立つのは、以下のコンテンツです。
| 資料・教材名 | 主な内容 |
|---|---|
| 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援マニュアル | BCPの作成から職員研修・訓練までの総合的なガイドライン |
| BCP作成・研修に関するQ&A集 | よくある疑問に対する公式回答 |
| BCP研修用 動画教材(自然災害編・感染症編) | 職員向けの分かりやすい解説動画 |
これらの資料はすべて、無料でダウンロード・閲覧できます。
参考:厚生労働省『介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)』
厚生労働省の資料を使うメリット
厚生労働省資料を活用する最大のメリットは、以下の点で「信頼性」と「網羅性」が確保されることです。
- 改訂される最新基準に基づいて作成されている
- 研修の到達目標や必要項目が整理されている
- 監査・指導にも対応できるレベルの内容
- テンプレートとしてそのまま使えるパーツが豊富
- 基本的に無料で入手できる
言うまでもなく、こうした資料や教材を叩き台として利用することで、自身ででゼロから資料を作成する手間もコストも削減できます。
4. 介護BCP研修を効率的に実施する方法
さて、資料を手に入れたら、後は実際に研修を実施していくだけです。そこで、次章では実際にどのようにBCP研修を進めるべきか、実施ステップについて解説します。
4-1. 最適な研修形式を選ぼう
まず、BCP研修を効率的に進めるために最初に検討すべきなのは、「どの形式で研修を実施するか」を決めることがとても重要です。研修の実施形式は大きく以下の3つに分けられるため、事業所のニーズと照らし合わせて、どの形式が最適かを検討することになります。
| 研修形式 | 特徴 | 向いている事業所 |
|---|---|---|
| 集合型研修(対面) | 職員同士で意見交換しやすい | 小〜中規模、現場密着型 |
| オンライン研修(Zoom等) | 時間・場所の制約が少ない | 複数拠点を持つ事業所 |
| eラーニング(個別受講) | 個々のペースで学習できる | 業務スケジュールがバラバラな施設 |
上記の中でもとりわけ近年人気なのがeラーニングです。そのメリットを知るとなぜ人気なのかが分かるでしょう。
eラーニングのメリット
- 管理者が研修(講師や教材の手配、スケジュール調整など)を準備する必要がない
- 好きな場所、好きな時間で受講できる
- 同じカリキュラムを再利用できるため学習の質にバラつきが生まれにくい
上記のメリットから、特に「業務が忙しい」「シフト勤務が多い」介護事業所ではeラーニングや録画研修を組み合わせることを強く推奨します。
eラーニングでは無料お試しから始めることができるサービスが多いため、まずは無料で始めてその効果を実感すると良いでしょう。介護のコミミでは、以下の記事で無料お試しから始めることができるおすすめのeラーニングサービスを紹介しているので、ぜひBCP研修の実施と併せてeラーニングの導入も検討してください。

もちろん、eラーニングはBCP研修以外にも多くの研修で活用できます。近年、介護のコミミを通じてeラーニングを導入している事業所が増えてきているので、ぜひ参考にしてください。
4-2. 30分・60分でできる介護BCP研修スケジュール案
短時間で完結できる研修スケジュール例を紹介します。
例1:30分版プログラムの場合
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 0〜5分 | 研修目的の説明 |
| 5〜15分 | BCP基本知識(自然災害編・感染症編) |
| 15〜30分 | 机上訓練(避難誘導シナリオ確認) |
例:60分版プログラムの場合
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 0〜10分 | 研修目的・BCP概要 |
| 10〜30分 | BCP実践ポイント講義 |
| 30〜55分 | グループディスカッション(机上訓練) |
| 55〜60分 | まとめ・質疑応答 |
4-3. 机上訓練の進め方とシナリオ例
BCP研修の中で最も重要なのが机上訓練ですが、もちろん研修の中で最も難しいのも机上訓練です。
そこで、ここでは机上訓練の進め方とシナリオ例を解説していきます。
机上訓練とは?
机上訓練とは、ある災害や感染症発生シナリオを設定し、職員がそのシナリオをもとにどう行動するかを考え、共有する訓練です。
簡単にできるシナリオ例
以下は、簡単にできる机上訓練のシナリオ例です。
| シナリオ | 内容 |
|---|---|
| 【自然災害編】夜間、地震発生→停電→避難指示 | 地震発生後、停電が発生し、避難指示が出された場合のシナリオ |
| 【感染症編】利用者に発熱者発生→隔離対応→施設内拡大防止策 | 利用者に発熱者が発生し、隔離対応が必要な場合のシナリオ |
机上訓練に失敗しないためのコツ
机上訓練を失敗しないためのコツは以下の通りです。
- 難しい資料を読み込ませるより、「行動をシミュレーションさせる」
- 少人数(3〜5人程度)でグループワーク型にする
- 振り返りシートを活用して、気づきを可視化する
準備の手間が少なく、効果が高いため、「時間がない現場」でも非常におすすめできる手法です。
4-4. 研修準備・実施・記録を仕組み化しよう
研修準備・実施・記録を仕組み化することで、翌年以降の研修準備を効率化できるほか、運営指導対策にも役立ちます。
研修準備・実施を簡単にできる工夫の例
研修準備・実施を簡単にできる工夫の例は以下の通りです。
- 年間計画に組み込んで「自動実施」する(例:毎年5月に実施する、など)
- 職員へ事前アンケートを取り、興味あるテーマを反映する
- 実施後は「参加者名簿+簡単な所感記録」だけでもOKとする
記録を簡単にするテンプレートの例
記録を簡単にするテンプレートの例は以下の通りです。
- 研修実施記録簿(日時・参加者・内容・気づき)
- 訓練振り返りシート(良かった点・課題・改善案)
テンプレートを用意しておけば、毎回「ゼロから作成」する負担をなくせます。
5. 研修を外部講師に依頼する場合のメリットと注意点、デメリットは?
BCP研修でeラーニングを活用しない場合は、研修を外部講師に依頼するケースも選択肢としてありますが、ここでは研修を外部に依頼する場合と自社で完結させる場合の比較を見ていきます。
研修を自社実施する場合と外部委託する場合の比較
BCPに限らず、研修を自社実施する場合と外部委託する場合を検討する際、一概にどちらが良いと言ったことはなく、それぞれにメリット・デメリットがあるため、事業所のリソースや状況に応じた選択が重要です。
そこで、ここでは研修を自社実施する場合と外部委託する場合の比較を見ていきます。
| 項目 | 自社実施の場合 | 外部委託の場合 |
|---|---|---|
| 研修準備の手間 | 資料作成・講師進行の負担あり | 準備・進行を講師に任せられる |
| 研修の柔軟性 | 自社の状況に合わせた内容が可能 | 画一的な内容になりやすいことも |
| 研修の専門性 | 担当者の知識に依存 | 専門家による最新情報・実務経験を反映 |
研修を外部講師に依頼するメリット
メリット1:最新の専門知識と実務ノウハウを学べる
外部講師は、厚労省ガイドラインに精通しているだけでなく、実際の災害・感染症対応経験が豊富なため、現場に即した生きたノウハウを伝えてくれます。
メリット2: 職員の意識改革がしやすい
外部講師は、職員の意識が自然と高まる効果も期待できます。
メリット3:担当者の負担軽減
外部講師は、担当者は最小限のサポートで研修を完結できます。
外部講師に依頼する際の注意点
外部講師に依頼する際の注意点は以下の通りです。
注意点1:費用感を事前に確認しておく
外部講師依頼には、講師料や交通費、資料印刷費などのコストがかかります。予算とのバランスを慎重に確認しましょう。
注意点2:自社の状況に合わせたカスタマイズをお願いする
講師によっては、「テンプレート的な一般論」だけで研修を進めるケースもあります。事前打ち合わせで、自社の規模・サービス種別に応じた内容や自然災害・感染症それぞれの重点ポイントをしっかり伝えてカスタマイズしてもらいましょう。
注意点3:フォローアップ体制を確認する
単発で終わらない支援が得られる講師を選定基準にすると安心です。
外部委託に向いている事業所は?
新設・小規模でBCP策定経験が浅い事業所や、自社に研修進行できる人材がいない事業所、厚労省通知に完全準拠した内容で確実に対応したい事業所は、外部講師活用を積極的に検討してもよいでしょう。
自社実施+必要に応じてポイント支援だけ受ける方法も良い選択肢になるでしょう。
6. 介護BCP研修に関するよくある質問(Q&A)
最後に、介護BCP研修に関してよくある質問をまとめました。
Q1. 介護BCP研修はどれくらいの頻度で実施すればいいですか?
原則、年1回以上の定期的な実施が義務とされています。
特に、
- 新規職員が入職したタイミング
- BCPの見直し(改訂)を行った後
には、臨時で追加研修を実施するのが望ましいとされています。
参考:厚生労働省『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について』
Q2. 介護BCP研修にはどれくらいの時間をかけるべきですか?
30分〜90分程度を目安にする事業所が多いです。
- 30分の机上訓練中心でも可
- 時間に余裕があれば60〜90分で講義+演習(机上訓練)を組み合わせると効果的です。
ポイントは、「座学だけでなく実践的なワークを含めること」です。
Q3. 介護BCP研修をオンラインやeラーニングだけで実施してもいいの?
オンライン研修やeラーニングのみでも、要件を満たすことは可能です。
注意点としては、
- 「誰が受講したか」の記録を必ず残す
- 理解度を確認する
といった対応が求められますが、eラーニングの場合はこれらの対応を自動で行ってくれるサービスが多いため、そちらを利用するのもおすすめです。
対面型でしかできない演習を補う工夫(例:Zoomグループワーク)を行うと、より実効性の高い研修になります。
Q4. まだBCPを策定していない場合、研修はどうすればいい?
仮でもいいので「簡易版BCP」を作成し、それに基づく研修を行うことが大切です。
- 厚生労働省提供の「BCPのひな形」を活用する
- 自社に必要な最低限の行動計画(初動・連絡体制など)をまとめる
策定と研修を並行して進めることも可能です。
Q5. 介護BCP研修を義務化に対応できていないと、どんなリスクがある?
BCP策定・研修未実施の場合、以下のリスクが懸念されます。
- 行政指導・是正指導の対象になる
- 介護報酬減算や更新時ペナルティリスク
- 災害・感染症発生時に適切対応できず、利用者に重大な影響を及ぼす
最低限のBCP策定+研修実施だけは必ず対応しておきましょう。
7. まとめ:介護事業所の危機対応力を高めるために、効率的なBCP研修を!
BCP研修は「一度やって終わり」ではありません。
- 職員の入れ替わり
- 社会情勢の変化(新たな感染症、災害リスク)
継続的に見直しと改善を行っていくことが不可欠です。
だからこそ、多忙な日常業務でBCP対応を継続していくには、効率的な研修実施が重要となっていくため、今回紹介した情報がみなさんの業務負担軽減の役に立てればと思います。
「記事を読むより、一刻も早く研修の負担を減らしたい」
「記事を読んでも、次に何をしたら良いかがわからない」
そんな方には、複数の研修サービスの一括資料請求して、無料体験から始めてみることをおすすめします。
研修の負担軽減に成功している事業所のほとんどは資料請求から始めています。
最短60秒!無料でできる
介護研修サービスの一括資料請求をする
注目の記事
 とは
とは
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する