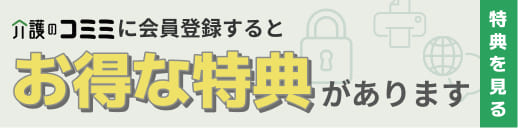介護保険負担の公平化実現へ – 制度改革の必要性を財務省が強調
ニュース
財務省は11日に開かれた財政制度等審議会にて、介護保険の財政負担増を背景とした介護保険制度改革の必要性を強調した。審議会にて提出された資料では、改革の1つとして介護保険負担の公平化を目的とした、負担対象の拡大についても言及されている。
参考:『社会保障② – 財政制度分科会(令和7年11月11日開催)資料』(財務省)
制度改革が必要とされる背景
介護保険制度は高齢化の急進と現役世代の減少により、介護費用と保険料が大幅に増加し制度の持続性が揺らいでいる。特に要介護認定率や給付費の高い85歳以上人口が急増する一方、支え手となる40〜64歳層は減少を続け、世代間の負担の偏りが拡大している。この構造的変化に対応するため、負担と給付の見直しが不可避と考えられている。
制度改革の内容
資料では介護保険制度改革の主な内容として、以下の具体案が記載されている。
介護保険負担の公平化
介護保険制度では、高齢化の進展と現役世代の減少により費用負担の偏りが拡大しており、負担の公平化が急務となっている。利用者負担は長らく横ばいが続く一方、現役世代の保険料は増加しており、世代間の不均衡が強まっている。このため、二割負担の範囲拡大や原則二割化、三割負担の基準見直し、資産や金融所得の勘案など、多角的な制度再設計が検討されている。ケアマネジメントへの利用者負担導入や多床室の室料見直しなども含め、より持続可能で公平な負担構造を構築する必要が高まっている。
担い手の確保と給付の効率化
担い手不足と給付の非効率性に対応するため、介護分野では複合的な改革が求められている。介護職員の処遇改善による人材確保に加え、ICT機器の活用や事業所の協働化によって業務効率化を進め、生産性向上を評価する報酬体系への転換が進められている。また、軽度者の生活援助を地域支援事業へ移行させることや、保険外サービスの活用、高齢者向け住まいの報酬体系の見直しなど、給付の適正化を図る取り組みも広がっている。これらは限られた資源を有効に配分し、持続可能な供給体制を確保することを目的とした改革である。
今後の見通し
今後の介護保険制度は、高齢化と費用増大が続く中で抜本的な見直しが避けられない状況にある。特に利用者負担区分やケアマネジメントの扱いなど重要項目は、次期計画期間が始まる2027年度までに結論を出す必要があるとされ、改革は段階的かつ継続的に進む見通しである。
将来推計では介護費用が2040年に現在の約二倍へ拡大する可能性が示されており、財政負担の抑制と制度持続の両立が最大の課題となる。このため、負担の最適化、給付の重点化、担い手確保を組み合わせた総合的な制度改革が求められている。